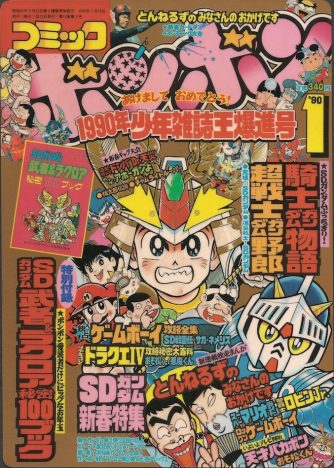藤谷千明×横川良明が語る、オタクとして楽しく生きる方法 「推し活動だって生涯続けられるのかもしれない」

今、推しを推すオタクとして求められるもの
藤谷:私はビジュアル系がメインジャンルなんですけど、昔はオタクジャンルとしては認識されていなかった記憶があります。でも最近は「ユリイカ」(青土社)の女オタク特集(2020年9月号「女オタクの現在」)で「ビジュアル系について」と執筆依頼がきたり、世間的にはオタクの範疇になっているようで。趣味に熱量を持った人は全部「オタク」になったのでしょうか。だから横川さんの本を読んで共感される方も多いんだろうなと思いました。執筆するときに、共感される、SNSでバズるというのは意識されましたか?
横川:実はバズることはそんなに意識してないんですよ。それよりも意識したのは、切り取られて怖いところがないかどうか。性的消費やルッキズムの問題が叫ばれる時代に、どこまで書いて大丈夫で、これ以上はよくないかという線引き。「推しの顔がいい」みたいな話をどうやったら人を不快にさせずに面白く書けるか。webだったら燃えるけど、紙(書籍)だったら燃えないかなとか。バズらせ方よりも、バズらない方向をすごく考えましたね。
藤谷:なるほど。私が編集さんと相談した時は、“残るもの”という点を意識しました。いわゆるツイッター構文など現代のネットのオタク用語を多用してはいるんですけど、由来が差別的だったり特定の人を傷つけたりするワードは避けたつもりです。
――横川さんの本を拝読すると、あえてそう書いている部分もあると思うんですが、全体にすごくポジティブなオタクなんだなという感じがしました。オタクであることを素直に楽しんでいらっしゃるな、と。
横川:それはすごく意識しています。自分自身のあり方としても。
藤谷:自分は屈折したオタクなので、それがまぶしいなと思いました。。
横川:僕は陽のオタクでいようと思っています。根はネガティブなので、ハレの場に行くつもりでオタクをやっているんです。違う自分になれるし、オタクをやっていると自分の気持ちが浄化されていると感じるので。だからオタクの自分と本当の自分は、地続きじゃないんですよね。根本的なオタクではないし、歴も短い。もともとの自分があまり好きじゃなくて、何かバージョンを変えたくてオタクになりました。陰になる理由がないとも言えますね。
藤谷:オタクという言葉のイメージってもともとはネガティブでしたよね。子どもの頃からオタクだった私としては、それを理由にバカにされることもあるけど、どちらかというと日陰者であることに心地よさを感じていました。石の下にいる虫みたいに、「この暗くてジメジメした場所がいい」的な。それが、先日読んでいた女性ファッション誌で「オタクは暗いなんて古い! ひとつのことを探求するのは素敵なこと」みたいなフレーズを目にして、すごい時代が来てしまったなと。
横川:人によっては、「広めてくれるな」っていう人もいますよね。別に拡大しなくていいんですが、と。
藤谷:私はそういうタイプのオタクでした。オタクとは隠れるもの、と思っていた。だから私、ライターとして自分の好きなジャンルであるビジュアル系の仕事を始めるときにすごく悩んだんですよ。こんなヌルいファン崩れが世にしゃしゃり出てもいいのだろうかと。
横川:ハハハ!
藤谷:ただその一方で、自分よりジャンルの解像度が低そうな人の雑語りをみて、「これは私がやったほうがマシなのでは」と思ったんです。仕事を始めた理由が屈折してるんですよね(苦笑)。
横川 僕は逆にそこがないんです。どのジャンルを語る上でも「自分のほうが詳しい」って思ったことが一回もない。2.5次元も『テニミュ』の初代から見ているわけじゃないし、『刀剣乱舞』もゲームからやりましたけど、ファンのみなさんの熱量にはとても勝てない。演劇は好きですが、いわゆる本流の作品にはそんなにハマれない。どこの沼とも相容れてないなっていう実感はあります。
藤谷 その「軽やかさ」は自分にはないものです。
横川 でもオタクになって、好きなものについて話すのが楽しかったんですよね。ポジティブなものを共有してることが楽しいっていうのが、オタクとしてのルーツです。それも生粋のオタクじゃないからなんでしょうね。
藤谷 ある意味、オタクという状態に対する「新規ハイ」が続いているということなんですかね?
横川 「新規ハイ」、そうかもしれないですね。