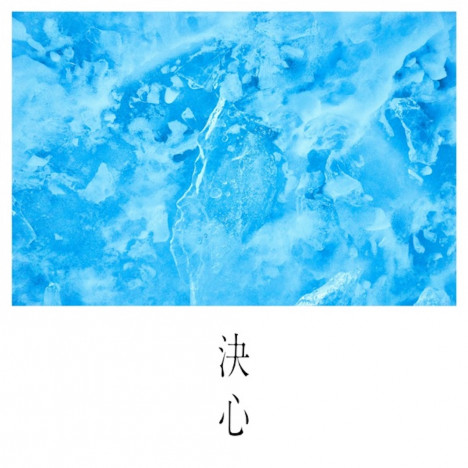SHE'Sは味方であり続ける バンドの音楽性を象徴した『Memories』ツアーの意義

SHE'Sが7thアルバム『Memories』を携えて、13公演にわたる全国ツアー『SHE'S Tour 2024 “Memories”』を開催。東京は初めての会場である豊洲PITで11月15日にライブを行った。キャリアを重ねレパートリーも増え、ファンが聴きたい曲も多様になった今、本編もアンコールもほぼ毎公演セットリストを変えていた今回。ニューアルバムを軸にしつつ、新旧のファンを納得させた。

会場が暗転する前から「Dull Blue」がオープニングSEとして流れ、鳥の声が響く見晴らしのいい丘の上にいるような擬似的な体感を得たところにメンバーが登場。アルバム同様「Cloud 9」の井上竜馬(Vo/Key)のアルペジオと歌が響く。メンバーの音がひとつずつ加わっていく構成が、井上がメンバーに向けて書いたこの曲の意図を生で理解できるようで、このスタートがツアーを象徴するかのよう。


晴れやかさはそのまま「追い風」に繋がる。ストリングスのSEが景色を変えた「Raided」では広瀬臣吾(Ba)のボトムを支えるベースサウンドが際立つ。全体的に緩急が効いていて、各楽器の聴かせどころがスッと入ってくる。そして、早くもサポートメンバーの永田こーせーが加わり、ダイナミックなライブアレンジで「Over You」を展開。井上の声色もおどけたりセリフ調になったり、リラックスしたムードが伝わる。浮遊感溢れるポップなソウル「No Gravity」もサックスが生であることや、服部栞汰(Gt)の艶っぽいギターソロでグッとライブチューンに成長した感じ。さすがツアー中盤である。


井上もギターを弾く「Kick Out」は、久しぶりにストロークでガシガシ押すサビが痛快。ロックバンドのギターソロは服部の真骨頂である。いつも通り、別に煽ることもなく淡々と演奏をし、曲数を重ねているだけなのに一つひとつのライブアレンジがバンドの伝えたいことを雄弁に語る。続く「Ugly」のイントロでのサックスも含む厚み、一転、Aメロで際立つ不穏なシンセベースは特に効果的。井上の怒気やシニカルさを含んだ声の表現もストッパー知らずな感じだ。オーディエンスの情緒のアップダウンを楽しんでいるのか? と訝しむ、Aメロは井上の繊細な歌で牽引し、2番Aメロからバンドインする「Angel」への落差が凄まじい。

前半でオーディエンスの集中力を最も高めたのは「Lamp」と「Unforgive」の並びだったんじゃないだろうか。ニューアルバムのなかではシリアスな「Lamp」の歌詞が非常に入ってきたのだ。自分の手に負えないような混沌が広がる時代を肌身で感じる今、アルバムでは一見地味だが光る曲という個人的な感触から、ライブで一気に重要な一曲になった。困難や怒りを表現した2曲の後に至上の(でもさりげない)ラブソング「If」をセットしたのも胸が締めつけられる思い。重厚でダークな曲の連なりはSHE'Sの見せ場のひとつだが、今回はダークさよりシリアスなベクトルで、新たな起伏を作り出した感じだ。

MCでは井上が『Memories』がポジティブな思い出で構成されていることを語り、加えて今作だけでなく、彼のソングライトの多くを占めてきたことを窺わせたのが初期曲からのピックアップ「Long Goodbye」だった。さよならの悲しみを凌駕するのも思い出の力だなと感じさせる。ぜひ、生のストリングスで聴きたいと思った。続くピアノと井上のファルセット、さらにコーラスで聴かせる「カフネの祈り」での、母親が生まれた子どもの幸せを祈るような歌詞がふたつの曲を呼応させる。同時に日本のバンドにおける稀有な個性を感じる場面だった。

ピアノが際立つスローは「Letter」に自然に繋がり、この曲同様、ファンに深く愛されている「White」へ。ひとりの人間としての成長を思わせるセットリストにもう一段の力強さを加えたのが、ゴスペルクワイヤやソウルミュージックの要素が色濃い「Alright」だった。ライブでは永田のブロウや服部のブルースマナーのソロがショー的な盛り上がりを加速させ、音源のストイックさを超え、その興奮は拍手と歓声の大きさに表れていた。

ストーリー性のあるセクションのあとはキッズに戻ったようなポップパンク「I’m into You」、初期からのライブ定番曲「Un-science」を披露。「Un-science」にパレードのような躍動感を与える永田のフルートも効果的だ。そして、ここ最近のライブでキラーチューンになったような感覚のある「Grow Old With Me」は、イントロの音をキャッチしたフロアがざわめき始める。井上がゆっくりAメロを歌い出すと、もうサビのクラップを待ち構えている空気があるなのだ。サビで大きく乾いたクラップが残響多めのこの会場に響き渡る。井上のラグタイムっぽさのあるピアノが奏でるグリッサンドで、さらに会場全体が躍動する。彼のエンターテイナーぶりが発揮される「Dance With Me」へと“With Me”つなぎでシンガロングとクラップは最高潮に達した。それにしても、レパートリーの音楽的な多様さは過去を含めて今が最もレンジが広いんじゃないだろうか。そこはライブアレンジの肝と言えそうな木村雅人(Dr)のプレイヤーとしての成熟が大きいと感じる。