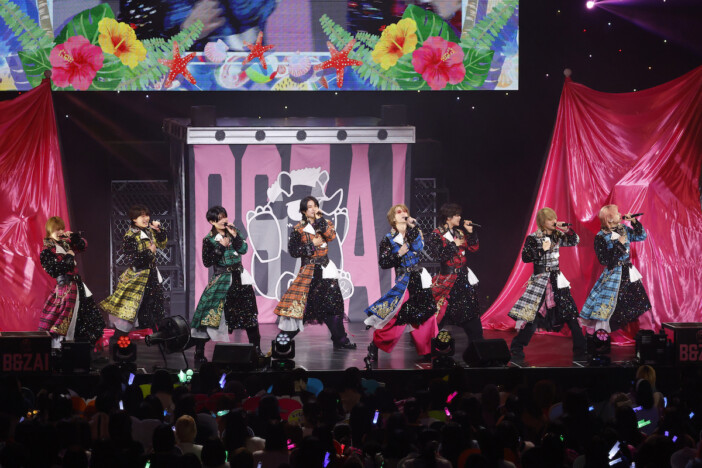坂本龍一との別れから一年に寄せて 日常に根付いていた“世界のサカモト”の音楽
坂本龍一がこの世を去って一年が経ち、あらためて気づかされることがある。それは彼の活動がいかに私たちの“日常”に根付いていたかだ。それは、“もう新作が作られることがない”という物理的な意味だけではなく、“坂本龍一がいなくなった”という現実的な感触の意味でもある。
坂本龍一の素晴らしい楽曲性や功績については、すでに膨大な言及がなされているのでここで詳細を振り返る必要はないだろう。それでも、2023年12月16日から今年3月10日までICC(NTT InterCommunication Center )で企画展『坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア』が開催され、彼がインスタレーション(現代美術表現)を用いて伝えようとした考えが、今後を生きる人類に課題と刺激を与えたという点で、逝去してもなお多大な影響力があることが示された。また、先日行われた『第47回 日本アカデミー賞』で会長特別賞が贈られたのも、日本のみならず世界中の映画作品において、音楽をもってして作品性を高めたことへのリスペクトにほかならない。
「リアルサウンド テック」
坂本龍一は「新しいテクノロジーと向き合い続けた人」だった
ライゾマティクス・真鍋大度が語った
“トリビュート展”実施の意義
文・取材=白石倖介https://t.co/apZyO6iaQu— NTT ICC (@NTTICC) March 10, 2024
存命中に心血を注いだ、環境保護活動や社会活動の数々ももちろん触れておかねばならない。そのひとつとして、坂本龍一は2011年に発生した東日本大震災直後から被災地支援を行っていたが、「心の復興」を掲げ、亡くなる直前まで監督として指導してきたのが東北ユースオーケストラだ。同オーケストラは3月23日から東北3県と東京で計4公演に及ぶ追悼公演を開き、彼が震災犠牲者への祈りを込めて書き下ろした曲「いま時間が傾いて」などを演奏。これらの模様を伝えた3月21日付『読売新聞オンライン』の「震災の記憶がない団員も増えている」の記述(※1)を読み、坂本龍一の遺志が蔦のように伸びていることが感じられた。それとともに、1月1日に発生して甚大な被害となった能登半島地震の被災者/被災地に自分はいったい何ができるのだろう――この数カ月の自問自答を再考する機会にもなった。
坂本龍一は、さまざまな人々に寄り添って社会活動を行い、地球規模での総体的課題を訴えていた。こと音楽面など創作においてはその総体性がより強く、いわゆる“ドラマ”というものへの反応が薄かったところが興味深い。
後藤繁雄との共著『skmt 坂本龍一とは誰か』(2015年/ちくま文庫)のなかで坂本龍一は、自分は『ウルトラマン』世代ではなく『ウルトラQ』世代だと話していた。彼は『ウルトラQ』について「あれは断片的ですよ。哀しみがある。物語なんてなくて、魚の格好してたり、ただ存在の苦渋に満ちているだけでさ」「『ウルトラマン』以降は完全に“物語”でしょ。みんな『宇宙戦艦ヤマト』とかのアニメ世代だから。だからゲームも物語性が強くって、チープな神話性みたいなのに回収される。ひとつの目的に向かって、突っ走って勝ち抜いていくっていうのはつまんない」のだという。
たしかに、彼は映画音楽を手掛ける際も、人物の内面や物語を表すための音楽は作っていなかった印象がある。
そうではなく、たとえば『アレクセイと泉』(2002年)や『Derrida』(2002年)であれば、ドキュメンタリー映画という特性もあってその映像のなかで実際に鳴っている“自然”な音に音楽を組み合わせていた。そういった手法は劇映画の『トニー滝谷』(2005年)などにも適用されていて、その最高峰とも言えるであろう『レヴェナント:蘇えりし者』(2015年/日本公開は2016年)では、自然や野生の音と音楽が境目なく融合していた。2010年に放送されていた『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』(NHK Eテレ)でも、彼は映画音楽について「映画ではなく、映像につける音楽」というイメージで作っていると語っていた。
そこで合点がいったのが、3月27日放送のバラエティ特番『くりぃむカズVS100人の天才』(日本テレビ系)でも明かされていた、坂本龍一の“天才エピソード”である。
大島渚監督から映画『戦場のメリークリスマス』(1983年)への出演依頼を受け、「音楽も担当させてもらえるなら」との条件で受諾した坂本龍一。ところが、音楽がつけられる前の編集映像が出来上がった時、自分の演技のひどさに椅子から転げ落ちたのだという。そこで、自分の下手な演技を誤魔化すために“いい音楽”を考え、自分の登場シーンに当てはめたのだという。彼自身、「僕がラッキーだったのは、(自分の演技を)音楽で補完できる立場にあったこと」と口にしていた。まさに「映画ではなく、映像につける音楽」である。しかも、そんな「自分の見栄えをよくするための音楽」を含むサウンドトラックが世界中で高く評価されることになるのだ。
音楽でストーリーを物語るわけでもなく、人物の心情を代弁するわけでもない。ある意味、俯瞰的に場面を眺めて、その“空気”に合った音楽をつけるのが“坂本流”。だからなのか、ドラマ性の強い黒澤明監督の作品のほとんどが苦手で、日常を淡々と映す小津安二郎監督の作品のタッチを好んだとされている。