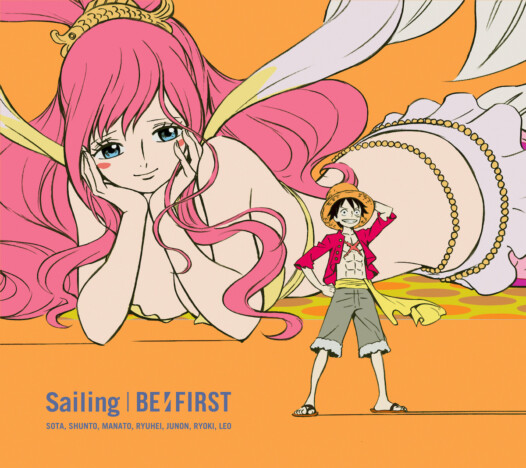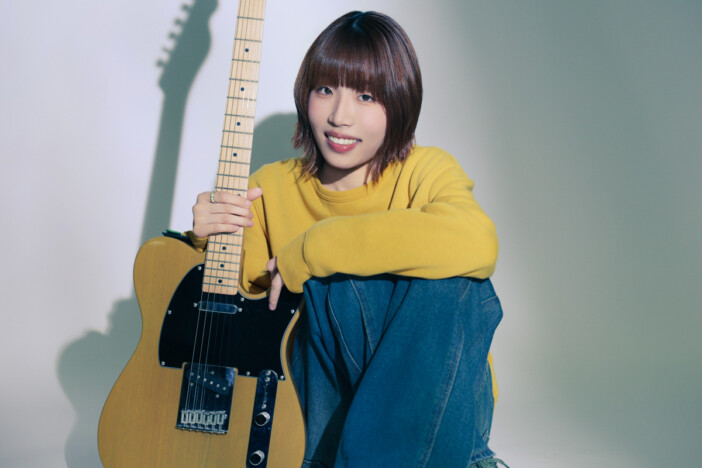Number_i、ONE OK ROCK、BE:FIRST、HANA……耳を惹き込む楽曲はなぜ生まれるのか? 徹底レビューで紐解く
街で耳を引く楽曲とは一体どのようなものなのだろうか。声なのか、メロディなのか、サウンドなのか、歌詞なのか。そこにはいろいろな理由があるだろう。リアルサウンドでは、今リアルタイムで街中に流れている、多くの人が一度は耳にしたことがあるであろう8つの楽曲をピックアップ。ライターの小川智宏氏、北野創氏、真貝聡氏、高橋美穂氏(五十音順)にそれぞれレビューしてもらった。
すでに話題となっている楽曲も多いが、なぜ多くの反響を呼ぶ楽曲となり得たのか、何が名曲たらしめているのか、そしてその楽曲が耳を引く理由とは何なのか――。ぜひ楽曲を聴きながら、その妙を紐解いてほしい。(編集部)
Aki「秘密の」
Akiが昨年1月に初のデジタルシングルとしてリリースした「秘密の」は、「Amazonプライム広告:アーバンジャングル」CM曲に起用されて注目を浴びた結果、Spotifyチャート「Daily Viral Songs(Japan)」で初登場3位にランクインした。YouTubeのコメント欄では「ワンフレーズだけで惹きつけられる」など絶賛する声が多く挙がっている。お店や街で流れていて気になった人も多いようで、Shazamの2024年8月30日付の日本チャートでは1位に登場。その後も同年9月25日付、今年2月12日付にも再び1位に返り咲きいた。リリースから一年以上のロングランを続けている。
では、なぜこの曲が多くのリスナーを魅了しているのか? まずは、Akiのハスキーがかった求心力のある歌声の力が大きいだろう。そして、楽曲全体の“構成力”の高さも光っている。色を失くしたモノクロの心に、少しずつ彩りが付き始めて、希望へと向かっていく歌詞。それと呼応するように、冒頭の囁くような歌、そこから声の体温が上がり、大きな広がりを見せていく、歌のなかでドラマチックな展開をつけているのも素晴らしい。(真貝)
Creepy Nuts「doppelgänger」
ジャージードリルを取り入れた「ビリケン」を経て、世界にその名を轟かせた「Bling-Bang-Bang-Born」で突き抜けた個性を確立して以降、明らかにネクストステップに進んだ感のあるCreepy Nuts。R-指定の変幻自在でスキルフル過ぎる変態的フロウも、DJ松永が生み出すタイプビート的な発想からはかけ離れた独創的トラックも、あまりにも唯一無二がゆえに、近作はすべて「初めての感覚なのにCreepy Nutsでしかない」という、アーティストとしては理想的な反転現象が起こっているように思う。だからこそ、ハードベース調のミニマルなビートと常よりもワルな雰囲気の高速フロウが中毒性を加速させる「doppelgänger」も、初めて聴いた瞬間にCreepy Nutsの楽曲だとわかりつつ、未知のものと出会えた興味や好奇心を刺激されて、何度も繰り返し聴きたくなる。それはまるでドッペルゲンガーと遭遇した時のように不思議な感覚で……なんて喩えは体験したことがないので言えないが、音楽に驚きを求めている人ならば必聴だろう。(北野)
天々高々「ロマンス」
「何よりも言葉の力を信じて活動してきたMOROHAのあの人」あふちゃん(MC)と「何よりも言葉にこだわり活動してきたシンガーソングライターのあの人」あいちゃん(Piano/Vo)のユニットとして、2025年から本格始動した天々高々。その1stシングルにして、いきなり世間をざわつかせている楽曲が「ロマンス」だ。2月14日=バレンタインデーにリリースされた、ど真ん中すぎるラブソング。なんといっても、「何回目!?」と言うくらい〈好きだ〉という歌詞が繰り返されるのだから。でも、その物語はロマンティックなだけではない。きらめきが転がるようなピアノに乗せて、〈占いでは相性は最低/でも会う度 会話 花が咲いて〉のラップから始まる恋は、瞬く間に現実を描いていく。〈料理は趣味 じゃなく家事になる〉〈叩く計算機 預金残金〉――そのなかの〈好きだ〉なのである。延々と続く〈好きだ〉に熱さや重さを感じる人もいるかもしれない。でも、重要なのはそこではなく、「ロマンス」は〈「愛してる」より「アイラブユー」より/「そばにいる」が実はなにより/ラブソング ラブソング/文脈なし 音程無視で歌う 歌いたい〉という天々高々の所信表明なのではないだろうか。泥臭い、汗臭い現実を生き抜く呪文のように〈好きだ〉と呟きながら、柔らかなコーラスに包まれる〈ハッピーエンド〉を目指す、“そのへんにいる僕ら”のための歌。(高橋)
Number_i「GOD_i」
今作はメンバーの岸優太がプロデュースを担当した楽曲で、作詞はNumber_iとPecori(ODD Foot Works)、作編曲はNumber_iとMONJOE(DATS)とSHUN(FIVE NEW OLD)が手がけている。テレビ局の単独取材で同曲のこだわった点を聞かれた際、岸は「何度も聴きたくなる曲をすごく意識した」と答えていた(※1)。いわゆる“スルメ曲”とも言えるが、この曲は街中で耳にした時に一発で心を掴まれて「ちゃんとフルで聴きたい」と思わせる魅力がある。同曲は次々に変則的なメロディやビートが繰り出される“予測不能”なところが印象的で、一曲を通して「こうくるのか!」と何度も驚かされる。神宮寺勇太の深みのあるきれいな歌から始まり、キックの連打とともに平野紫耀の無骨なラップへ移行し、今度は音数がタイトになり岸の中毒性の高いキャッチーなラップへと変わる。まるで別々の楽曲をつなぎ合わせているのではないか、と思うほど次から次へと新しい表情を覗かせる。にもかかわらず、一曲を通して聴くと整合性を感じるという、天才的なバランスに引き込まれる。(真貝)