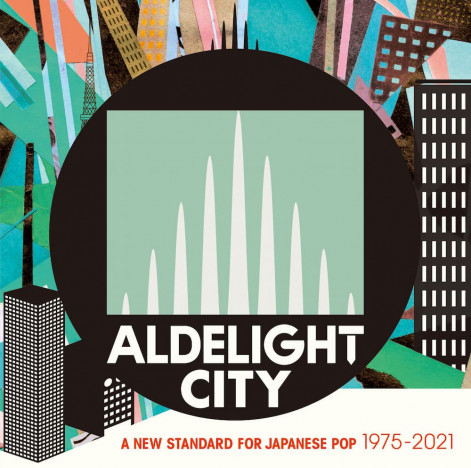『melody of memory - City Pop of Tetsuji Hayashi Selection』インタビュー
林哲司、シティポップ冠した洋楽コンピレーション選曲秘話 世界的ブームについて思うことも

松原みき「真夜中のドア~stay with me」や竹内まりや「September」などのいわゆるシティポップアンセムの他、クラシックから歌謡曲まで幅広いジャンルで活躍する作編曲家であり、シンガーソングライターでもある林哲司。彼が選曲を手掛けた洋楽のコンピレーションアルバム『melody of memory - City Pop of Tetsuji Hayashi Selection』が発表された。この作品は、自身に影響を与えた1960年代から90年代の楽曲がセレクトされており、メロディメイカーとしての林のルーツがわかる選曲となっている。また、土岐麻子による新録曲もボーナストラックとして収録するなど、温故知新を感じさせる内容だ。これまでにありそうでなかった新しいタイプのコンピレーションについて、じっくりと語ってもらった。(栗本斉)
林哲司に影響を与えたアーティスト/楽曲
ーーまず、どういう経緯で『melody of memory』が生まれたのでしょうか。
林哲司(以下、林):シティポップという視点で洋楽曲を選曲してみませんか、という依頼があったのが最初です。ただ、シティポップと言ってしまうと、どうしても80年代のAORに集中してしまうじゃないですか。実際、そのあたりの洋楽コンピは多いですから。だから、もちろんそういった楽曲は選びつつも、自分の作品に影響を与えた楽曲や、直接影響がなかったとしてもすごく好きで自分の生活に溶け込んでいるような楽曲も含めて選びました。また、シティポップにスポットが当たっているのが80年代で、自分が活動した年月もそのあたりに集約されているからかもしれないですが、自分が作るメロディの土台になっている音楽はそこだけじゃなくて、実際はもっと長い年月で聴いてきたものなんです。だから80年代の音源が中心ですが、そこにとらわれずに幅広く選びました。
ーーたしかにシティポップというと、どうしても70年代から80年代のAORやソウルのイメージがありますが、選曲は60年代から90年代まで幅広いですね。
林:そうなんです。でもそうなると、並べて聴いたら曲が変わるたびに急に時代の違いを感じることもあるので、そこは選曲だけでなく曲順やマスタリングで調整し、違和感がないように配慮しました。
ーー時代の振り幅もそうですが、AORやブルー・アイド・ソウルだけじゃなくてジャンルも様々ですね。シティポップという括りにしては意外な曲も入っていますし、そのあたりが林さんならではだと思います。
林:自分のルーツで言うと、どれが自分の音楽と直結しているかというのは一言では難しいですよね。The Beatlesから始まって色々な音楽を聴いてきましたが、ひとつ言えるのはMOR、いわゆるミドル・オブ・ザ・ロードです。中道路線というか、ポップでメロディアスなものが多いということですね。ロックでもギンギンのロックではないし、R&Bでもわかりやすくてポップなもの。音色的にもエッジが効いているものよりは、ソフィスティケートされたものが自分は好きなんだなと再確認しました。
ーー今回の選曲はすべてリアルタイムでお聴きになっていたと思うのですが、一番古いのはダスティ・スプリングフィールドの「恋の面影」で1967年の楽曲です。
林:これは映画『007/カジノ・ロワイヤル』(1967年)の主題歌ですね。ダスティ・スプリングフィールドは、後にエルヴィス・プレスリーが歌う「この胸のときめきを」のシングルを持っていてよく聴いていましたが、「恋の面影」はバート・バカラックが参加しているので選びました。実はこの曲を選んだのは最後なんです。一度すべて選曲した後に、なぜか僕が大きな影響を受けたバカラックが入っていないことに気付き、もう一曲入れられるということだったので選曲しました。
ーー同じ時代の楽曲だと、スティーヴィー・ワンダーの「マイ・シェリー・アモール」が1969年です。
林:スティーヴィーは70年代に入ってからシンガーソングライターとしての才能を発揮しますが、当時はまだ他の作家の曲も歌っているんですよ。この曲はシングルのB面でしたが、当時はそれが信じられなかったですね。でも、後にスティーヴィー自身で書いた曲がシングルカットされるようになっても、A面曲ってどれも彼の能力からすればとてもわかりやすい曲ばかりなんです。
ーーClassics IVの「トレーセス」やThe Grass Rootsの「恋は二人のハーモニー」までは林さんのデビュー前の楽曲ですが、このあたりはご自身の初ソロアルバム『ブルージェ』(1973年)にも近いのかなと思いました。
林:僕のデビューアルバムはThe Beatlesの影響が出ていると思うのですが、基本的にソフィスティケートされたものが好みなので、ソフトロックや少しソウルっぽいロックを選んでしまいますね。今回権利の関係で選べなかったのですが、The Associationがすごく好きで、コード進行などは影響を受けましたから。
ーー当時のソフトロックやポップスって、アーティスティックというよりは外部の作曲家が作るというイメージがあるじゃないですか。そういった作家の存在は当時から意識されていたのでしょうか。
林:それは全然なかったですね。クレジットを見て作家やミュージシャンといった裏方に目が行くようになるのは、日本にタワーレコードができた頃の70年代後半から80年代に入ったくらいからですね。それまではライナノーツに作曲家などが書かれていることはあっても、一般的に興味を持つことはあまりなかった。例えば、僕がバカラックを知ったのは、大学生のときに一緒にバンドをやっていた仲間のお兄さんがバカラック好きで、彼からそのすごさを教えてもらったんです。それでやっと、自分がFEN(Far East Network:進駐軍放送のこと)で聴いていて好きだった音楽がバカラックの曲だって知りました。僕が初めて買ったレコードは「リバティ・バランスを射った男」という西部劇のイメージソングなのですが、実はこれもバカラックだったということも後から知りました。

ーー林さんはシンガーソングライターとして1973年にデビューされましたが、1976年からは作家として楽曲提供もするようになったんですよね。
林:厳密にいうと、デビュー前に僕の担当ディレクターの別のアーティストに作品を頼まれて書いた曲もあるんですが、作家としての意識ではなかった。実際、僕が作品を提供するようになった頃は、まだ僕が提供できるような歌い手がほとんどいないんですよ。ポップスというと洋楽のカバーだったし。だから、大橋純子さんあたりが最初だと思いますけど、竹内まりやさんや松原みきさんが出てきて、ようやく僕が楽曲提供できる人が誕生したっていう感覚でした。
ーー『melody of memory』では、やはり1970年代後半から80年代にかけての楽曲がメインになっていますね。これらはやはりソングライターとしての林さんに直結していた楽曲ですか。
林:自分の仕事を暴露するみたいですけど(笑)。僕は作曲の資料として絶えずフェイバリットソングのカセットテープを作っていたんですよ。大量に仕入れたレコードを聴きながら、自分の意識に入ってきたものをそこに入れていましたし、ラジオもエアチェックしていたから、タイトルを聞き逃してもいい音楽だったらそのテープに入れていましたね。このテープが膨大な数あるんです。アレンジの参考資料にもなっていたし、実際に曲を作るときはそのテープからインスパイアされたこともあります。
ーーということは、実際に仕事の資料としてコンピレーションを作っていたようなものですね。
林:たしかにそうですね。あと、仕事とは別に自分自身のお気に入りのテープも作っていましたね。ドライブ用とか自分が楽しむために作っていたから、仕事用のテープとはまた違う視点のセレクトなんですよ。今回のコンピレーションはわりとそれに近いかもしれないですね。プライベートモードというか。
ーーその中でもAORはやはり軸になっています。ボズ・スキャッグス、スティーヴン・ビショップ、Playerなどがそうですが、彼らの音楽ってアレンジの妙やバックのミュージシャンも含めて制作スタイルやその背景に興味が行く音楽だと思います。林さんが目指していたのもそういった音楽でしょうか。
林:AORからは多大な影響を受けていることは確かですね。当時からフロントのアーティストだけでなく、クリエイターやミュージシャンといった作り手に視点がいきますし、構築されたものに対する興味を持っていました。他の産業でもアメリカやヨーロッパに追いつけ追い越せと頑張ってきた高度成長期という時代でしたが、音楽でもアメリカの音楽を研究しながら曲を作り、ミュージシャンも演奏を真似て自分のものにしていくっていうプロセスがありましたし。僕自身も、色々な海外の音楽のエッセンスを身体中に取り込んでからろ過して、いかに自分のカラーとして出せるかというがテーマでしたね。でもこれって、大先輩である服部良一さんを筆頭とする洋楽に影響を受けた作曲家たち、例えば中村八大さんや村井邦彦さんといった方たちがやってきたことで、その上に僕たちの音楽が成り立っているっていう気持ちもあるんです。そして、日本の音楽にここまで影響を及ぼす洋楽はすごいなと思いますね。
ーーピーター・アレンの「フライ・アウェイ」は、竹内まりやさんへの提供曲のセルフカバーです。
林:竹内まりやさんのアルバム『LOVE SONGS』には、僕が提供した「September」や「象牙海岸」も入っていて、「フライ・アウェイ」もそのレコーディングのときに初めて聴きました。でもまりやさんのとはまた少し違って、ピーター・アレンらしく作られているのが印象的なので選びました。この曲が入っている『Bi-Coastal』っていうアルバムがすごく好きなんですよ。
ーーAORとは別にブラックミュージックもコンピレーションの軸になっていると思うのですが、ここで選ばれているのはすごくポップな楽曲ばかりですよね。マイケル・ジャクソンではみんなが知っている有名曲ではなくて、「想い出の一日」を選ぶというのが林さんらしいです。DeBargeなどもそうですが、メロディ志向というか。
林:マイケルのこの曲を選んだのは、ビート感のある曲を歌っているマイケルではなく、バラードを歌えるマイケルっていうところなんです。バラードって歌の上手さが表に出るじゃないですか。Jackson 5の「アイル・ビー・ゼア」なんかもそうですけど、マイケルって本当に歌が上手いなって感じますよね。あとはアレンジもしっかりしているし、オーケストレーションも豪華だし。
ーーブラックミュージックでいうと、ブレンダ・ラッセルの「ピアノ・イン・ザ・ダーク」で始まるのが意外でした。とてもいい曲なんですが、オープニングにするにはちょっと地味じゃないかと(笑)。
林:本当だったら2曲目にあるボズ・スキャッグスの「ジョジョ」が1曲目ですよね(笑)。でもそれだと面白くないなって。自分らしいテイストで選ぶならこれなんですよ。ブレンダ・ラッセルの中でも地味なんだけど、いい曲ですよっていうことを声を大にして言いたい。ただ、当時のロックやR&Bなどと比べると、清涼飲料水みたいにきれいな曲だなと感じましたし、かえって目立っていた気はします。