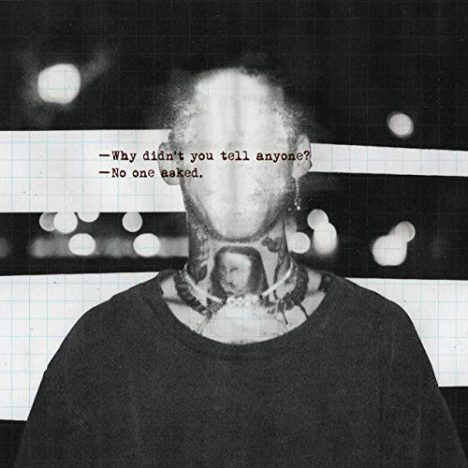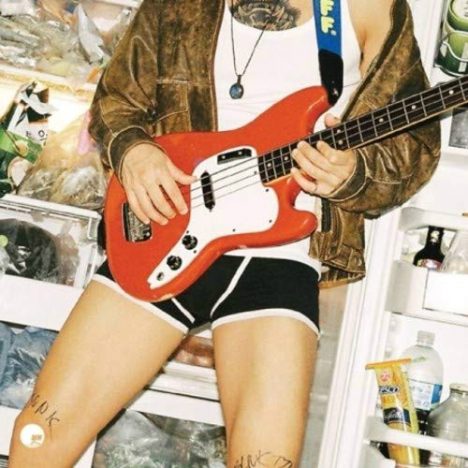ベストアルバム『ONES』インタビュー
ISH-ONE、ワールドワイドな活躍と今後「母国語で歌うことがユニークだと思ってもらえる状況に」

18歳で渡米し、バイリンガルスタイルなラップで日本のヒップホップシーンを席巻。ワールドワイドな活躍を見せているISH-ONEが自身初となるベストアルバム『ONES』を発売した。今回リアルサウンドでは、これまでのキャリアの振り返りだけではなく、日本と世界両方を見てきた彼が考える「日本の音楽が海外でどう戦っていくか」という戦略なども踏まえ、話を聞いた。(編集部)
色んな定義や意識も変わってきている

――今回、キャリア初のベスト盤を制作されたきっかけは?
ISH-ONE:2006年リリースの『ST-ILL』からこれまで5枚のアルバムを出してきて、6枚目のアルバムも完成間近で。だからそのタイミングで、自分の今までやってきた道のりを総括してみたいっていう気持ちがあったんですよね。ニューヨークから帰ってきて、日本でデビューしてからの13年に対して、いちど節目を入れた方が良いのかなって。
――ご自分のキャリアを纏められての手応えはいかがですか?
ISH-ONE:制作してた時に絡んでくれた人間や、客演してくれた人とのスタジオセッションを思い出したりして楽しかったですね。ベストっていう作品が作れるぐらい頑張ってきたんだとも自分で思えたし、過去曲のこっ恥ずかしい部分も含めて、ラッパーとして成長してこれたっていうのが見えたのも嬉しかったし、学びにもなりましたね。
―― 「ラジオ体操参拾八 ft’ SAGGA」や「NYJP」のような初期作は、現在のサウンドとはかなり違いますね。
ISH-ONE:そうですね。自分の作品でもそうだし、僕がニューヨークに渡ったのが98年だったんですけど、この20年でヒップホップ全体のサウンドが変わっていった流れを、ずっと目撃できたのはラッキーだったと思いますね。そして、その変化こそヒップホップかなと思うんです。時代時代によってリアルの定義の方も変わっていくと思うし、インターネットが未発達だった頃と、今みたいに誰でもネットにアクセス出来て、自分の音楽を自分で発信できる時代とでは、色んな定義や意識も変わってきてると思う。それこそ、昔だったらニューヨークに渡って、本場で黒人から教わらないとヒップホップじゃないとか、ストリートじゃなきゃみたいな、ヒップホップの固定観念があったと思うんですね。でも、いまはリッチ・ブライアンみたいに、インターネットで学んで、一気にスターダムに上るようなアーティストもいる。言語に関しても、昔だったら英語じゃなくちゃ世界には通用しないみたいなイメージもあったけど、今は英語じゃなくても、面白ければ聴いてもらえますよね。
――88rising勢のように、英語と母国語のミックスであったり、母国語が優先するようなアーティストにも注目が集まりますね。
ISH-ONE:僕も先日フランスでライブをしてきたんですけど、みんな日本語で反応してくれるんですよね。その数がスゴく多いかっていうと、そこまででは無いんだけど、それでも日本語で歌ってくれる人がいる。だから、母国語で歌うってこと自体がユニークだと思ってもらえる状況になってると思うんです。特にフランスみたいにアートにうるさい国だと、日本人が英語を使うよりも、そのまま日本語を使った方が受け止めてくれる。そういう風に、誰でもヒップホップが出来る時代になって、だからこそ生まれるトレンドだったり、新しいフロウがあると思うんですよね。そういった変化も含めてヒップホップが大好きだし、その変化に追いつくために新しい音にチャレンジしてきたのが、今の自分の結果かなと思いますね。
――そういった発言が、いわゆる「バイリンガル・スタイル」とカテゴライズされるISH-ONEさんから出るのは非常に興味深いですね。
ISH-ONE:ニューヨークでラップを学んだという部分もあるので、やはり英語のラップが基礎にありますね。だから、英語を使うのはスゴく自然なことだったし、別にアメリカ人になろうと思って英語を使ってるんじゃなくて、普段からそういうバイリンガル的な喋り方だったから、それがラップに繋がっていっただけなんですよね。それに、僕がデビューした当時は、まだ日本語のラップのリズム感だったりフロウが90年代を引きずってる部分があったので、それを進化させたり、壊したいっていう感覚はスゴく強かった。ヒップホップは究極的に言えば「ダサい」か「かっこいい」かしかないと思うし、若かったこともあって、その当時の日本語ラップのスタイルはダサいって攻撃的になってた部分もあると思いますね。だから英語に偏ってた時期もあったんですが、一方で日本語でしか表現できないニュアンスだったり、日本語ならでは言葉の深みもスゴくあるから、それはないがしろにしたくないなって。そう思ってた時期に、KOJOEやAKLOっていう、バイリンガルで面白いラップをする奴らがポンポン出てきたんで、そういうムーブメント的に捉えられた部分はあると思いますね。そして、そこで新しいレベルにシーンが開けていって、それが今の若い子たちに影響を与えられたんだとしたら、それは良かったと思います。
―― その時期に、仮想敵だと考えていたシーンや物事はありますか?
ISH-ONE:あえて言うなら、日本よりも海外ですね。ニューヨークでワイクリフ(・ジョン)も所属してたレーベルと契約してた時に、ワイクリフに「日本人よりも俺たちの方がヒップホップをわかってる」的なことを言われたんですよね。やっぱり、ニューヨークに住んで、ヒップホップコミュニティを見てると、そこには黒人至上主義みたいな部分が垣間見られたし、そこを打破したくて自分はヒップホップをやってたって部分がありますね。そこをぶっ飛ばさないと、俺たちはいつまでたっても借り物の文化で、他人のふんどしで相撲取ってると思われてしまう。その状況をどうにかして打破して、世界で認められたいっていう。だからそれがモチベーションではありましたね。

――今回のベスト盤の具体的な話を伺うと、選曲はどのように決めていかれましたか?
ISH-ONE:自分の中で自分のことを成長させてくれた、自分を前に進ませてくれた曲が中心になりましたね。あとはライブでの定番だったり、自分で歌って救われたような曲とか、そういう曲が中心になったと思います。
――曲順的には時系列順ではなく、1曲目は2012年リリースの「NEW MONEY」から始まっていますが、それはご自身にとっても印象深い曲だったと言うことですか。
ISH-ONE:やっぱり、自分を一番変えてくれた曲だと思いますね。
――収録されたアルバム『NEXT』、そして制作されたMVも含めて、この曲からISH-ONEのニューチャプターが始まった感触がリスナーとしてもあります。
ISH-ONE:スゴい良い曲できたという感触や、HilcrhymeのTOCくんがリミックスしてくれたりっていう広がり、ネットでのバズり、それから後に俺がプロデュースするS7ICKトルツメCHICKsと出会うきっかけになったりとか、いろんなものが動き出すイミングを作ってくれた曲が「NEW MONEY」なんですよね。だからそこから始めようかなと。時期的にも、ちょうどバイリンガルのラッパーみんなで集まって色々やろうぜって意気込んでた時期なんで、エナジーとしても自分たちが時代を作ろうっていう気持ちがすごく入ってます。あの時は俺らまだ全然認められてないし、スキルはあるのに全然アンダードッグで。だからこそ、そこで仲間と切磋琢磨できたし、何でも好きなことやってやろうぜって思ってた時期なんで、勢いはとにかくあったと思いますね。「NEW MONEY」の頃は本当に。今そこからどんどん成長してる仲間を見てると、成長もすごく嬉しいし、またどっかのタイミングでみんなで一緒にできたら面白いなとは思います。