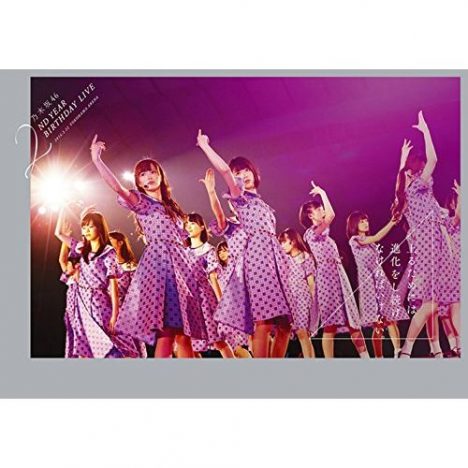香月孝史が舞台『すべての犬は天国へ行く』を評する
乃木坂46が舞台『すべての犬は天国へ行く』で手にした、グループとしての強靭な武器
演劇に対峙するグループとしての乃木坂46についてあらためてまとめるならば、その始まりは2012~2014年まで合計3度上演されてきた演劇公演『16人のプリンシパル』に見出せるだろう。『16人のプリンシパル』は公演の第一幕を公開オーディションにあて、それを受けての観客による投票で第二幕の演劇のキャスティングを決めるという、独特の形式をとった。日々の上演の動向をファンの「民意」にゆだねる企画性を持ちつつ、キャスト選出の当落線上にいる彼女たちをドキュメンタリー的に見守るこの公演は、乃木坂46のトレードマーク的なイベントになってきた。しかしまた、これを「演劇」の公演としてみるとき、そこには常に限界が伴ってもいた。形式上の「本編」である第二幕の演劇のキャストが公演時間の直前に決定されるという性格上、メンバーはすべての登場人物の台詞と段取りを覚える必要がある。専業の俳優であればいざ知らず、まだ俳優としての訓練を受ける以前の彼女たちにとって、その環境の下で演劇のクオリティを上げることはきわめて難しい。『16人のプリンシパル』は独特の魅力を放ちつつも、演劇と向き合うための場としては、演者であるメンバーにとっても演出する側にとっても、いびつさをはらむものだった。
今年に入り、乃木坂46は演劇面に関してある変化を見せた。デビュー以来毎年続けてきた『16人のプリンシパル』を実施せず、代わりに2つの演劇公演を企画したのだ。ひとつが6月に上演された『じょしらく』、そしてもうひとつが今回上演された『すべての犬は天国へ行く』(いずれも渋谷・AiiA 2.5 Theater Tokyo)である。これら2つはそれぞれに異なる性質を持ちながら、いずれも乃木坂46の演劇への志向を大きく推し進めるものになった。いってみれば前者は「アイドルが演劇をやること」を内側に向けて、後者は外側に向けて、ひとつの形を突き詰めようとした歩みといえるだろう。『じょしらく』は、「アイドルが落語家を演じる」というその企画趣旨そのものを入れ子構造のように劇中劇として再現し、アイドルが「演じる」ことの意義自体を作品の重要なテーマにしていた。「アイドル」というジャンルの可能性をポジティブに謳い、同時にこのジャンルへの批評ともなる投げかけがそこでは行なわれていた(参考:乃木坂46が舞台公演『じょしらく』で見せた、“アイドル演劇”の可能性とは?)。

それに対して今回の『すべての犬は天国へ行く』は、「アイドル」という枠組みを外したときに彼女たちが俳優として立ち回っていく基盤を作る、そのための足がかりだった。この公演のために乃木坂46が選んだのは、ケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERA)によるシリアス・コメディの傑作『すべての犬は天国へ行く』だが、この戯曲が描く救いのなさと笑いを成立させるのは、そう容易いことではない。実際、「KERA作品の上演」としてこの乃木坂46版をみるとき、まず気にかかるのが客演の役者陣に比べての、乃木坂46メンバーたちの未熟さであることは間違いない。しかし、今回の公演に関していえば、その未熟さの露呈自体が、ひとつのプロセスとして「正しい」ものだった。
西部劇をモチーフにしたこの劇に登場するのは女性のみ。町の男たちが殺し合いの果てに一人残らず死に絶えたのち、居酒屋とその二階にある売春宿で過ごす女性たちが描かれる。男たちが形作っていた町の論理の中では従属的な立場にいたはずの彼女たちは、男が誰一人いなくなったのちも、それを解放の契機と受け止めるのではなく、男がいた頃の習慣をなぞって生きている。男がいなければ成り立たなかったはずの売春宿でさえも、虚構の男を無理やりに維持させ、虚構の「外部」に出ていこうとする女性たちを次々と殺してまでも、その形骸を守ろうとする。そして、全員で維持している虚構がほころぶと同時に、彼女たちは無意味に最後の殺し合いを始める。