スクエニ、シーマン、バンナム、モリカトロン……ゲームAIを牽引してきた開発者4人が語る「20年の歴史と未来への展望」

『シーマン』を開発して気がついた日本語の持つ特殊性

次にプレゼンテーションをした斎藤氏は、広告代理店に勤務していた1994年にMac用のソフトウェア『タワー』をリリースしたことで、ゲーム業界でのキャリアをスタートさせた。『タワー』は高層ビルを次々と建設し、エレベーターを伸ばしていくゲームである。ビルが高層になっていくと、エレベーターに渋滞が起きる。朝はオフィスであれば上り、住宅であれば下りに、ランチタイムはその逆に向けて人が集中するという具合に、ビルの種類によってラッシュアワーは異なる。
従って、いかにエレベーターを効率的に上下させるかの優先順位を付けることがゲームにおいて重要になる。「一定時間も待たされると、人は怒りますから、そのビルから出ていって家賃収入が入ってこなくなります。そうすると、経営が立ち行かなくなるので、そうならないようにバランスを取りながらビルを育てていくゲームです。これが売れたことで、自分のキャリアがスタートすることになりました」と斎藤氏は語る。
1962年生まれの斎藤氏の世代にとって、人工知能は雪男やUFOのようなSF映画に出てくる用語の一つであった。『タワー』を制作するにあたっては、群れ理論を応用させているが、一人ひとりの人間の動きはシナリオベースではなく、「新たにやってきた住民がどこに行くのか」「お昼はどこに行くのか」などを、条件文で積み上げていったという。「例えば、1箇所のオフィスで6人が仕事をしているとします。そのうち、1人が部長さんで3人がベテラン、1人が新入社員という設定にすると、年齢によって食べに行きたいものが変わってきます。おじさんだったら蕎麦を食べに行きたい、若い人だったらハンバーグを食べる、という設定にすると、それぞれが色々な動きをするようになります」

斎藤氏はこの頃から、今で言うAIのような動きを作ることに関心を持っていた。それがさらに色濃く出ているタイトルが1999年にリリースされた『シーマン ~禁断のペット~』である。このゲームには、シーマンという日本語を話す人面魚が登場する。その開発プロセスの詳細は人工知能学会の学会誌に掲載されたインタビュー「シーマンは来たるべき会話型エージェントの福音となるか?:斎藤由多加インタビュー 」にあるが、あたかも生身の人間と会話をしているかのような巧妙に作り込まれたシナリオは、多くのプレイヤーの心を掴み社会現象にもなった。
ゲームの中でシーマンはユーザーを「お前」と呼ぶ。それは、日本語には英語のyouのように、上下関係を伴わない、あるいは目上の人に対しても失礼のない二人称が存在しないからである。「僕が例えば、森川さんに対して『あなたは?』と言うとすごく失礼になってしまうので、『森川さんは?』と名前で呼ばなければいけません。こういう言語が日本語なんです」現在のように発達した合成会話の技術がなかった当時は、ユーザー一人ひとりの名前をシーマンに発話させることは難しかったのである。
限られた予算と時間の中、シーマンの声優は斎藤氏自身が担当した。そこで発見した日本語のもう一つの特徴が、日本語は文法ではなくメロディに依存した言語であるということだ。「僕はメロディ言語と勝手につけているのですが、日本語は、SVOCのような欧米型の文法が破綻しているということが分かってきました。それを補っているのがメロディです。例えば、『お前、昨日、ヒロコとデートしたのか』というセリフがあったら、文字面は同じでも、『お前』『昨日』『ヒロコ』『デート』の、どの単語のメロディを上げるかで、意味が全然違ってきます」と斎藤氏は解説する。
つまり、今後『シーマン』のようなゲームを人工知能を実装させて作るなら、日本語という特殊な言語の処理を適切にする方法を作らない限り、自然な日本語を話すエージェントを作ることは難しいということだ。そのような問題意識から、斎藤氏はシーマン人工知能研究所を設立した。
さまざまな用途に活用されるゲームAI
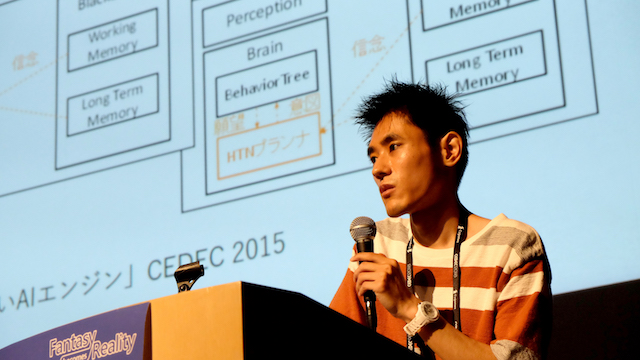
長谷氏は、2009年にバンダイナムコスタジオへ入社し、『エースコンバット アサルト・ホライゾン』(以下、『エースコンバット』)の開発チームに配属された。ゲームAIに出会ったのはその時が初めてだったという。『エースコンバット』のオンラインモードの対戦では、プレイヤーの代わりに入るボットがゲームワールドの戦況を解析して戦略を立てるAIや、プレイログを収集するAIを開発した。それ以降も『鉄拳タッグトーナメント2』と、『オール仮面ライダー ライダーレボリューション』、『タイムクライシス5』などの開発に携わってきた。

『タイムクライシス5』で作ったAIは、アメリカの哲学者マイケル・ブラットマンが提唱した「意図の理論」を応用したBDIアーキテクチャをもとにした。これはロボティクスなどに使用されているモデルで、ゲームでは制御しにくいであったが、ビヘイビア・ツリーや階層型タスクネットワークなどを使用して、ゲーム向きにBDIアーキテクチャを再構成した。
もう1つは、パラメータのチューニングである。『タイムクライシス5』は、ガンシューティングのゲームで、乗り物に乗った敵が登場する。乗り物は物理シミュレーションによってリアルに動くものの、アクセルやハンドルの加減をAIにパラメータとして渡して正確に制御する必要がある。その調整コストが高いため、AI自身が調整するように設計した。他のタイトルでは、プレイヤーの行動をもとに、プレイヤーの状態や感情をAIで推測し、それによって敵の出現数や出現頻度をコントロールした。
ゲームAIの灯火を未来につなぐために

ここまでゲームAIの歴史と現在の取り組みについて、各登壇者が発表したが、森川氏は、実用化されて20年経った今でも日本のゲームAIは風前の灯火だと警鐘を鳴らした。「誰かがフッと冷めたことを言ったら消えてしまいそうだという危機感を持っています。AIを使うことによる効果が圧倒的じゃないと、魅力を感じていただけませんし。AIを活用した他のサービスのように、正しいか正しくないかでは割り切れない、面白いか面白くないという感覚的なものが評価の基準になります。ですから、ともすると『AIは使ったけど、その効果はどうなんでしょうね?』ということになりかねません。ですから我々の努力によって、この灯火を消さないようにしたいと思っています」
また森川氏は、AIを開発する人材の不足についても言及した。「特にAIを使えるプランナーがすごく少ない。AIは工学的な技術ですが、プランナーは文科系の人が多いので、どうしても両方扱える人が少なくなってしまいます」
AIを扱える人材の不足は、ゲームAIの開発コストの高騰という課題を生む要因にもなっている。現在、長谷氏が所属するバンダイナムコスタジオでは、ゲームジャンルを問わずに利用でき、ゲームエンジンにも依存しない、汎用的なゲームAIエンジン「Munchkin」を開発している。「Munchkin」を作った背景には、これまではゲームタイトルごとに独自のゲームAIを開発する必要があったため、AIを実装することで、意図していたのとは逆に開発コストが高騰してしまうという課題があった。
その要因として、ドメインへの依存性が高いというAI全般が抱えてきた問題と人材不足があったという。「弊社で開発しているものは、ゲームタイトルごとに実装されているAIを、1つのAIエンジンを土台として使うことで、それぞれのゲームでの開発コストを削減することを目指しています。削減したコストを新しいAI技術の開発に回し、それをまたAIエンジンにフィードバック使うことによって、さまざまなタイトルで高度なAI技術を簡単に利用できる。このサイクルをうまく回していくことを目指して開発をしております」と長谷氏。
最後に斎藤氏は、ゲーム業界とIT業界の違いは、人を面白がらせる力にあると語った。「僕は、ゲーム業界が愛されている力の理由であり源泉であるのは、人を面白がらせることにあると思います。その面白がらせるノウハウは、残念ながらIT業界にはなく、ゲーム業界のみが持っている力です。ですから、本日のお話の中から、面白がらせようという気持ちと必ずひも付けて考えていただくと、世の中が面白くなると思います」と会場にエールを送り、セッションを締めくくった。
■高橋ミレイ
編集者。ギズモード・ジャパン編集部を経て、2016年10月からフリーランスに。デジタルカルチャーメディア『FUZE』創設メンバー。テクノロジー、サイエンス、ゲーム、現代アートなどの分野を横断的に取材・執筆する。関心領域は科学史、哲学、民俗学など。




















