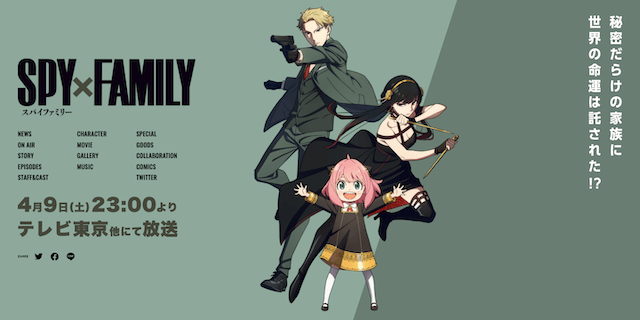『劇場版アイドリッシュセブン』から“推し”文化を考える ライブアニメが持つ演劇性

『劇場版アイナナ』から「推し」について改めて考える
ここ10年ほどの間、ポップカルチャーに関する批評や教育に携わっていると、いわゆる「推し(活)」について考えを巡らさないわけにはいかない。
もはや説明するまでもないだろうが、「推し」とは自分が応援したい対象を指す言葉である。また、そうした「推し」を応援することが「推す」という行為である。もともとはAKB48などのアイドルグループのファンがお気に入りのメンバーを呼ぶために使っていた「推しメン」(推しメンバー)という言葉に由来する。しかしその後、2010年代を通じて、より一般的な文脈にも広がっていった。その言葉の持つ意義は2020年代以降も変わらず、いまや現代人の感性や文化表現、行動様式を象徴するキーワードとして、さまざまな場面で注目を集めている。宇佐見りんの芥川賞受賞作『推し、燃ゆ』(2020年)や平尾アウリのマンガ『推しが武道館いってくれたら死ぬ』(2015年〜)、赤坂アカ原作、横槍メンゴ作画のマンガ『【推しの子】』(2020年〜)など、近年は「推し(活)」そのものをテーマにした作品やコンテンツも目立つ。あるいは、大学の授業で「推し」について話題にしたり解説をしたりしても、総じて学生たちの関心は高い。
こうした「推し(活)」の持つ特徴や本質については、私を含め、すでに多くの論者が論じている。そして翻って、「推し(活)」の対象となる作品そのものの細部にも、それらの要素が反映されていると感じることが多い。例えば、そのことは、現在劇場公開中のアニメーション映画『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』(2023年/以下、『劇場版アイナナ』)にも当てはまる。このコラムでは、『劇場版アイナナ』を題材にして、今日の「推し」文化の内実を改めて考えてみたい。さらに、後述するように、『劇場版アイナナ』は、いわば「ライブイベント」の体裁を借りた「映画」作品なわけだが、本作を通じて、主にメディア文化論の視点から、現代における「映画」の変容の意味についても検討してみよう。
ライブアニメとしての『劇場版アイナナ』
まず、『劇場版アイナナ』の元となる『アイドリッシュセブン』(『アイナナ』)の概要について簡潔に確認しておこう。
『アイナナ』は、2015年からバンダイナムコオンラインが提供しているスマートフォン向けアプリゲームだ。父の経営するアイドル事務所「小鳥遊芸能事務所」で働くことになった主人公(ゲームではプレイヤーに相当する)が、7人組男性アイドルグループ「IDOLiSH7」のマネージャーを務めることになり、彼らをトップアイドルへと育成することになる……という、昨今のアイドルゲームやアイドルアニメの定型を踏襲したストーリーで、映画でも脚本を手掛けている都志見文太がシナリオを担当している。これも同種の人気アイドルコンテンツの御多分に洩れず、メディアミックス展開も多く、これまでにも作中の音楽CDの発売やライブイベントの開催をはじめ、小説化、マンガ化、リアル脱出ゲーム化がなされ、2018年から2023年までには3期にわたってTVアニメ化もされている。
ところが、錦織博と山本健介の共同監督による今回の劇場版は、通常の意味での映画化とは趣がだいぶ異なっている。というのも、『劇場版アイナナ』ではいわゆる物語は描かれず、(2022年末に公開されたメインストーリー第6部の展開を受けた)全編が、作中に登場する、それぞれ事務所の異なる4組のアイドルグループ、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:vale、ŹOOĻによるライブコンサートの形式を採っているからだ。各キャラクターたちが3DCGでモデリングされ、ーーモーションキャプチャを利用しているのだろうーー細かい仕種まで表現され、スタイリッシュにダンスする。こうした表現の全面化は、本作のアニメーション制作元が、TVアニメ版の制作元であるTROYCAから、『宝石の国』(2017年)などCGアニメーションのクオリティに定評のあるオレンジに変更されたことにも関係しているのかもしれない。
こうした趣向は、宣伝側が本作を「映画」ではなく、あくまでも「ライブ」としてプロモーションしていることからも如実に窺われる。そして、これも主に2010年代以降の映画文化の新たな慣習といってよい、いわゆる「応援上映」を想定した趣向であることもいうまでもない(応援上映的なスタイルは正確には新しいものではないのだが、ここではあえて議論を単純化して表現している)。私は、決して『アイナナ』の熱心なファンというわけではないが、それでも冒頭から終幕まで、キャラクターたちのパフォーマンスとそれをリアルライブのように表現する演出に惹き込まれ、終始、圧倒されてしまった。
一般的に想定される物語映画(物語アニメ?)ではなく、ーー応援上映を前提としたーーキャラクター(俳優)による楽曲の歌唱と身体的なパフォーマンスに特化し、ほぼ全編がライブコンサートの体裁で展開するこのようなライブアニメは、アイドルアニメという一般層にはさほどポピュラーではないジャンルに特化しても、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』(2019年)などをはじめ、すでにいくつも先例があり、いまやとりたてて珍しいものではない。ましてや、これらライブアニメ的な想像力は細田守監督『竜とそばかすの姫』(2021年)や吉浦康裕監督『アイの歌声を聴かせて』(2021年)、谷口悟朗監督『ONE PIECE FILM RED』(2022年)、湯浅政明監督『犬王』(2022年)、そして立川譲監督『BLUE GIANT』(2023年)など、より大衆的な支持を獲得し、なおかつ通常の物語を備えたここ最近の名だたるアニメ監督たちによる劇場アニメにも明らかに浸透している。あまつさえ、同じようなセンスは、『ボヘミアン・ラプソディ』(2018年)以降の海外の実写映画にも見られるだろう。