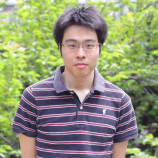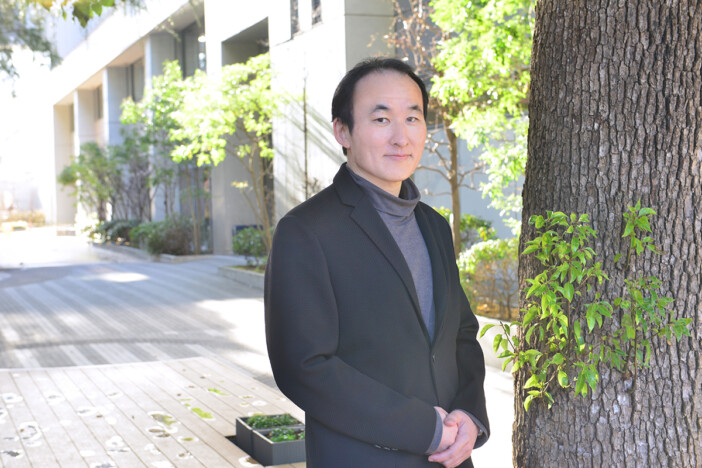ソ連の歴代指導者はなぜ「悪党」だったのか 近現代ロシア史研究者、池田嘉郎に聞く権力構造

『悪党たちのソ連帝国』(新潮選書)は、「悪党」という言葉から、ソ連の約70年の歴史を丹念にたどっていく一冊だ。本書で紹介される「悪党」は、レーニン、スターリン、フルシチョフ、ブレジネフ、アンドロポフ、ゴルバチョフ。つまり、ソ連に「指導者」として君臨してきた6人だ。彼らはなぜ「悪党」と定義されたのか。そして彼らの生涯を通して見えてくる、ソ連の歴史とはどのようなものか。本書の著者であり、近現代のロシア史を専門とする東京大学大学院人文社会系研究科教授・池田嘉郎氏にお話をうかがった。(若林良)
ソ連の指導者の生涯を見つめる
――本書で語られるソ連の歴代指導者たちは、なぜ「悪党」と定義されたのでしょうか。
池田:本書は新潮選書の『悪党たちの○○帝国』というシリーズの3冊目です。最初の本は君塚直隆さんによる『悪党たちの大英帝国』ですが、君塚さんは「悪党」を「アウトサイダー」と定義していました。私も当初はそうした定義のもとで書くのがいいかと思い、ラスプーチンなどを取り上げようと考えたのですが、途中で意向が変わりました。私は歴史に名を残す「悪党」には、単に悪いことをしただけではなく、一般社会の常識とは離れた、新しい価値観を提示した側面もあると思ったんですね。たとえば、レーニンやスターリンは、私的所有や市場経済はよくない、個人のエゴイズムは克服されねばならないという自分たちの価値観に沿って、新しい社会をつくりあげた人物と言えますし、また彼らを含むソ連の歴代のいずれの指導者も、同様にして、現在の私たちの常識とはかなり異なる価値観に基づいて社会を管理していました。そこから、ソ連の指導者たちを「悪党」と定義し、彼らの生涯を見直してみようと思いました。
付け加えますと、本書における「悪党」には、「悪」という意味そのものは込めておりません。もちろん、ソ連の指導者たちの政治には、戦争や飢饉、弾圧などによって多くの人が命を落としたような側面はありますが、ただそれらのスケールはあまりにも巨大なので、一般的な基準で善悪を測ろうとは考えていませんでした。むしろ、彼らが行使した権力や、それにともなって生まれた犠牲の巨大さを、「悪党」という言葉に託したかったんです。
――冒頭では、ソ連の指導者たちが念頭に置いていたこととして、「ソ連という一つの共同体を守り、発展させねばならないということ」があったと語られています。こうした思いの内実についておうかがいできますか。
池田:私はソ連を、「家族共同体」であったと思っています。西欧諸国の場合は、まず一人ひとりの国民が自立した存在であり、その上に社会や国家があるという構図があります。一方でソ連には(ソ連以前/以後のロシアにも通底する部分はありますが)、一人ひとりの国民が起点にあるという考え方は根付いておらず、まず大きな共同体があり、その中に国民があったのです。つまり、主体となるのは国民ではなく、あくまでも共同体でした。
ただの共同体ではなく、「家族共同体」であることについても説明が必要ですね。ここでいう「家族」は、父親の権力が強い、良く言えば伝統的な、悪く言えば旧弊な価値観に基づいたものだと考えてください。父親は子どもが自分に逆らったり、自分から離れようとしたりすると暴力でそれを抑えようとしますが、一方で親としての責任や優しさもあるので、子どもである国民を守ろうとする姿勢も見せる。そうした二つの面が、ソ連の中には息づいていました。
ソ連は一般的に、これまでになかった先進的な社会をつくる試みであったとみなされる部分はあります。とくに研究者の間では、ソ連の社会主義は資本主義よりも新しいものだと語られることも多いです。しかし、私の考えでは、ソ連社会主義の核はあくまでも「家族」という伝統に根ざしているんですね。その意味では、ソ連はモダン(近代)ではなく、プレモダン(前近代)の側面が強いと思います。
――ブレジネフ(ソ連の1964~82年における最高指導者)の章で、20世紀初頭のロシアにおいては、ロシア人かウクライナ人かといった区別はさほど厳格ではなかったと語られていますが、これは少し驚きでした。日本も含め、少なくない国では「正統の国民か、そうでないか」という考えが根強く存在すると思うのですが、100年以上前のロシアではそうした意識が希薄だったのですね。
池田:いわゆる「ロシア人意識」の発達が遅かったことが、ロシアの大きな特徴として指摘できると思います。たとえばフランスやドイツ、また日本では、おおむね19世紀の半ばから民族的なマジョリティが「自分たちこそがこの国の国民なんだ」という意識を持ち、身分の差を越えて団結し国民国家としての国を形づくっていったとは言えるのですが、ロシアの場合は、「同じ民族で団結する」という発想は長い間根付くことはありませんでした。同じ民族でも、貴族と農民はまったく離れた存在で、日常の暮らしにおいて多くの接点を持つことはなかったんですね。
それはロシアの皇帝が意図していたことでもあります。ロシア人たちが身分の差を越えて団結すると、皇帝の地位も危うくなるので、同じ民族同士の間でも分離のある状態が長年続いていました。そうした構造がようやく変化したのが1930年代で、スターリンは広いソ連の中で、多数派であるロシア人に「ソ連の中心である」という意識を持ってもらうことで、支配の円滑化を試みたのです。実際にそれは功を奏し、国力の強化につながったと言えます。ただ、そうは言っても、ロシア人やウクライナ人といった明確な民族意識の確立は、いまお話ししたようにそんなに古い話ではありませんでしたので、いまだに境界線がはっきりしない部分もあります。ロシア人とウクライナ人にしても、言葉も比較的似ていますし、同じ地域に混住していることもありますから、良くも悪くも、「民族の壁」がそこまで大きくはないということが、ロシア史の大きな特色であると思います。
――6人の「悪党」の中で、池田さんがもっとも思い入れのある人物は誰でしょうか。
池田:なんといっても、ブレジネフですね。日本では彼の研究はほぼ存在せず、また彼を知っている人にとっても「何もしなかった人」というイメージに留まっていると思います。また、彼の死後数年でゴルバチョフが最高指導者の地位につき、ソ連が大きく変動していったことから、余計にブレジネフのマイナスイメージが強まっているかもしれません。
しかし、ブレジネフの主眼は改革ではなく、安定にありました。彼が出てくる以前は、スターリンによる粛清や戦争などでソ連の人々が疲弊していたこともあり、恐らくは急激な変化を、市井の人々は求めていませんでした。ブレジネフはそうしたソ連全体の空気を鋭敏に感じ取り、安定を追求していったのです。その努力があって、ソ連は世界が激変する中でも一定の平和を維持できたとは言えます。私も本書の中で「ブレジネフの18年間はソ連史上でもっとも平穏な18年間であった」と評しています。
付け加えますと、ブレジネフ自身が闘争のようなものと無縁であったとは言えません。権力を得る中では、彼もライバルたちを蹴落としてきましたし、政治的な欲望も強かったでしょう。ただ彼は、ライバルたちを「蹴落とす」といっても、処刑や追放といった強硬的な手段を使ったわけではありません。一定の名誉は与え、かつ経済的にも優遇はしつつも、発言権は与えないといった形で、彼の闘争は、あくまでも調和を守ったうえでのものだったんですね。ブレジネフがそうした品性を意識しなければ、彼の時代にもすさまじい権力闘争や混乱があったと思いますし、それを避けたという点でも、ブレジネフは評価に値すると思います。
ソ連から現代ロシアへ
――ソ連の74年の変遷の中で大きな転換点としては、スターリンの大粛清やペレストロイカがぱっと頭に浮かびますが、池田さんが考える、ソ連の大きな転換点は何でしょうか。
池田:一番大きいのは、スターリンが第一次五か年計画(1928~32)で、ソ連全体の工業化・集団農業化を推し進めたことですね。この政策によって、ソ連は旧来的な農業国家から、近代的な工業国家へと大きな変貌を遂げました。これはソ連が発展したというだけではなく、ソ連への諸外国からのイメージが変わったこともまた特筆に値します。「社会主義」のイメージはそれまではよく分からない実験のようなものでしかなかったでしょうが、ソ連が短期間で急速な近代化を成し遂げたことで、資本主義や自由主義とは別な次元で、文明の発展がありえるのだという認識が生まれたんです。これは世界の認識が大きく変わった瞬間でした。
この変化に比べると、ペレストロイカは、その出発点においては、それほど大きな転換ではありませんでした。ゴルバチョフが積極的に推し進めた政治改革だと一般には思われていますが、行政機構や経済管理の機能を改善する必要は、第二次世界大戦後から歴代の指導者が意識し、ある程度は改革に手をつけてもきました。ペレストロイカそのものというよりは、ゴルバチョフによるその進め方が拙速であったことが、ソ連史にとって大きな意味をもったといえます。また、彼のやり方には強引な点があり、それがソ連崩壊の引き金ともなりました。そうした点を考慮すると、やはりペレストロイカよりはスターリンの政策のほうが評価に値するでしょう。
――6人の「悪党」の中で一般に最も知名度があり、同時にもっとも「悪党」という印象を覚えるのはスターリンかなと思いますが、ソ連だからこそ生まれてきた彼のパーソナリティとしては、どのようなものがあると思いますか。
池田:スターリンは、実はロシアの中心から出てきた人物ではなく、出身はグルジア(現ジョージア)です。幼少期は僧侶になることを目指していたのですが、ある時期から政権の中枢に入ることを志向するようになり、ロシア語を学び、グルジア語で書くことをやめました。いわば辺境から出てきた努力家ではありますので、恵まれた立場に胡坐をかいているような人間には厳しかったですし、同時にソ連のどの地域であっても、「ソ連」の内部にいる人間に対しては、みな一定の権利を持つべきだという考えは持っていたと思います。それゆえに、スターリンの姿勢はソ連の多民族性から養われたものだとは言えるでしょう。
――スターリンは、同時代のヒトラーやムッソリーニ、毛沢東などと重ねて語られることもあり、「独裁者」という側面も強いかと思うのですが、他国の「独裁者」との違いはありますか。
池田:人間関係を重視するか否か、ということが大きいと思います。ソ連におけるトップの機関は「ソ連共産党政治局」ですが、ソ連のリーダーは独断で意志決定をするわけではなく、政治局のメンバーたちと協働し、そのもとで政策を形にしていっていたんですね。スターリンは邸宅で、政治局のメンバーや取り巻きたちと夜中に酒を交えながら政治的決定を行うことも多かったので、集団的な決定を重んじていたとは言えます。ヒトラーなどは恐らくはそうではなく、ほぼ単独で物事を決めている。ソ連のリーダーのほうが、少なくとも形式面では集団的な意思決定を志向しており、これは先ほど申し上げた「家族」という像ともリンクすると思います。
――そうした姿勢は、現在のロシアの指導者であるプーチンにも通底するものでしょうか。
池田:プーチンは存命の人物なので、その評価を断定することは難しいですが、彼の根底にあるのは、ただの権力欲だけではないでしょう。ソ連崩壊後、基盤が弱くなったロシアを立て直すという気持ちや、国内、ひいては国外のロシア人の助けになりたいという気持ちはあるでしょうし、ソ連のリーダーたちにあった同胞愛や祖国愛は、彼の中にも確かに根付いていると思います。また、彼は「チーム」(コマンダ)で仕事をすることが大事であり、自分を助けてくれるチームのメンバーを尊重しなければならないとも強調しています。公式な肩書よりも仲間うちの人間関係を重んじるという点で、ここにも「家族共同体」を志向するソ連の政治文化と似た傾向を見出すことができるでしょう。
その一方で、プーチンに私利私欲の感情がないとも言えないでしょう。ソ連の崩壊後は、資本主義の悪い面といいますか、個人の競争が幅を利かせるようになったので、社会主義の時代とは異なり、指導者が私腹を肥やすことはよりやりやすくなっています。実際、プーチンも大きな別荘などを持っていたりしますし、そうした個人の欲望を「公共」よりも優先する意識は、ロシア全体に広がっていると感じています。そもそもロシアでは、歴史的に「公共」概念の発達が弱く、帝政期には皇帝と貴族身分の私的な利益が社会全体の利益と同一視されていたと言えないこともありません。ソ連時代には皇帝がいなくなったかわりに、共産党と国家が「公共」空間を独占して、自分たちのイデオロギーによって住民を支配しました。これに対して現代ロシアではプーチンを中心とするエリートたちの仲間内でのつながりが、行政機構であれ自治体の仕事であれ文化活動であれ、公務を自分たちの私腹を肥やすために独占しているように見えます。
――現在、日本ではロシアは「危険な国」というイメージが強いと思います。渡航の難しさもある中、ロシアという国をより解像度を高めて理解するためには、何が必要だと思われますか。
池田:前提として、日本人がロシアに渡航することは可能です。現在、ロシアの多くの地域は外務省から渡航中止勧告が出ていますが(2025年12月時点)、あくまでも勧告なので、行こうと思えば行くことはできるんです。実際、研究者でもロシアの学会に出席している方はいますし、また旅行者も少なくはありません。今後、若手研究者をロシアに派遣する展望も出てきますから、学生・院生の皆さんには、チャンスがあれば現地を自分の目で見てきてほしいと願っています。
質問の答えとしては、ロシアにおける小さな声に、耳を傾けることではないかと思います。直接ロシアには足を運ばずとも、映画や小説やノンフィクションなどを通じて、ロシアにおける市井の人々の姿を垣間見ることはできます。エレーナ・コスチュチェンコ『私の愛するロシア――プーチン政権から忘れ去られた人びと』(高柳聡子訳、2025年、エトセトラブックス)のような、いいルポルタージュも出ています。私自身にとっては、今日も細々と続いているFacebook上での交流が、ロシア国内の気分を伝えてくれるかけがえのない機会となっています。
私自身の経験を振り返りますと、以前は世論調査の数字を参考にして、ロシアの大半の人々はプーチンのこの戦争を、少なくとも消極的には支持していると考えてきました。ですが、そのように言うたびに国内外のロシアの人々から、本当は世論調査よりもずっと多くの人々が、この戦争に反対しているのだと批判されました。先日、浅草で行なわれた展示会「ロシアの抵抗の顔」(国内外でプーチン政権に反対するロシア市民の紹介がなされていました)でも、そこにいた若いロシア人たちとやりとりしたのですが、統制の厳しい体制下において、戦争に公然と反対する人々がいることの重みは、表面的な数字からは測れないと言われました。
彼らの周囲にいる人々は、一般的なロシア人よりも政権に批判的な人が多いと考えることもできます。ですが、外から見えるよりも多くのロシア市民が戦争に批判的なのだと何度も言われるなかで、私自身、世論調査の数字とは別に、こうした実感のこもった言葉を重視しなければならないと考えるようになりました。現在のロシアに対して「危険」や「怖い」というイメージがあるのは当然のことではありますが、プーチンとその取り巻きだけがロシアというわけではありません。また、日本との交流が古くからある身近な隣国であることも否定できません。まずは小さな声に耳を傾けることを、意識していただければと思います。