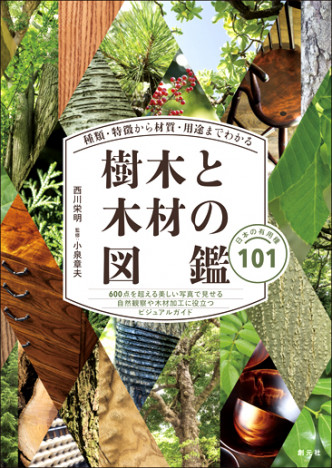10-FEET TAKUMA チバユウスケへの思い「ずっと心を支える音楽」 遺作『EVE OF DESTRUCTION』に触れて

2023年11月26日、THEE MICHELLE GUN ELEPHANT(ミッシェル・ガン・エレファント)やThe Birthdayとして活躍したチバユウスケさんがこの世を去った。享年55歳。世界中で大ヒットを記録した映画『THE FIRST SLAM DUNK』のオープニング主題歌「LOVE ROCKETS」を担当したことでも話題を振りまいていただけに、往年のファンはもちろん、冒頭にベースラインから始まり、ギターリフやチバユウスケさんの歌声が象徴的に使われる映画を観た人からのショックも大きかった。
そんなチバユウスケさんの死去へのロスが続いていた昨年2023年の紅白歌合戦。同じく映画『THE FIRST SLAM DUNK』でエンディング主題歌『第ゼロ感』を担当し演奏したのが10-FEET(テンフィート)である。その紅白歌合戦において『第ゼロ感』パフォーマンス中に「チバユウスケ」とシャウトした姿で多くの人々に強烈なインパクトと感動を与えたことも記憶に新しい、ボーカル/ギターのTAKUMA氏にインタビューを敢行。チバユウスケ氏への出合いからエピソード、それにチバ氏のレコード・コレクションと“音楽愛”を凝縮した話題の書籍『EVE OF DESTRUCTION』(ソウ・スウィート・パブリッシング )の魅力など、しっかりと質問に対して一つひとつの言葉を考え、時に当時を思い出し熟考し、自分の“言葉”として紡ぎ出しながらチバユウスケさんへの思いを真摯に語っていただいた。(編集部)
僕の中にあるネガティブな部分と共鳴した

――まず、チバさんの音楽との出会いを教えてください。
TAKUMA:僕はTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTは結構後追いやったんですけど、最初にじっくり聴いたのは「GT400」だったと思います。確かテレビでミッシェルが演奏してたのを観たのが最初の出会いで。それから「エレクトリック・サーカス」とか「ブギー」とか、メジャーどころの曲をよく聴いていました。
――同じボーカリストであり作詞家でもあるTAKUMAさんから見て、どんなところに惹かれたんでしょう?
TAKUMA:今思えば、チバさんの音楽が僕の中のネガティブな部分にすごく共鳴したんですよね。ロックとかパンクって、応援ソングじゃないですけど、「元気出そうぜ、頑張ろうぜ!」みたいな、わかりやすいものが多いなと思っていたんですけど、チバさんの音楽は、なんかこう……辛いことあるけど頑張ろうぜ、じゃなくて、「辛いことあるんだよな〜」って言ってるだけの感じがして。だから素直に聴けるというか。
人の性格はいろいろあって、辛い状態にもいろいろある中で、真正面からの前向きな言葉はときに痛かったり、幼稚臭く聞こえたり、お前に何がわかんねん!って思ってしまうところがたまにあるんですけど、チバさんは「いやあ、よくわかんないけど、どうせ最悪なんでしょ」「まあ、俺もなんだけど、しょうがないよね。飲む?」みたいに言ってくれてる感じがして。近しいけど、ベタベタしてないような距離感を曲からすごく感じたんですよね。
――「GT400」にも「ブギー」にも、まさにそんな感覚があると思います。今言っていただいたような共鳴は最初からあったんでしょうか。
TAKUMA:…………いや、最初に触れた頃は、あまりわからなかったんですよね。それが「GT400」とかを聴きながら、「こういうことをこういう風に歌う!?」ってだんだんわかっていったのと同時に、「あ、チバさんって、こういう人やったんや」っていうのが、なんとなく感じ取れてきて。僕も歌詞や曲を書いたりしてますけど、チバさんの音楽に対しては「違うバンドの人やし」とか「流派が違う人やし」とか、そういうことを全然感じずに聴いてましたね。
――なるほど。
TAKUMA:それも、表現がかっこよかったっていうのが一番大きかったんですけど。自分にとってかっこいいものって、よくわからんものが多かったんです。(ミッシェルの曲には)めちゃくちゃ熱量を感じるし、強い想いもそこにありそうやけど、ある意味、深い意味はないっていうのが、自分にめっちゃ深く刺さってました。別にスカスカしてるわけではなくて、むしろ鉛の塊のようなロックな意志が存在してそうやけど、そういうものをぶつけるというよりは、ただその場で激しく渦巻いて燃え上がってる炎みたいな感じ……だからクールかって言われるとそうじゃないんやけど、熱いっすよねっていう感じでもない。それが自分に刺さったと思います。
――当時のTAKUMAさんは、何に苦悩を感じ、チバさんの音楽によってどう感情が動いたのでしょう?
TAKUMA:…………なんやろね。当時は今より、もっともっと若くて無知で未熟だったなと思うんですけど、精神的なストレスとか憤りを抱えながら、頑張って歌詞を考えて書いたりしてたから、「自分はそれなりに入り組んだことや深いことを考えられている人間や」と思い込んでいて。「ある程度のことは経験できたし、音楽のこともだいぶわかってきたんちゃうかな」っていう、やり尽くした感があったんですよ。自分が求める表現力のさらに先を行っている人は果たしているんやろうか……って。そんなとき、チバさんがバンッと現れた。「まだまだすごい人がいるねんな……自分なんかまだまだ小学校2年生くらいの感じやったわ」と思うくらいの衝撃でしたね。相談できるのかって言ったらできるわけもなく、きっと相談してもあんまり答えてくれなさそうやけど(笑)、チバさんの音楽から「自分次第でこの先まだまだ行ける」みたいな、考え続ける意義を得ることはできたかなと思ってます。
チバさんの音楽は「心の支え」のように聴いていた

――それは10-FEETで言うと、どのくらいの時期に一番強く感じていましたか?
TAKUMA:『VANDALIZE』を作ったあたり、2007~2008年くらいですね。その前からミッシェルは聴いてたんですけど、当時は心の支えのように聴いていました。
――2007~2008年というと、10-FEETの主宰フェス『京都大作戦』が始まり、『VANDALIZE』でミクスチャーバンドとしてのオリジナリティをもう一段階追求している時期だったと思います。直接的ではないにせよ、何か参考になるものがあったのでしょうか。
TAKUMA:一通り(音楽を)掘り終えたと思ってたら、まだまだ掘り終えてないことに気づいたので、それが一番大きかったかな。単純にかっこいい音楽を聴いて影響されて、音楽が作りたくなりました。ドキドキ、ワクワクするような向上心が一度燃料切れになりそうなときやったから、すごくいいときにミッシェルを聴けてたなと思いますね。あと参考ってことで言うと、ずっと聴いていたミッシェルが、今さらながら「すごいな」と思うことがあって。
――例えば?
TAKUMA:…………言葉の使い方ですね。チバさんの書くすべての曲の「語呂」がいいんですよ。けど、とにかく語呂に合う言葉だけを選んでるのかって言ったらそうではなくて、確固たるチバさんフィルターみたいなものを通したこだわりと好みが、曲のポイントになっているなと感じました。例えば 「ゲット・アップ・ルーシー」やったら、「タッ・タッ・タラ」という音に合っててある程度かっこいい言葉なら何でもいいわけじゃなくて、もうそこは絶対「ゲット・アップ・ルーシー」っていう言葉じゃないといけないんですよ。本人に聞いてないからわからないですけど、いろんなタイプの聴き手を想定しているかのごとく、ミッシェルの曲は誰にとってもかっこよく聴こえる部分があったりする。そういう言葉を書く感覚を、持ってはる人やったと思いますね。
――『Chicken Zombies』リリース当時のインタビューで、インタビュアーから「チバさんの歌詞は、大体8割がリフみたいに尖っていて、残り2割はそうではないもので書かれている」といった旨を指摘されて、チバさんが「なるほどねえ!」と納得している場面があって。「ゲット・アップ・ルーシー」とか、「スモーキン・ビリー」の〈“愛という憎悪”〉とかもリズミカルでかっこいいし、その上でチバさんにしか書けない言葉になっている。
TAKUMA:「なるほどねえ!」って言ってる姿、想像つくなあ(笑)。ほんまにそういう言葉を書いてますよね。