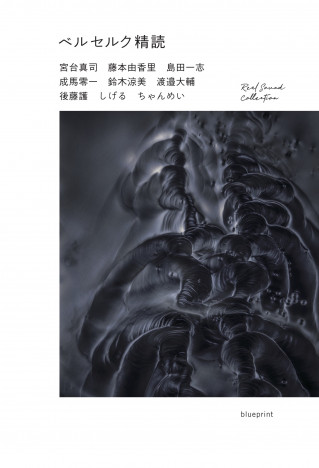「SNS的な言葉」の専制に対峙する小説ーー九段理江『東京都同情塔』論
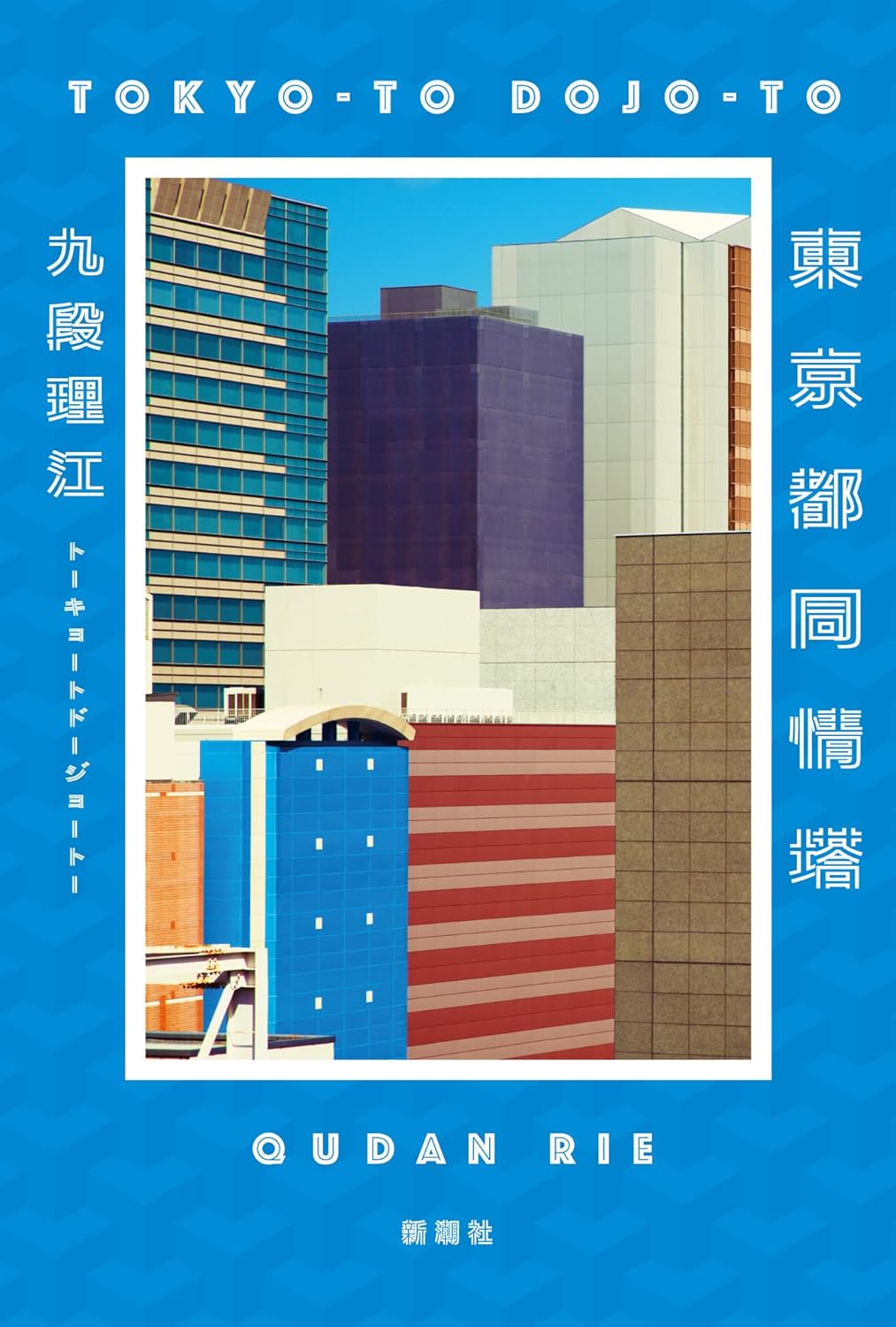
生成AI時代のディストピア小説
『東京都同情塔』(新潮社)は、2023年11月に発表され、今年1月に第170回芥川賞を受賞して話題を集める九段理江の6作目の小説である。
物語の舞台は2020年代の近未来の――そして、ザハ・ハディド設計の国立競技場が竣工し、コロナ禍の2020年にオリンピックが開催された可能世界の東京。小説の語り手はふたり、「私」こと建築家の牧名沙羅と、「僕」こと彼女より歳下の青年・拓人。沙羅は目下、気鋭の建築家として、都心の新宿御苑内に建設が計画されている超高層タワー「シンパシータワートーキョー」の設計を手掛けている。
作中の日本では、現実の私たちの世界のように、社会的寛容論やマイノリティに対するポリティカル・コレクトネスが過度に浸透している。シンパシータワートーキョーもまた、社会学者で幸福学者のマサキ・セトなる人物の提唱したポリシーに基づいて、犯罪者や非行者を「ホモ・ミゼラビリス」(同情されるべき人々)なる呼称で呼び替え、「誰一人取り残さないソーシャル・インクルージョンとウェルビーイング」の実現を目指し、棟内では彼らが――むしろ俗世よりも――快適な生活を送れるように設計された、いわば新時代の「刑務所」なのだ。昨今のカタカナ表記の名称の時流に乗り、有識者たちによって決められた「シンパシータワートーキョー」という名前に違和感と覚える沙羅は、恋人の拓人が考案した「東京都同情塔」というネーミングを絶賛する……。
社会的包摂とポリコレと言葉狩りが隅々まで行き渡り、「多様」で「寛容」で「適切」な、しかし真綿で首を絞められるような息苦しさを誰もが感じて生きるこの21世紀の現代特有のモティーフをあちこちに散りばめた巧緻なディストピア小説であり、作中に登場する生成AIの記述を、実際にChat GPTを活用して執筆したことで、マスメディアからの脚光を浴びていることでもすでに知られている話題作だ。
ポストヒューマン小説としての九段作品
ここ10数年続くいわゆる第3次ブームとも呼ばれるAI開発の潮流の一つの到達点として登場したChat GPTやStable Diffusionなどの生成AIは、2022年から2023年にかけて社会の各方面に大きなインパクトをもたらした。『東京都同情塔』もまた、小説創作におけるその試みの一つとして、日本文学で指標的な意味を持ったことは紛れもない。ただ、こうした奇抜な試みが、単に表層的な時流に乗っただけのものではなく、本作の文学表現や近年の社会的文脈、そして九段自身の創作上の履歴とも密接に関連するものであることは、この小説を読み解く上でまず押さえておく必要がある。
というのも、九段が本作執筆にあたって実践した、この人間=作家と人間でないモノ=AIとのコラボレーション(協働/競合的執筆)というあり方は、本作の世界観や叙述のレベルでも形式的に反復されているためである。作中では、ヒトとモノ、有機物(身体)と無機物(建築)、言葉と事物……といった本来は相互に対立し合うとみなされる二つの要素群が、あるときは同一のものと語られたり、境目なく混ざり合ったり、親密に接触し合う姿や認識がいたるところに描かれる。
最も典型的なのは、沙羅が、自分も含めた人間存在を建築物とほとんど同一視する認識が全編を通して披瀝される点だろう。沙羅は、「社会通念を大きく逸脱する趣味嗜好を誰かに開陳したことはないが、私は陸上生物であるところのヒトを「思考する建築」、「自律走行式の塔」と認識して」(26頁)おり、またホテルの窓から国立競技場のスタジアムの屋根を眺めている時には、「ほとんど自分と屋根とが一体化しているといってもいいほど」(28頁)に建築物に没入してしまう。
また、その彼女の認識には、自身と建築物の一体化のみならず、無機物であるはずの建築を生きもののような有機物として眺めるという、ある種の倒錯した感性も関わっている。例えば、沙羅の目には、ハディドが設計した国立競技場は何かヒトならぬ大きな生きものに見られており、しかもそこには性差まで付与される。
「今にも動き出すのではないかという生命感を湛えた構造物は、周囲に林立するビル群や道路を走る車のライトを養分にして独自進化を遂げた、巨大生物のように見える。東京が生み出した世にも美しい生きもの。その生きものが、開閉式の半透明の屋根をひれのように自在に動かし街を回遊する、SF映画さながらの映像が鮮やかに脳内に映し出される。彼女には意志があり、彼女の意志がこの雑多な都市を導いていくのだ」(33頁)。
この引用箇所にも表れているように、以上のようなヒトと建築物の一元論には、つねにセクシュアルなニュアンスがつきまとうのも特徴だ。例えば、「有機的なダイナミズム」を備えていたというスタジアムの当初のザハ案を評した「初老の建築家の男」は、沙羅に向かって、「僕の心がねじくれていることは認めるよ。それにしても修正案は、女性のアレにしか見えなかった。どこからどう見てもグロテスクなスタジアムだった」(31頁)と「不適切」な感想を零す。
だが、沙羅にしたところで、「僕」=拓人に対して、「君みたいな綺麗な建築を見つけるとね、人間はここまで美しくなれるんだって、希望を持つことができる、この弱い私は。[…]メンテナンスに相応の費用を要するのは、建築も人間も同じでしょ」と、やはり彼という人間を建築と同一視しつつ、「さっき、ホテルの部屋で、君が私に触ってくれて嬉しかった。もっと君が私に近づいて、もし私の中に入ってくるようなことがあれば、きっと天にも昇る気持ちになるでしょうね」(77頁)と、そこに先ほどの男と同じような、セクシュアルな感慨を付け加えるのだ。そして最終的に、彼女は、「すでに私はもう、何かの外部にも内部にもいない。私自身が外部と内部を形成する建築であり、現実の人生なり感情なりを個々に抱えた人間たちが、私に出入りする」(140頁)のだという思いを口にするのである。
『東京都同情塔』は、作家がChat GPTと協働しながら作品を創作をするように、まさに「何かの外部にも内部にも」ならず、さまざまな他者たちが「私に出入り」し、相互に包摂し合い、一体になりながらヒトを超えた何かに生成変化していく、「ポストヒューマン」な手触りをたたえた小説になっている。
例えば、沙羅は作中で、あるアメリカ人男性ジャーナリストから「Ms. Machina?」(126頁)と声をかけられる。この時に綴られる文字は、いみじくも「機械machina」と同じであり、彼女自身がポストヒューマンなオブジェクトと等価な存在であることが小説で暗示されている。本作が取り上げるAIから気候変動まで、ポストヒューマニティが時代の思潮となってすでに久しいが、『東京都同情塔』の描く世界もまた、それに近い思想を共有していると言える。
ちなみに、こうしたリアリティは、他の九段作品にも共通して認められるテーマでもある。ヒトと馬の壮大な交流の歴史を描いた野間文芸新人賞受賞作「しをかくうま」(2023)はそれに最も該当する先行作だと言える。ここから「ポストヒューマン文学」としての九段作品について論じることも可能だろう(さらにいえば、九段は、川上弘美や笙野頼子など、SFやファンタジーの強い影響を受けて1990年代にデビューした一連の女性作家の系譜に位置づけることもできる。例えば、それはこの後に述べる「言語」への着目とも相俟って多和田葉子などにも共通する指向を持つだろう)。