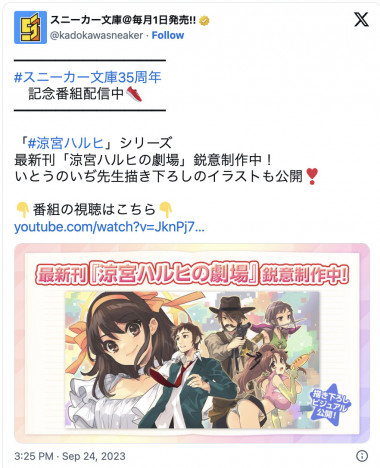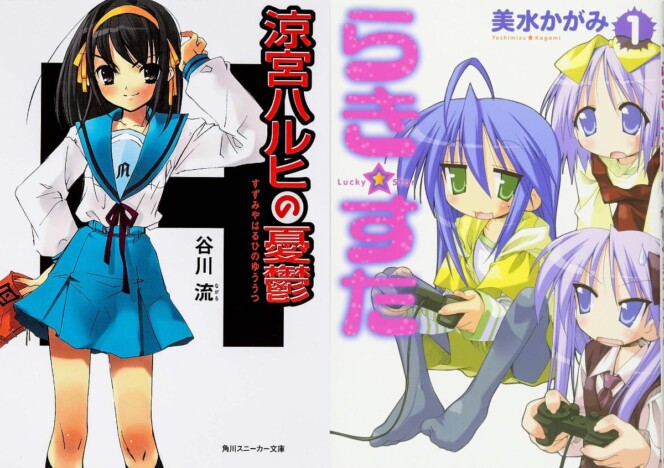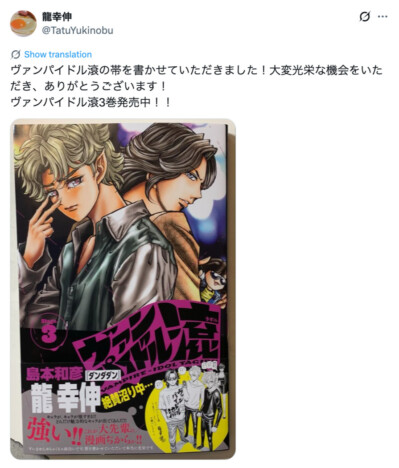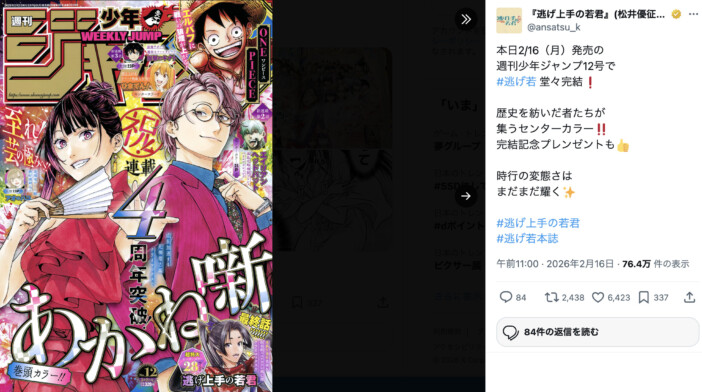ツンデレの文学史――「スクリューボール・コメディ」との相似性、長い歴史を振り返る
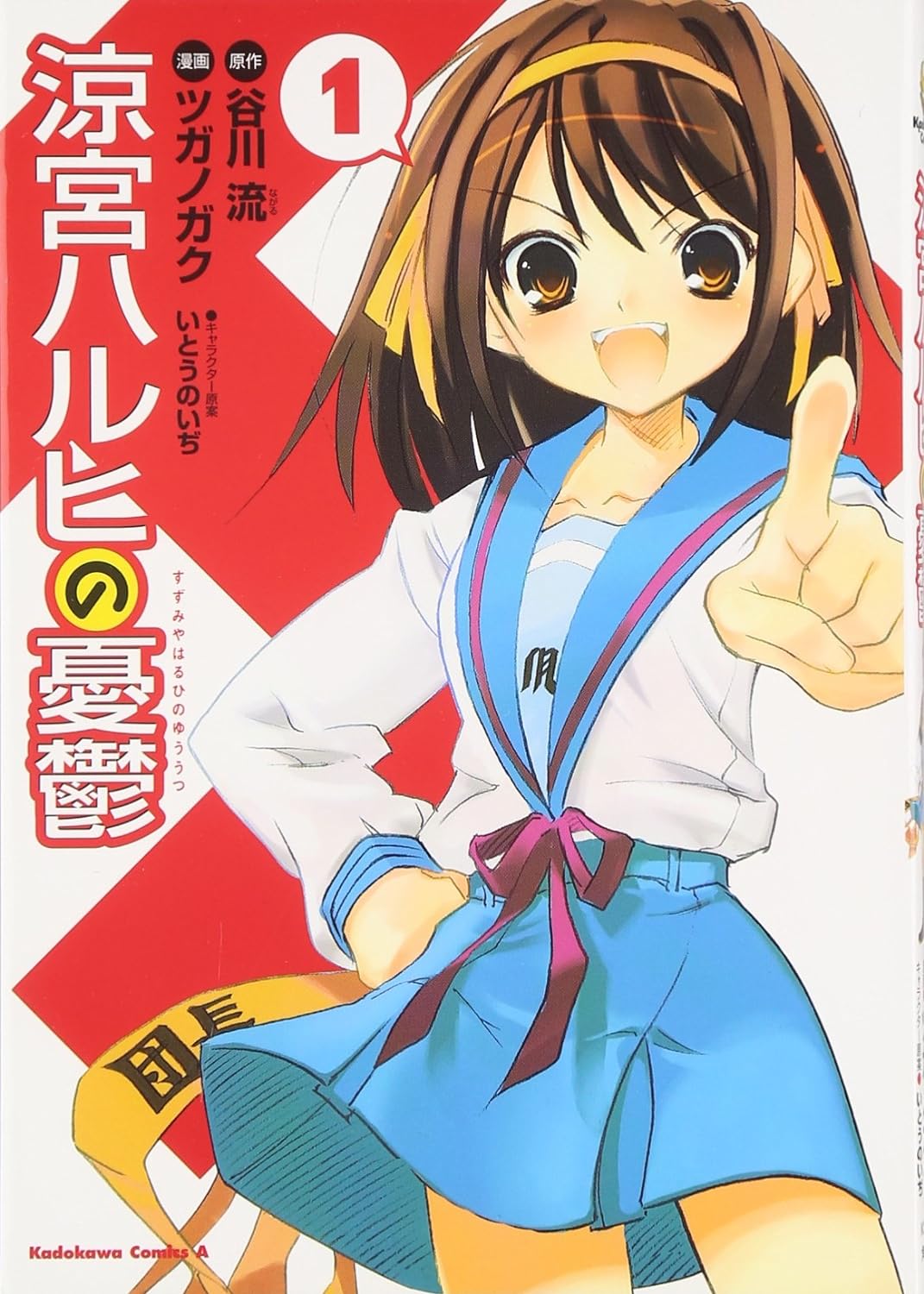
■ツンデレ≒スクリューボール・コメディのヒロイン
時代を大きくさかのぼる前に、近現代に発生した代表的フィクションの媒体である映画の、一つのサブジャンルの話をしておこう。スクリューボール・コメディとは1930年代初頭から1940年代にかけてハリウッドでさかんに作られたコメディ映画のサブジャンルの一つである。
スクリューボールとは野球の球種の一種であり、スピンがかかりどこでオチるか予測がつかないボールであることから突飛な行動をとる登場人物が出てくる映画をこう呼ぶようになった。ラブコメの古典的名作『或る夜の出来事』(1934)が興行・批評の両面で大成功したことで同種のスクリューボール・コメディが大量生産されることになる。
余談だが、現代のMLBにおいてスクリューボールの使い手はほとんどいないが、野球殿堂入りしたカール・ハッベル(1903-1988)が1930年代当時、まさに全盛期を迎えており、彼はスクリューボールを武器にしていた。現代のアメリカでは野球の人気そのものが衰退しており、ファン数でサッカーに抜かされて4番手に落ちそうな勢いである。時代を感じる表現である。
『或る夜の出来事』は「大富豪の父親から望まぬ結婚を押しつけられることを嫌って家を逃げ出した娘が、この家出話をゴシップ記事として売れるとにらんだ新聞記者と逃避行をともにするうちに恋におちる」というまるでどこかでテンプレートをコピーして作成されたような内容だ。だが、何事にも原初・原典が存在し、この作品の設定は当時は斬新だった。同作の身分違いの恋、スピード感あふれる展開、気の強い女性が男と対等の立場で交わす軽妙な会話といった要素はスクリューボール・コメディが衰退したのちも模倣され続け、今では「テンプレ」とまで言えるほどに定着している。
さて、筆者はここで「現代の作品など全部パクリである」などと批判する気はない。映画界には「映画100年の歴史は盗作100年の歴史」という格言が存在し、人の作った優れた作品を模倣するのは当たり前の行為だとすら言える。「学ぶ」は「真似る」に由来するとの説もあり、他人の作った優れたお手本を真似るのはどのような分野にでも当てはまる。(かく言う筆者は映画脚本家としての実績もあるが「影響を受けた作品は?」と聞かれたら何の恥じらうこともなく答える)
ここで強調したいのは、『或る夜の出来事』に出現し、テンプレ化した要素の一つ「気の強い女性が男と対等の立場で交わす軽妙な会話」である。そして、スクリューボール・コメディのヒロインはさんざん気の強い発言でやりあったすでに、最後はデレる。ここにツンデレへの既視感を感じるのは筆者だけではないはずだ。
ツンデレの主要な構成要素とスクリューボール・コメディのそれはほぼイコールと言えるのではないだろうか。 ではその「気の強い女性が男と対等な立場で軽妙な会話」をして「最後にはデレる」展開は1930年代のハリウッド映画以前には存在しなかったのだろうか?
もちろんそんなことは無い。
筆者が知る限りでもその要素の創作への出現は、少なくとももう300年は遡れる。