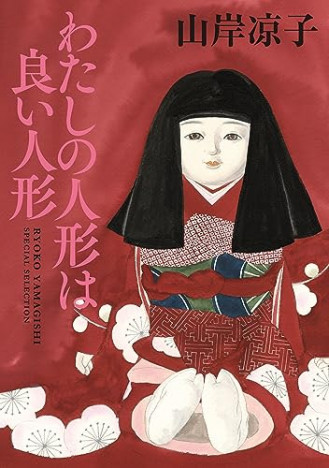令和に読む名作漫画『日出処の天子』 聖徳太子のイメージを大きく変えた山岸凉子の異才に迫る

「いつも女が男の餌食にされるなんて」
この言葉は終盤での刀自古郎女(刀自古)の嘆きである。
彼女は本作のヒロインとも言える存在で、毛人の妹である。つまり蘇我氏の女なので、政略結婚はまぬがれない。史実でも厩戸王子と結婚をするのだが、本作ではフィクションの展開がとりわけ強調されて、少女時代は無邪気だった彼女を、運命は容赦なく打ちのめす
そんな彼女が、ある女性の遺体を見て心の中で見出しのように嘆くのである。
1980年代前半、エンターテイメント作品におけるジェンダーやフェミニズムに焦点があてられるのは非常に珍しいことだったはずだ。勘の良い刀自古は、無意識のうちに女性たちの運命を狂わせているのは男性社会だと見抜いている。刀自古自身が、女性であるがゆえの数々の不幸と対峙してきたからこそ、そのことが理解できるのだろう。
そもそも史実を見ても、刀自古は厩戸王子の妻で山背大兄王子の母親だったことしか描かれておらず、生没年も不詳である。しかも本作では異母妹だった河上娘と史実では混同されており、河上娘の妹、もしくは同一人物だったのではないかとも言われている。
これは刀自古だけではない。この時代を生きた高名な男性の詳細はほぼ明らかになっているのに、女性には生没年どころか名前や存在すらあやふやな人物が数多く存在していて、これは江戸時代になっても続いている。私が気づいていないだけで明治時代以降もそのような例は多いのかもしれない。
歴史の中で運命に翻弄される女性の悲しみを、刀自古の運命や刀自古と関わりのある女性を通して描写して、刀自古に「いつも女が男の餌食にされるなんて」と思わせる山岸凉子の観点に圧倒される。“女性は好きな男性に愛されてハッピーエンド”という少女漫画へのアンチテーゼとまではいかないが、この時代に刀自古を通してそれを言わせたのは、作者のジェンダーに対する意識の高さをも表しているのだろう。
厩戸王子も毛人も、非常に敏感な人物なのだが、男性であるがゆえに女性が理不尽な目に遭う不幸には気づかない。刀自古についてはほかの記事でも触れたいと思う。
『日出処の天子』はバッドエンドなのか
この記事を書きながら、悲劇=バッドエンドだと考えていた自分の短絡的な考え方に気づかされた。
『日出処の天子』は悲劇である。しかしながら登場人物全員が、今で言うところの大学生くらいの年齢で完結しており、実際に厩戸王子(聖徳太子)が数多くの功績を日本史に残すのは『日出処の天子』の後だ。史実を見れば彼らの子孫には陰惨な末路が待ち受けているが、たとえそうであっても、以後死ぬまで、喜びもなく悲しみもない人生があるとはとうてい思えない。これは1990年代半ばの文庫化で、当時小学生だった私が、初めて本作に触れたときにはわからなかった感覚でもある。何せ当時の私はほとんどの登場人物より年下だったのだ。
本作に登場したある女性は、死ぬ際に、自分に仕え、自分をかばって死んだ老女に連れられていく。このくだりには少々驚いた。厩戸王子がほのめかす死後とは大いに異なるからだ。彼女が死ぬ間際に見た幻想なのかもしれないが、そうだとしたら毛人も、死ぬ間際に厩戸王子に連れられて今度こそ一緒になる可能性もあるかもしれない。史実では、毛人の最期は、息子の入鹿が殺された後に自殺という決して安穏としたものではないが、もし厩戸王子が毛人の死をもってして、性別すら超えたところで彼といっしょになることができたなら……と願ってしまう。
私は漫画オタクなのでよく誤解されるが、BL好きではない。ただこの『日出処の天子』や竹宮惠子の『風と木の詩』を読むと、同性·異性に関係なく、愛する人の性別を気にすることなく愛し合えたら良いのにと願ってしまう。
この令和の世になって、多少はそれが受け入れられるようになった。ただエンターテイメント作品だけではなく、現実でもそうあってほしいと本作を読みながら思い、毛人の死後のハッピーエンドをどうしても願ってしまうのである。
※初出誌一覧
『日出処の天子』:「LaLa」(白泉社)1980年4月号~1984年2月号、4月号~6月号
『アラベスク 第1部』 [りぼん版]:「りぼん」(集英社)1971年10月号~1973年4月号
『アラベスク 第2部』[花とゆめ版]:「花とゆめ」(白泉社)1974年6月号(創刊号)~1975年22号