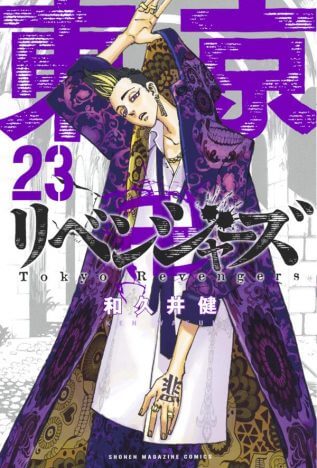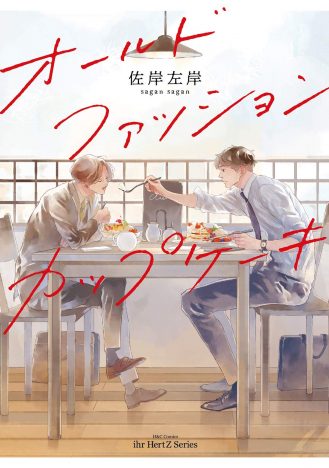佐々木チワワが語る、歌舞伎町とホストクラブ文化 恋愛観と金銭感覚は今どうなっているのか

『「ぴえん」という病 SNS世代の消費と承認』(扶桑社新書)で昨年デビューを飾った現役大学生ライター・佐々木チワワ氏。11月に刊行された新書『歌舞伎町モラトリアム』(KADOKAWA)は、佐々木氏が15歳の時から「ホーム」として生きてきた歌舞伎町の現在、またそこに生きる若者たちを、彼女ならではの視点でとらえたエッセイ集だ。
「痛客」「繊維」「ラスソン」など、歌舞伎町でよく聞く言葉を解説した「歌舞伎町用語集」や、「童貞も守れない男になにも守れないんですよ」という名言で知られる草摩由紀氏など、歌舞伎町の有名ホストとの対談も収録した幅広い内容の一冊となっている。歌舞伎町という町の魅力やこの街だからこそ生まれる関係性の機微について、話をうかがった。(若林良)
歌舞伎町にのめり込むまで
――佐々木さんと歌舞伎町の出会いは、2015年の大みそかに現地を訪れ、年明けを挟む2泊3日でご友人と過ごされたことにあるそうですね。
佐々木:2万円を手に、まずは居酒屋に行ったことがスタートでした。何もかもがはじめてだったわけですよね。都会の喧騒に触れるのも、居酒屋に行くのも。大晦日だったので街もより浮かれていて、0時になった瞬間にみんなで「あけおめー!」って叫ぶようなことも楽しかった。
街を歩いていたら、外国の方に「新しい友達!レッツシングトゥギャザー!」みたいな感じで声をかけられて、一緒にカラオケに行ったんですよ。そうしたら、同じように連れてこられた日本人の男性2人がいて、一緒に歌ったり、合コンめいた雰囲気にもなったり。非現実が本当に楽しくて、それから3年連続で歌舞伎町で年越しをするようになりました。そして18歳になってはじめてホストクラブに行き、現在に至る……という感じですね。
――なるほど。本書では歌舞伎町に行くようになったきっかけとして、「誰かに、何かに没頭したかった」とも書かれています。どういうことでしょうか。
佐々木:本当にホストクラブに没頭している友達がいたことが大きかったですね。話をしていても、生活の全てがホスト中心で、それ以外に話題がなくて。また、学校をやめて親との縁も切りかけていたこともあって、それほど彼女の熱量は高かったんです。そういう選択の是非について、上からああだとかこうだとかも言えるでしょうけど、私はそこまで一人の人に入れ込むことを、まぶしく思ったんですね。当時の私は自身のキャリアを全部捨ててまではまる何かに出会ったことが人生でなかったので、そこまで想える何かへの出会いを得たいと感じるようになったんです。
――実際、ホストクラブを経験されたことで、歌舞伎町の楽しみ方が異なったものになったと思います。
佐々木:そうですね。まさに新しい世界のはじまりでした。そこからの経験が、『歌舞伎町モラトリアム』には反映されています。
ホストクラブならではの金銭感覚

――素人目線ですが、ホストクラブですと、まずお金の使い方により幅が出てくるように感じます。たとえば、はじめて佐々木さんが飾りボトルを卸した時のエピソードが語られますが、いくらくらいだったのでしょうか。
佐々木:30万円ですね。いくつか種類があって、45万円とかもあります。
――おお……。それはその場で支払われたのでしょうか。
佐々木: 半額はその場で支払って、残りは立替(ホスト個人が売掛を立て替えてくれている状態)にしてもらって、何か月かかけて返しました。未収が残っていると、女の子もホストもお互いに関係を切れないんですよね。
――それを聞くと、逆にホストにずっと会いたいから、あえて売掛にするような手段もあるように思います。
佐々木:そうですね。そのやり方は「売掛縛り」と呼ばれるものです。歌舞伎町には売掛の金額が700万とか、多ければ3000万円なんて人もざらにいます。ホストが自分のことをどんなに嫌いでも、お金の関係がある以上は連絡を取らざるを得ないので、それを利用する女性がいたり。逆にホストがそういう関係がストレスになって、「自分がそのお金を立て替えるから、もう関係は絶つ」と告げるようなこともありますね。お金を介することによって発生する関係が色々とあって、それは面白いと感じています。
――ぎりぎりの駆け引きのようなものを感じますが、その一方で、ホストの世界がよりマイルドになったことも本書では示唆されます。たとえば、歌舞伎町の女の子が優しくなったことや、元祖アイドルホスト・やるきげんきだいきさんとの対談の中で、ホスト業界も「人材切り捨て方式」から「長期でいい男の子を育てる方式」に変化していったことが語られますね。
佐々木:そうですね。それには、市場が拡大していったことが大きいです。もともとは有閑階級と言いますか、お金に余裕のある富裕層の女性か、歌舞伎町で働く夜の女の子たちだけがホストクラブを利用するような形だったのですが、近年の客層はより広がってきています。いわゆる普通の女の子たちも、アイドルのライブのような感覚で来るようになりました。また彼女たちが、親子連れやカップルで来ることも今は少なくはありません。
その背景にあるのは、SNSの存在です。TikTokなど、いくつものSNSでホストが発信を行い、これまでよりも多くの人たちがホストクラブの存在を認知できるようになりました。それに伴って、ホストクラブを経営する側の人たちも、よりクリーンな世界にしていかなくてはという意識を働かせるようになったんです。
ホストをめぐる文化にもまた、変化が起こりました。以前は、「ヤバい女の子をものにしてこそホスト」みたいな美学があったのですが、問題のある客を相手にするとなると、ホストにとってはストレス以外の何物でもないですよね。自分の心を守るために客との関係を断つこと、また客を選ぶことがより許容されるようになりました。ホストの文化を続けていく上で、喜ばしい変化だと思います。