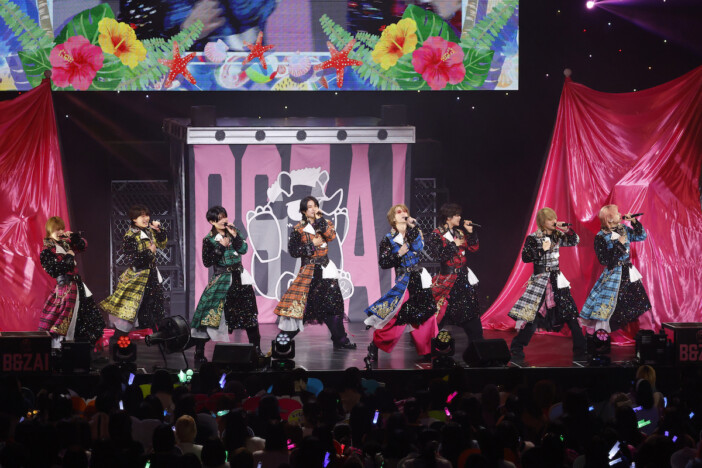『第68回グラミー賞』最優秀新人賞ノミネート オリヴィア・ディーンが描く“愛”が現代に響く理由とは【著名人コメントあり】

2025年を代表する一枚となった『The Art Of Loving』においても、こうした魅力は、さらに上質に磨き上げられた上で、しっかりと引き継がれている。
〈It's the art of loving, it's the art of loving/It wasn't all for nothing, yeah, you taught me something〉
(それは愛する技法/すべてが無駄だったわけじゃない そう、あなたに教えられたこともあった)
1曲目となる「The Art of Loving (Intro)」では、どこかに想いを馳せるような優しい歌声とともに、さまざまな“愛”を経験したオリヴィアの回想する姿が描かれている。この時点で、アルバムに収録されている楽曲の一つひとつが、「無駄だったわけじゃない」と思うような場面を切り取ったものであることが示唆される。
実質的なオープニングナンバーである「Nice to Each Other」は、Fleetwood Macの影響を感じさせる、まるで電車の車窓を眺めているかのような軽やかな楽曲だ。そこに広がっているのは、どこか熱を失ってしまったカップルが変化を求めてイタリアへと向かう様子であり、オリヴィアは〈We could be nice to each other〉(お互いに優しくなれるかも)と期待しながらも、心のどこかで、それがうまくいかないことを確信している。
オリヴィアの必殺技である、楽曲のいちばんの聴かせどころで放つキラーフレーズは、ここでも見事に炸裂している。
〈Meet me on the mountaintop/I'll be in the shallow end/And wait for you to call it off/'Cause I don't want a boyfriend〉
(山のてっぺんで会おう/私は浅瀬にいるから/そこであなたが諦めるのを待ってる/だって彼氏なんていらない)
流れるような演奏がふっと止まり、〈だって彼氏なんていらない〉という歌声が力強く響く。少しずつ積み上げてきた「何か」が一気に崩れ去る瞬間の、切なくもどこか元気づけられてしまうような奇妙な感覚は、まさにストーリーテラーとしてのオリヴィアの真骨頂だ。
「The Hardest Part」でも描かれていたように、「経験を重ね、変化していくこと」はオリヴィアにとってのひとつの象徴的なテーマなのだろう。アップリフティングな「Lady Lady」では、(恐らくは「Nice to Each Other」の後に迎えたであろう)別れを経て、戸惑いや希望を抱く今の自分自身を、〈Growing on, growing into it/And it's all going on〉(成長して 馴染んで/そうやって何もかも続いていく)と「変化の過程」としてありのままに受け入れようとする。
『The Art Of Loving』の興味深いところは、本作がいわゆる“ハートブレイクアルバム”ではないということだ。「Close Up」で予感させた新たな愛の予感は瞬く間に高まっていき、オリヴィア自身も愛してやまない(「Man I Need」のリリックにも登場する)ボサノヴァ調の「So Easy (To Fall In Love)」では、リラックスしたムードのなかで〈I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life〉(私には 土曜日の夜のワクワク感と一生を共にする安心感があるの)と自信をのぞかせる。
「パートナーなんて必要ないの」という強い想いと、「私こそがあの人にピッタリに違いない!」という浮足立った姿。それは、どちらも愛と真摯に向き合ったオリヴィアの姿にほかならない。今なおロングヒットを続ける「Man I Need」は、その狭間で揺れ動くオリヴィアの姿を巧みに描いた楽曲でもある。
〈Tell me you got something to give, I want it/I kinda like it when you call me "Wonderful"〉(言ってよ「渡すものがある」って、ほしいの/「魅力的」って言われるとなんだか嬉しい)というサビのフレーズに象徴されるように、楽曲全体を貫くのは、想いを寄せる相手にすっかり夢中になっているオリヴィアの姿だ。まるで恋愛モノのミュージカルのような展開が繰り広げられる幸福感に満ちたMVも相まって、一聴するとポジティブに突き抜けた楽曲のように感じられるかもしれない。
だが、耳に残る〈Talk to me, talk to me〉(話して、話して)というフレーズの反復が示すように、楽曲の至るところから、相手に対する「ちゃんと想いを言葉にして伝えてほしい」という願いが滲んで、染み渡っている。持ち味でもある美しいコーラスワークは、喜びと不安を同時に抱く多面的なオリヴィアの姿を表現しているかのようだ。
アルバムが後半へと向かうと、かつては浮足立っていたオリヴィアの感情に、再び暗雲が立ち込めたり、希望が垣間見えたりと、いずれにしても“永遠の愛”とは程遠い光景が続いていく。だが、その一つひとつをオリヴィアはやはり真摯に受け止め、豊かな感情を残さず音楽を通して拾い上げていく。だからこそ、その音楽性は前作からさらに広がり、一言で「R&B/ソウル」とは形容できない、ここでしか味わえないような手触りになっている。
英オックスフォード英語辞典を出版するオックスフォード大学出版局が、2025年の「今年の単語」に「レイジ・ベイト」を選出したように、近年の潮流といえば、瞬く間に受け手の感情を刺激するようなコンテンツが重視される傾向にある。だが、オリヴィアの描く光景はそうした「分かりやすさ」とは無縁で、一言では表現できない重層的なものが多い。だが、その「リアルな複雑さ」こそが、オリヴィアが多くの若者を惹きつけてやまない理由なのではないだろうか。安易な言葉で片付けられてしまいがちな繊細な心に、オリヴィアの音楽はそっと寄り添ってくれるのである。
それは、複雑怪奇な“愛”というものと真摯に向き合い、そこから生まれる一つひとつの出来事を、ありのままに受け入れながらアートへと昇華していくオリヴィアの豊かなアーティストとしての生き方が導いた結果なのだろう。
アルバムの最後を飾る「I’ve Seen It」で、オリヴィアはこのように歌い上げている。
〈Catches your eye, you blink and then it's gone/Brings out the worst, brings out the best/I know it's somewhere in my chest/I guess it's been inside me all along〉
(目に留まり 瞬きすると消えてしまう/最悪な面を引き出したり/最高な面を引き出したり/そう、この胸のどこかにあるの/たぶんずっと私の中にあったんだね)
自分のなかに愛を見つけたオリヴィアは、再び前へと進んでいく。変化を楽しみながら、きっと今年も私たちを楽しませてくれるはずだ。
※1:https://www.nylon.com/entertainment/olivia-dean-tour-man-i-need-the-art-of-loving-interview