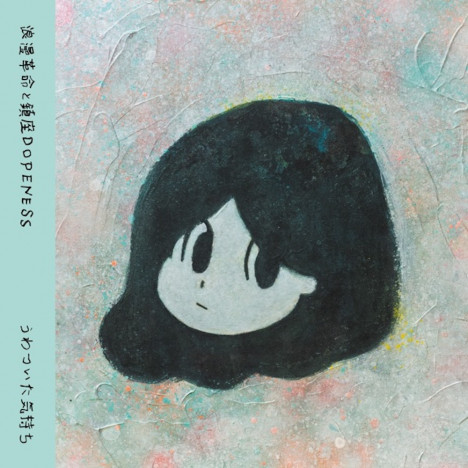J-POPの王道に連なる新たな存在 2024年注目のSUKEROQUE、表情豊かな楽曲に滲む独自の視点

1970年代〜90年代の洋楽のエッセンスを取り入れながら、日本語ならではのノリをしっかり感じさせてくれる楽曲。都会の中心ではなく、郊外(=サバービア)で暮らす人々の姿や思いを投影した歌詞。シンガーソングライター SHOHEIによるソロユニット SUKEROQUEは、日本のポップスの王道を受け継ぐアーティストだ。
SUKEROQUEの音楽的原体験は、父親が聴いていた山下達郎や松任谷由実で、洋楽はスティーヴィー・ワンダーやマイケル・ジャクソン。10代になるとMuseやTravisなどのメロディアスなUKロックを聴き始め、音楽への興味を大きく広げた。過去のインタビューではSMAPへの共感を示すなど、メインストリームのJ-POPもしっかりチェックしていたようだ。
大学在学中に前身バンドを結成し、渋谷を中心にライブ活動を展開。メンバーの脱退を機に、自らの音楽性をさらに追求すべくソロユニットとして始動した。SUKEROQUEという名前は、歌舞伎の代表的な演目の一つである「助六」に由来。江戸歌舞伎の粋を集めたと称される“助六”を自らのアーティスト名に据えるあたり、実はかなりの自信家なのかもしれない。
最初の作品は、2019年リリースのEP『SUKEROQUE -EP』。1曲目の「超Very Good Times」は、ファンク/ソウルのテイストを取り入れたバンドサウンド、軽妙でしなやかなメロディ、そして、物足りない日々を前提にしながら、それでも〈実はハッピー 今だたのし〉と歌い上げる歌詞が一つになったこの曲は、まさにSUKEROQUEの原点と言えるだろう。
その後のリリースは1年に1曲ペースだったが、2023年7月に発表された「オリーヴの星」「蝸牛」から6カ月連続で新曲をドロップ。リリースを継続することで、多彩な音楽性とアーティストとしてのポテンシャルを幅広いリスナーにアピールしてきた。
ブルースロック的ギターリフから一転、スムースなファンクサウンドへと移行する「オリーヴの星」はサビに入った瞬間に華やかなポップネスをまといながら聴く者を魅了。抒情的にしてメロウなR&Bバラード「蝸牛」では、優しさと繊細さを併せ持ったボーカルを響かせる。この2曲のアレンジには日本のファンクミュージックの要である屋敷豪太、SEKAI NO OWARI、Official髭男dismなどの楽曲に関わってきた保本真吾が参加。SUKEROQUEの音楽性の精度を引き上げることに成功している。
さらに、疾走感のあるビートと鋭利なギターを軸にした爽やかなアッパーチューン「COOL CHINESE」(2023年8月)、ミクスチャーロックの進化型と称すべきサウンドと高度な情報社会におけるカオスをテーマにした歌詞が響き合う「utopia utopia」(2023年9月)、軽妙なギターカッティングとシンセベースが心地いいトラックのなかで“男女の恋の駆け引き”を描いた「市街地」(2023年10月)と、リリースを重ねてきた。
なかでも個人的にもっとも心に残ったのは、11月にリリースされた「トランジスタレディオ」だ。楽曲の中心を担っているのは、美しく、ドラマティックな旋律。ボーカルを支えるシンセのカウンターメロディをはじめ、洗練されたアレンジも素晴らしい。編曲とプログラミング、すべての楽器を担当しているのは、伊藤立(agehaspringsParty)。YUKI、ELAIZA、玉井詩織などの楽曲に携わってきた伊藤の手腕にも注目してほしい。