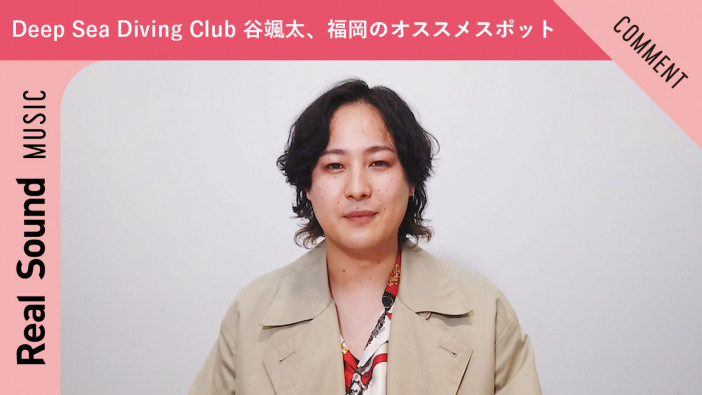Deep Sea Diving Clubのシティポップにあるオリジナリティの背景 谷 颯太が語る、“東京三部作”に至るまでの歩み

福岡を拠点に、「TENJIN NEO CITY POP」を掲げて活動する4人組バンド・Deep Sea Diving Club。今年1stフルアルバム『Let's Go! DSDC!』をリリース、初めてのワンマンツアーも開催。7月には「フーリッシュサマー」、そして9月には“シティポップといえばこの人”という土岐麻子を迎えて「Left Alone feat. 土岐麻子」をリリース、ますますポップに進化したサウンドを武器に、じわじわとその名前を全国区に広げつつある。
そんなDeep Sea Diving Clubが「フーリッシュサマー」「Left Alone feat. 土岐麻子」に続く“東京三部作”(東京でレコーディングしたのでメンバーはそう呼んでいる)の完結編としてリリースしたのが「Miragesong」。ポップなサウンドが切ない感情に寄り添い、ドラマティックに展開するウィンターソングだ。これまで以上にポップさを追求しつつ、結果的にはボーカル・谷 颯太のパーソナルな部分も色濃く滲み出たこの曲が生まれた背景、そしてバンドのこれまでの歩みについて谷に語ってもらった。(小川智宏)
シティポップで初めて親和性があるジャンルにたどり着いた

――今年、Deep Sea Diving Clubはアルバムを出し、ワンマンツアーもやり、今作も含めて3作シングルを出し。ギアを入れて活動してきました。どんな心持ちで走ってきましたか?
谷:今年は年明けからアルバムのレコーディングと、1月にもツアーをやって。頭からかなり準備をして動いてきました。今までは結構ギリギリというか、いきなり作っていきなり出す、みたいなことも多かったので、時間をちゃんと作って、ツアーもレコーディングも準備ができるようになりました。
――結成されたのが2019年ですよね。その当時はどういうビジョンを持って組んだんですか?
谷:もともと自分がいろんなオリジナルバンドをやってきたタイプで。もう覚えてないぐらいの数のバンドを経験して、最後はアコースティックで活動をしてたんです。それが活動休止したときに、正直バンドはもういいかなと思ったんですよね。自分がソロでやって、知り合いの楽器の上手い人にサポートしてもらおうかなって感じだったんですけど、ひょんなことから今のメンバーと出会って、バンドにした方がいいなって思って。今まではバンドを組んでもちょっとライブをするくらいの活動が多かったし、周りもそうだったんですけど、このバンドは最初から、「組みました」って言ったときにはMVが出来上がってて、「パーティするので来てください」って言える状態になっていたんです。今までの失敗を踏まえてじゃないですけど、先を見て動いてきたバンドだったので、それがうまく転じたのかなと思います。
――今までいろんなバンドをやってきたというお話でしたけど、音楽的にも結構変遷してきたんですか?
谷:そうですね。初めてライブハウスに出たのは中学生の同級生と組んだONE OK ROCKさんのコピーバンドだったんですよ。オリジナルもちょっと挑戦しつつでしたけど、そこからは結構ハードコアな音楽をやっていました。シャウトのボーカルをしていたり、そういうバンドが流行ってた時期でもあったので。そのあとはキーボードがいるポップなバンドをやったり、ファンクっぽいバンドをやったり。でも、割合でいうとロックバンドだったことが多いですね。最後はアコースティックだったんですけど。
――いろいろやってきているんですね。このバンドでシティポップをやるようになったのはどうしてなんですか?
谷:大学生のときに組んでいたバンドが、みんなJamiroquaiとかが好きで。ベースの人が特にファンクが好きだったので、いろんな音楽を教えてもらってたんですよ。その頃って日本でシティポップがリバイバルする直前ぐらいで、新しいバンドがいろいろ出てきだした時期でもあったので、友達の家でお酒を飲んだりすると、大体そういうバンドの曲がかかってて。ペトロールズとかLUCKY TAPES、あとbonobosが「Cruisin' Cruisin'」を出した時期でもあって、なんかいいなって思ったんです。そこからメンバーに教えてもらって、そういうバンドも聴くようになって。今も忘れられないんですけど、今のバンドみたいなことをしだしたときに母から「絶対こっちの方が合ってる」と言われたんです。その時はピンと来てなかったんですけど、今思えばいろいろやってきた中で初めて親和性があるジャンルにたどり着いたのかなとは思いますね。
――でも、それまでやってきた音楽とは違う音楽を新しいバンドでやっていくことに難しさは感じませんでしたか?
谷:逆にいうと、今までのバンドがうまくいかなかったのって、自分も含めていろんなジャンルに挑戦する技術がなかったってことなんですよね。作曲能力も演奏能力も。でもDeep Sea Diving Clubはむしろそれができるなって最初に気づいたので、難しさというよりは心強さのほうが大きかったです。今までできなかったことができるようになって、最初からすごく楽しかったですし。やっぱりある程度技術があると自由度が上がるんだなっていう実感はありました。できる楽曲の解像度も上がっていく感じがありましたね。

――それでいうと、今年出したフルアルバム『Let's Go! DSDC!』がいわばそこまでのDeep Sea Diving Clubの1個の集大成みたいな作品になったじゃないですか。その後出してきている「フーリッシュサマー」からの3曲って、またそこともフェーズが変わってきているような感じがしますね。
谷:そうですね。作り方も途中で変わって、セッションで作る方法からみんなDTMで曲を作るようになって、メンバー4人とも曲を作るようになったんですよ。アルバムのときも、新曲が半分入っているんですけど、その6曲ぐらいは今のやり方の始まりみたいな感じだったんです。アルバムが終わってからの3曲はそれをさらに突き詰めたやり方になっています。あとは東京でレコーディングするようになったのも大きな違いですね。アルバムまでは福岡で録っていたんですけど、東京でやると選べる機材もスタジオの大きさも、使える時間もスケジュールも違うし。あとスタッフさんが多くて、初めて東京でやったときはみんなキョロキョロしてました(笑)。
――先ほど解像度が上がったみたいな話をされてましたけど、音源を聴くと制作の面でもまさに解像度が上がったんじゃないかなと思います。
谷:そうですね、4人とも曲を作るようになったので、まず擬音で喋らなくなりました(笑)。自分が携わっていないパートでどの楽器の音が鳴っているかがみんなわかってきているので、曲も歌詞もすべて解像度が上がっている、より細かく見られるようになった気がします。
――メンバーそれぞれがDTMで曲を作るようになると、よりそれぞれの趣味やバックグラウンドも出やすくなっていくじゃないですか。そういうことも感じますか?
谷:特にアルバムのときは感じましたね。一聴しただけで誰が作ったかわかるなって。出原昌平(Dr)がアレンジを担当していて、そこでなんとなく整理される感じはあったんですけど、みんながやりたいことをぶち込んできて「さてどうする」みたいな(笑)。出原はスタジオミュージシャンをしていた経歴もあるので、音楽的な知見もメンバーの中では一番広くて、いろいろ教えてくれるので。アルバムまでは特に、かなり助けてもらいました。
“東京三部作”への挑戦でバンドが手に入れたもの

――Deep Sea Diving Clubは現在も福岡在住ですけど、福岡という街がバンドの表現に影響を与えているところはあると思いますか?
谷:街ならではの音楽の歴史があるのが大きいとは思います。福岡って外から見ると、地方の中でもかなり特殊な街だって思われている感じがするんです。自分たちからすると普通なんですけど、ジャンルがごちゃごちゃだったり、みんないろいろやっていたりして。プレイヤーとエンジニアを兼ねている人も多いですし、今はわからないですけど自分がDeep Sea Diving Clubをやる前はドラムとベースが取り合いみたいな感じだったんですよ。兼任も多かったし。それがすごく変わっているということは県外に行って初めて気づきました。メンバーと帰りながら「福岡ってなんか変じゃねえ?」みたいな話をして。
――そういう血が流れているからなのかなと思うんですけど、シティポップをやっても、東京のバンドが鳴らすシティポップとやっぱり全然違うものになるんですよね。
谷:やっぱり違いますね。最近それはすごく感じます。ビートが均一じゃないなって自分では思っていて。東京のバンドというか、いわゆる近年のシティポップって、メロウで、ちょっとBPMが遅かったり、ビートがずっと均一っていうイメージがあるんですけど、そういう曲を聴いてから自分たちのバンドを聴くと少し激しいなと思いますね。
――たぶん4人それぞれが聴いてきた音楽の影響もあるでしょうし、人間くさい部分が出ているし、出したくなるのかなと思いますけどね。で、今回「Miragesong」という、“東京三部作”を締めくくる曲が出たわけなんですが。これはどういうふうにできていったんですか?
谷:“東京三部作”は自分たちで勝手に言ってるんですけど(笑)。バンド内でリリースに向けて「コンペ」を行いまして。1作目の「フーリッシュサマー」から初めての東京で、しかも初めてアレンジャーさんと一緒に作ったのもあって、かなり曲に対しての考え方が変わって。どうやったらポップになるのか、どうやったらいろんな人に聴いてもらえるだろう、とより考えるようになったんです。それで「Left Alone」を土岐さんと一緒に作らせていただいて、人が聴きたくなるメロディや歌詞にみんなかなりの密度で触れたというか。今回の「Miragesong」に向けた「冬のコンペ」は、「冬」というテーマとともに、「ポップ」というのもテーマとしてあって。出原が作ってきたこの曲を初めて聴いたとき、隙のないポップスだなと思ったんですよね。彼はAメロから全部サビみたいなメロディで作りたいと言っていて、鼻歌でメロディを入れたデモが送られてきたんですけど、かなり本気だなと思いました。
――ポップという部分でいうと、歌とメロディがやはり重要ですよね。
谷:そうですね。ただこれ、歌う側からすると難しいんですよ。頭のメロディがすごく難しい。でも出原と一緒に仮歌を取りながら2人で修正したり、あとは歌詞を自分が書いたので、歌詞に合わせてメロディを修正して、引くところは引いて、お互い譲れないとこはちゃんと出して。そういう会話を重ねてできあがっていった感じです。