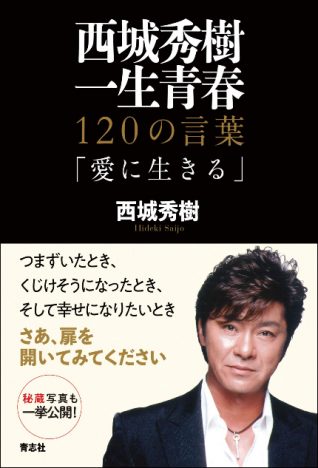西城秀樹が体現したロックシンガーとしてのダイナミズム サエキけんぞうによる復刻ライブアルバム徹底解説

日本のロックシンガーの草分けとして熱狂を生んだ西城秀樹
「昭和の歌手」に注目が集まっている。DJからも若者からも。今の世の中からは生まれ得ない存在感があるからだ。
その中では、西城秀樹が筆頭に上げられるだろう。ダイナミックなキャラクターと豪快な歌声は、今聴いても感嘆せずにはいられない。2022年3月にはデビュー50周年を迎え、昨年6月より入手困難なアルバムの復刻発売がスタートした西城秀樹。これらを聴けば、これまでの評価では生ぬるいことがわかるだろう。
氷室京介やYOSHIKIが賛辞を述べたり、甲本ヒロトも初めて買ったレコードが『薔薇の鎖』(1974年)だと明かしているなど、1980年代以降のロックアーティストからの支持は極めて分厚いものがある。そう、西城秀樹こそ「日本のロックシンガー」の草分けなのかもしれない。そんなことを昨年12月24日に発売された復刻リリース第三弾であり、その真骨頂ともいえるライブアルバム5タイトルを一気に聴いて感じさせられた。

僕は西城秀樹の「Rock Your Fire」(1991年)という曲に詞を提供したことがある。その時に素晴らしい歌唱を目の当たりにしたためシンパシーは強いが、一方で1970年代の自分のロック少年時代には、歌謡曲勢の一人ということで「ロックではない」と色眼鏡で見ていたことを告白する。それは当時の大勢の洋楽ロックファンと同様だろう。日本語の歌謡曲歌手は、ミック・ジャガーやデヴィッド・ボウイと比べて卑下される傾向にあった。
それを何故ひるがえすことになったのだろう? その理由を考えながら、西城秀樹が日本のロックのオリジネイターの一人であることを証明していこうと思う。

ライブアルバム1枚目『西城秀樹 オン・ステージ』(1973年)は、1973年3月26日に大阪毎日ホールで開催されたライブを収録。17歳という、彼の最初期のコンサートのライブ録音だ。一聴して、今の若いリスナーには新鮮な編曲だろう。ジャズメンを中心とした演奏で、普通のロックではない。冒頭を飛ばす「グッド・ゴーリー・ミス・モーリー」「ジョニー・B.グッド」といったロックンロール曲も、The Beatlesやエルヴィス・プレスリーのような演奏ではない。ジャズタッチのドラム&ベースなので、「ビートの刻み」が非常に細かい。後のジャンルでいうならアシッドジャズ風。1960年代末、ラテンではブーガルー、ポップスではシェイクと呼ばれたリズム。ジャズメンは、リンゴ・スター(The Beatles)やジョン・ボーナム(Led Zeppelin)のような2拍4拍で重いビートを決めるロック演奏が苦手なので、ジャズ流でこなすとシェイクになるのだ。当時は非常にダサいと思ったが、1990年代クラブ音楽を経た現在は、それが新鮮に聴こえるのである。
Led Zeppelinが大好きで、ドラマーでもあった西城秀樹は、洋楽ばかりを聴く家庭環境に育った。だから彼は当時勃興したばかりのLed ZeppelinやDeep Purpleのような本格ハードロックをやりたかったに違いない。しかし1970年代初頭の日本にはロックの名手が何人もいなかった。フラワー・トラべリン・バンドのような、レアな本格的ロックバンドを組まなければそうしたロックはできなかったのだ。アイドルという立場の伴奏ではとても手が出ないサウンドだった。しかし秀樹は負けていなかった。自分の立場で全力を尽くし、観客のために全身全霊で歌った。
もともと1960年代の御三家歌手たち、例えば橋幸夫も「あの娘と僕(スウィム・スウィム・スウィム)」などのマニアックなリズム歌謡で本場ロックンロールに接近しようとしていた。西郷輝彦は、現在ではムーンライダーズが好きなマニアックなロックファンである。彼らだって、どんなにかプレスリーやThe Beatlesのようなリズムで歌いたかったことだろう。しかし日本のスタジオにはジャズメンしかいなかった。そうした歌謡曲に抗うように日本のロックは発進を始めたのだ。
西城秀樹も、橋幸夫など60年代の御三家と同様の出発であった。しかしロバート・プラントの薫陶を受けた秀樹は、比較にならないほどダイナミックな感性を持っていた。ジャズメンのリズムだろうが、ホーンの大編成だろうが、アグレッシブでいながらも正確な歌唱で引っ張って、ロック的な世界を創り出してしまったのだ。その熱は、今こそ映える。コンピュータであらゆるサウンドがシミュレーションできる現在は、その野獣のようなオーラがとても輝いて見える。ロックには豪華で重すぎるオーケストラをバックにしても、ぶっちぎった熱狂を作り出せるのは、秀樹だからこそなのだ。
最後のメドレーで歌われている「ヘイ・ジュテーム」では、感情が入りすぎて最後に倒れてしまったらしい。音源のラストからも、それらしきスタッフの声や、不自然に大きくなった歓声が確認できる。グループサウンズの演出による失神ではなく、本気で全力投球したがゆえの歌唱。ファンが熱狂するのもよくわかる、凄まじいドキュメントである。
『西城秀樹 オン・ステージ』には「質問コーナー」がある。この時代のファン達が熱狂的なあまりほとんど何を言ってるかわからないような質問をするのが面白い。その一つひとつに丁寧にはっきりと歌い答える秀樹。一人が「いつまで歌い続けるんですか?」と問いかけた。秀樹は、その答え通りに「死ぬまで」歌い続けた。
西城秀樹のライブスタイル確立に影響を与えた決定的瞬間

2枚目のライブアルバム『西城秀樹リサイタル/ヒデキ・愛・絶叫!』(1974年)は、1973年11月7日に東京郵便貯金ホールにて開催された、同名の第2回コンサートを2枚組で発売したもの。編曲は、ザ・ワイルド・ワンズ出身のキーボーディスト・渡辺茂樹(チャッピー)が担当しており、ドラムもロック系に進化している。
ジョン・レノンの「ラブ」、Carpentersで大ヒットしていた「イエスタデイ・ワンス・モア」で始まるのは、当時大流行したソフトな「ラブ・サウンズ」といった大人向けのブームを反映している手堅い選曲。その調子は前半いっぱい続くが、後半はラウドに飛ばしていく。「サティスファクション」「ダンス天国」といったジャンプナンバーが眩しく、「恋の約束」「チャンスは一度」「情熱の嵐」など、自身のメドレーの迫力も物凄い。その理由はロック的にドッカリ攻めるドラマーと、鋭角的かつ正確なリズムをカミソリのように細かく繰り出すジャズベーシストが他流試合のように闘うからだ。ロックとジャズの饗宴、この時期ならではのレアなアンサンブル。各ジャンルの畑で固まったアメリカでは見られない演奏だ。日本ならではの事情が生んだリズムの上を戦車のように歌い込むボーカル。秀樹はジャンルレスで渡り合うサウンドの上にも、ロックを実現する稀有なボーカリストだ。
秀樹は1974年2月にロッド・スチュワート&フェイセズの来日公演を観る。これが運命の分かれ目になった。ロッドの素晴らしいステージングに魅了されたのだ。ロッドがライブでマイクスタンドを振り上げる動作が、アルミ製のマイクスタンドによるものだとわかり、それを自分用に作った。そして前座のジョー山中バンドの芳野藤丸(Gt)に惚れ込み、直接バックで弾いてくれるよう説得したのだ。
この後の1974年8月3日、ソロ歌手としては日本で初めてとなるスタジアムでのワンマンコンサート『ヒデキ・イン・スタジアム “真夏の夜のコンサート”』を大阪球場で開催している。以降10年連続、後楽園球場では1978年から4年連続でスタジアムライブを行う。凄まじい数である。秀樹は日本のスタジアムアーティストの草分けなのである。

3枚目のライブアルバム『西城秀樹リサイタル/新しい愛への出発』は、1974年10月20日、東京郵便貯金ホールで行われた第3回コンサート『We Love Hideki '74 西城秀樹リサイタル』の模様が収録された2枚組ライブアルバム。「オープニング」に連なり、孤高のシャンソン歌手で、デヴィッド・ボウイも尊敬するジャック・ブレルのヒット曲「行かないで」を意訳した「泣かないで -IF YOU GO AWAY-」と重々しく始まる。井上陽水の大ヒット曲「夢の中へ」も取り上げて盛り上げるが、The Rolling Stones「悲しみのアンジー」など、情緒的な曲が多い。そうした曲での豊かなムードは秀樹ならではの魅力だろう。
ELO風に編曲された「ロール・オーヴァー・ベートーヴェン」、Kool & The Gang「ファンキー・スタッフ」、そしてマニア好みのグラムロック・バンド Geordie「ジャスト・ライク・ア・ウーマン」と、大変にレアな曲が続くが、こうしたディープな選曲が本当の秀樹の趣味なのかもしれない。
後半は自身のヒット曲メドレーでますますパワーが高まっている。しかし、サウンドは前作の延長線上にあるといっていいだろう。本当のロックへの挑戦は、次作になる。