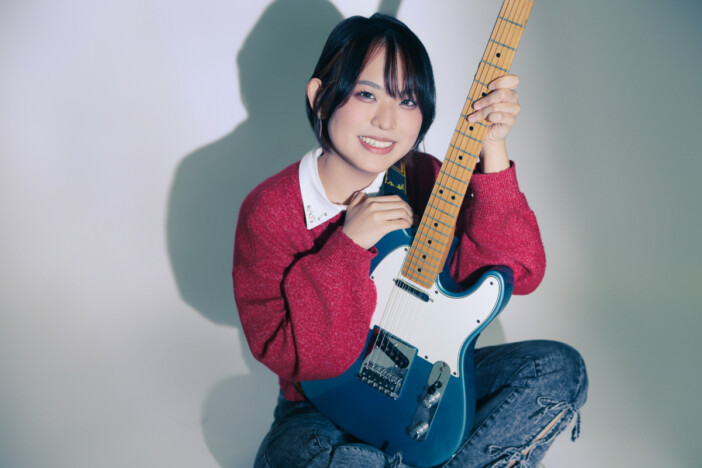稲垣吾郎が“稲垣吾郎”を崩すことで生まれる笑いとは 舞台『プレゼント・ラフター』が高純度のコメディである理由
いやー、笑った笑った。こんなにも声を出して笑えるとは。稲垣吾郎が主演を務める舞台『プレゼント・ラフター』を観劇した。
いよいよ本日開幕!稲垣吾郎主演舞台『 #プレゼント・ラフター 』開幕前会見&公開舞台稽古を実施!https://t.co/62DXk92XXe#新しい地図#atarashiichizu#稲垣吾郎#GoroInagaki pic.twitter.com/eVSik4AYhj
— 新しい地図 (@atarashiichizu) February 6, 2026
私たちのなかにある「稲垣吾郎」が生かされ、そして崩される
パジャマ姿でヘアスタイルが乱れた稲垣が登場するだけで、客席からは「クスクス」と声が漏れる。彼が絶対に選ばなそうなシマウマ柄の派手なガウンを羽織り、気に入ったそぶりを見せるだけで、大笑いが起きる。この笑いは、役とはいえ「あの稲垣吾郎によくやらせた」という賞賛でもあったように感じる。
けたたましく鳴り響く玄関のブザーに慌てて出ようとしながらも、すかさず鏡を覗き込むのを忘れない仕草に爆笑してしまったのも、そう。きっとほかの人が演じていても、面白いのだと思う。でも、“あの”稲垣吾郎が演じているからこそ、余計におかしく感じてしまうというのは否めない。それは、私たちのなかで、積み重なってきた“稲垣吾郎”があるからだ。
自身の美学を徹底した立ち振る舞い。髪型が崩れるような強風のロケはNG。バラエティ的な無茶振りや、段取りの悪い番組進行には、つい“イラチ”な顔を覗かせる。ちょっぴり神経質で浮き世離れしたミステリアスな存在。それが、私たちが見つめてきた“稲垣吾郎”という人だ。
舞台『プレゼント・ラフター』では、そんな私たちのなかにいる“稲垣吾郎”が、巧みに利用されている。「こんな吾郎さんが見られるなんて!」という嬉しい裏切りと発見が、随所に散りばめられているのだ。
それは本人にも自覚があるようで、インタビューでは「稲垣吾郎という鎧がどう崩れるかを楽しんでほしい」(※1)という発言もあったほど。“稲垣吾郎”というイメージが強固であればあるほど、この舞台の笑いの装置が迷うことなく発動する。
逆を言えば、これほど私たちが期待する“稲垣吾郎”であり続けてきたこと。そしてそんな自身を“素材”として舞台に提供するという、稲垣のエンターテイナーとしての真髄を感じさせる作品にもなっていると思った。
稲垣が引き受ける、弱さや愚かさへの「許し」
『プレゼント・ラフター』は、マルチアーティストのノエル・カワードが1939年に描いたラブコメディ。当時のスター俳優は“マチネアイドル”と呼ばれルックスの魅力で人気を博していた……と聞くと、現代の“アイドル”の印象ともまさに重なる。
稲垣が演じたスター俳優のギャリーもまさにそのひとり。だが、現代も“アイドル”といえば若くフレッシュなイメージが先行するように、ギャリーも年を重ねていくこと、自身が出演する作品への葛藤を抱えていた。これが90年近くも前の作品かと驚かされる設定ではないだろうか。それほど、時代を超えて“スター”や“アイドル”が抱える悩みは変わらないのかもしれない。
人気稼業ゆえに誰にでも“いい顔”をしてしまうギャリー。それを「演じている」「本当の顔を見せて」と指摘されても、もはや何が本当の自分なのかわからないというのが本音だ。それでも、彼を求める声は絶えない。それぞれが好き勝手にギャリーを求め、その声につい応じてしまう。だが消えることのない孤独感に、ギャリーは「陰謀論だ」「落ちる」と、まるで10代の青年のように衝動的に怒ったり繊細に沈んだりと大忙し。
そんな振り回されっぱなしのギャリーこと稲垣が、実に愛しいのだ。「あなたって、ときどきすごく若く見える」と劇中のセリフにもあったが、世間がアイドルに求めるものは身勝手なものだ。少年のままでいてほしいという反面、大人としての振る舞いも期待される。大衆が向ける勝手な期待や失望に稲垣もこんなふうに人知れず翻弄されてきたのだろうか、もちろん、ギャリーほどそれを表面に出していたかは、わからないけれど。つい、そんな想像の余地をゆるしてくれるところも、また“稲垣吾郎”というスター俳優のなせる技。
ちなみに、本作の稽古中には元妻・リズ役の倉科カナに聞かれて、初めてMBTIにトライしたという稲垣。ラジオ『THE TRAD』(TOKYO FM)では「答えるときに、嘘つかないで、悪めに答えた」という気になる結果は“擁護者”(ISFJ)だったと明かしていた。だが、その内容を倉科に伝えたところ「『あ、そうなんですか』で終わりました。聞いといて」というあっさりした対応だったと囲み取材で語り、笑いを誘っていた。そんな肩透かしに合っているところも、ギャリーさながら稲垣のかわいらしさを感じさせる一幕だった。
本舞台はいわば、稲垣の“あったかもしれない”もうひとつの世界を覗き見しているような気持ちになる作品だ。無論、稲垣のプライベートがこんなにも“困った人”だとは思いたくない。でも、そうなっていてもおかしくない。そんな絶妙なリアルと想像のあいだにあるフィクションだからこそ、説得力のある笑いを生む。
『プレゼント・ラフター』というタイトルには、“今この瞬間の笑い”という意味があるという。この作品が初演を迎えたのは、第二次世界大戦の戦時下だった。時代的にも、この舞台がいかに挑戦的な作品だったかを想像する。一方で、現代の日本はどうだろうか。年々、さまざまな視点から“笑い”が難しくなっている印象もある。
笑えることは、信頼だ。弱さや愚かさに対する共通の“許し”があってこそ成立する。その“許し”が自然と観客の側から差し出されるのは、そこに立っているのが稲垣吾郎だからだ。長年かけて築き上げられたスターのイメージ。崩れてもなお崩れ切らない品格。そして、どこか放っておけない孤独。そうした積み重ねのすべてがあるからこそ、この舞台の笑いは濁らない。安易でも、過剰でもない。『プレゼント・ラフター』は、稲垣吾郎がいるからこそ成立する、驚くほど純度の高いコメディなのである。
※1:https://realsound.jp/movie/2025/12/post-2256178_2.html
稲垣吾郎が語るSMAPと90年代音楽シーン 「“はだかの王様”だったんで、僕ら」――『THE TRAD』で回顧するあの時代
稲垣吾郎がMCを務める音楽ラジオ番組『THE TRAD』にミラッキが出演し、“最高位2位の名曲”をテーマにトークを繰り広げた。
稲垣吾郎&草彅剛&香取慎吾、あえて地下へと潜っていく選択肢 『ななにー』100回目放送で証明するスターの力
稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』(ABEMA)が、12月28日の放送で100回という節目を…