中国版“プデュ”新シリーズ『青春有你2』、人気上昇中の理由 BLACKPINK LISAらの参加など、4つのポイントから解説
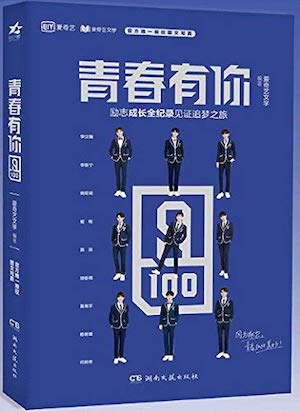
2016年に韓国で放送され社会現象を起こしたオーディション番組『PRODUCE 101』(以下、プデュ)。日本でも昨年末に『PRODUCE 101 JAPAN』が放送され反響を呼んだが、中国でも2018年頃から“プデュ”のフォーマットを踏襲した番組が数多く制作され、人気を博している。なかでも今年3月から中国三大動画配信サイトの一つ、iQIYI(愛奇芸)で毎週木・土曜の日本時間21時から配信中のガールズオーディション番組『青春有你2(Youth With You 2)』は、英語、韓国語、タイ語など多言語字幕付きで配信され、日本でも注目度が高まっている。
同番組は2018年に『偶像練習生(Idol Producer)』というタイトルでスタートし、中国のアイドル史に残る国民的ボーイズグループ・NINE PERCENTを輩出(現在は解散)。2019年の2ndシーズンで『青春有你(Youth With You)』に改名し、最新シーズンにあたる『青春有你2』はiQIYIとしてはシリーズ3作目にして初の女子版となる。デビュー候補の練習生は中国内外から選抜された109人。4カ月間の合宿生活を通してトレーニングを積み、視聴者投票により9人のメンバーを決定する。
見どころPOINT 1:番組をリードする豪華トレーナー陣の魅力
“中国版プデュ”と呼ばれる番組に共通する大きな見どころの一つに、練習生を指導する講師陣の豪華さが挙げられるだろう。特に『青春有你2』は、BLACKPINKのLISAがダンス講師として出演し、『偶像練習生』が生んだ中国のトップスター・蔡徐坤(ツァイ・シュークン)が“青春制作人代表”としてメインMCを務める。練習生にとって憧れのロールモデルであると同時に一番の理解者でもある二人の存在感は絶大で、テクニック面では一人ひとり細部にいたるまで厳しく指導ながらレベルアップに貢献し、悩みを抱えている者がいれば自らの経験をシェアしてそっと寄り添う。長い下積み期間と熾烈なデビュー争いをくぐりぬけ、重圧と戦いながら今現在トップに立っている二人のアドバイスは、何よりも説得力があり、心を揺さぶられる。また、練習生を評価する際のシャープな洞察力もすばらしく、ともするとメンターが“推し”になってしまいそうなほど魅力的なのだ。
見どころPOINT 2:“X”というコンセプトが伝えるメッセージ
『青春有你2』のキーワードは、“X”=「未知数」「無限大」だ。同番組は「女性を定義せず、ガールズグループを定義しない」とし、視聴者に「“X”に対する限りない想像を広げ、2020年を代表するグループを選んでください」と語りかける。
練習生も、アイドルデビューを目指してトレーニングを積んできた者はもちろん、アフロヘアーのボーカリスト・张鈺(チャン・ユエ)、ムーラン似で話題の寡黙な“チャイナガール”陈珏(チェン・ジュエ)、SNSで1000万フォロワーを誇るインフルエンサー・林小宅(リン・シャオザイ)、マイクを握れば名言が飛び出す圧倒的ディーバ感・上官喜爱(シャングァン・シーアイ)……というように、さまざまなバックグラウンドを持つ個性豊かな面々が集まっている。
番組内ではしばしば「女性らしくない」「スタイルがよくない」「若くない」など、いわゆる大衆が求める“女子アイドル像”にふさわしくないとレッテルを貼られてきた女性たちがフォーカスされ、彼女たちが「あるべき論」を覆していく様子を通して、多様性の尊重や自己肯定感を高めるメッセージが発信されている。
そして、そのコンセプトが最も象徴的に現れているのが主題歌「YES! OK!」のパフォーマンスだ。センターを務める刘雨昕(リュウ・ユーシン/XIN Liu)は、スカートではなくショートパンツを履いて生き生きと踊ってみせる。もちろん、これまでも中性的なメンバーを有するガールズグループは多数存在したが、“プデュ”系のオーディション番組で制服ルックにパンツという選択肢があること自体も斬新で、過去に中国のオーディション番組を見たことがない層にまで番組の存在が知られるきっかけになった。
「YES! OK!」は曲名からも伝わってくるように、ありのままの自分を肯定するポジティブなメッセージが全面に押し出されている点もこれまでのシリーズと一線を画している。もちろん、お決まりの「Pick Me」というキーフレーズは入ってくるが、続く言葉は「和我一起吧(Come with me)」。「僕をトップに連れてって」でも「君は今日から私のもの」でもなく、誰の手をとるのかを相手に委ねたうえで「一緒に行こう」といざなう。また、毎回の順位発表式の後も「国民プロデューサー様、よろしくお願いします」と頭を下げる代わりに、「和我一起吧」と手を差し伸べ、ともに未来を描く“仲間”に語りかけるようなスタンスを一貫しているのが興味深い。























