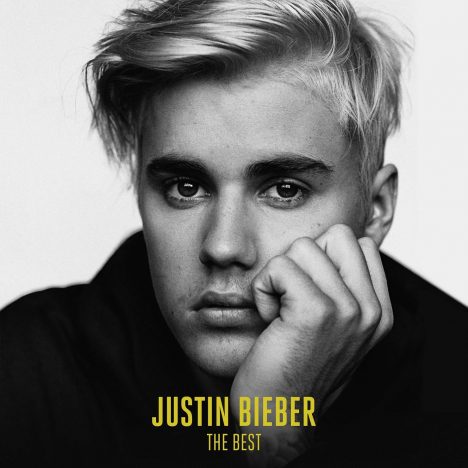ポール・ドレイパー、Mansun時代の苦悩とソロ活動の喜び「“音楽”という大きな流れの中にいたい」

個人のアーティストとして自分らしく活動をしていくだけ

ーー2003年からソロ活動を始めて、ようやく『EP ONE』という作品になったのが2016年。一時はこのままプロデューサーになってしまうのでは? と思っていました。あなたは元々裏方志向とのことですが、昨夜のような楽しい時間が持てるのであれば、人前でパフォーマンスするのもなかなか良いものでしょう?
PD:ああ、僕は元々Mansunの作品をプロデュースしていたけど、Mansunの終わり頃にはThe StrokesやThe White Stripesのような新しいバンドが出てくるようになったんで、心がざわつくようになったというか……そもそも自分はスタジオの仕事をやってた人間なので表舞台にいることがしっくりこなくて、裏方に引っ込んでいったんだ。それでウエスト・ロンドンにスタジオを作って、その流れでThe Joy FormidableというウェールズのバンドやSkin(Skunk Anansie)の作品をプロデュースしたら、そうした作品がベストプログレアルバムとかベストウェルシュアルバムに選ばれたりして『サンデー・タイムズ』や『オブザーバー』で評価されて、結果的に、そこで僕の名前がまた表舞台に上がってきたんだ。それら一連のことがソロ活動をする後押しになったと思う。
実は2ndソロアルバムも4分の3ほどできているんだ。この後、中国をツアーするんだけど、帰ったらあと3カ月くらいで完成するんじゃないかな。今は他の人のプロデュース仕事は入っていないので、しばらくはソロに集中してやっていくつもりだよ。
ーーかつてのあなたは音楽界全体を見渡して、それに対してどのような創作を行なって行くべきか、ということを考えていたと思うのですが、今はどうでしょう?
PD:今の音楽業界は、僕のようなアーティストにとってはかえっていいんじゃないかな。なぜなら、自分だけの世界の中で活動していくことが可能だから。かなりの数の人が僕のSNSをフォローしてくれていて、僕は自分のやり方でファンと直接交流している。今は必ずしもレコード店で作品を売る必要がないしね。
ソーシャルメディアのチームには、Facebookを運営してもらってる。ファンからのメッセージが毎日来るから、それに返信することを心がけているよ。インスタはポール・ドレイパー個人のものの他に、Mansunのアカウントもある。『SIX』がリイシューされることもあって、今でもMansunの動向を追い続けているファンが大勢いるから、そちらにも情報を出しつつ……という具合に、今はアーティストが自分だけの世界の中で十分活動できる状況がある。それが昔との最大の違いだよね。もうポップチャートに上がる必要はない。ただ、個人のアーティストとして自分らしく活動をしていくだけだ。実際、僕はソロでもアメリカ、フランス、ベルギー、日本、中国をツアーしてるわけで、次のセカンドでは香港や台湾、ヨーロッパの他の国も回ったりできればと思ってる。マンサン時代からのファンと改めて繋がると同時に、新しいファンの掘り起こしもしているけど、それが大きなメディアに出なくてもできるというところが昔とは違うんだ。
ーーそれでは、今は何かと闘ったり、もがいたりしている感覚はないですか?
PD:ないね。若い頃は怒りに満ちていたけど、いつまでもそうだったらおかしいだろ。今はマイルドにハッピーだよ(笑)。1995年にツアーを始めて、もう24年こういう生活をし続けることができている。そのこと自体がラッキーだって実感しているから。怒りに燃えることで惨めになるのではなく、感謝することを覚え始めたんだ。
ーー感謝といえば『Spooky Action』のCDのクレジットには、ものすごくたくさんの名前が連なっていますね。
PD:ああ、そういうのも昔はやってなかったね。
ーー中には「敵たちへ。君たちを赦すよ。愛が答えだ」と書いてあって驚きました。やはり紆余曲折あったことで、何かを悟った感覚はありますか?
PD:あれは前のバンドのメンバーと、一部の業界人のことを指しているんだ。昔のことは、過ぎたこととして受け止めているし、全てが思い通りにはいかないまでも、今、自分は音楽をやって生きていくという希望を叶えている。それだけでもありがたいことなんだ。例えばゆうべのように素晴らしいコンサートができた時は、心から幸せを感じる。そういうことがあると、これまでの道のりは無駄ではなかった、やってきた価値があったな、と思えるんだよ。
ーーそうですか。でも長年のファンとしては、あなたの音楽はまだまだ正当な評価を受けていないという気持ちもあるんですよ。昔から時代に早すぎたり、マニアックだったりと、一般的にはとかく「不遇」というイメージがあるんですが、自分ではその辺り、どう思っていますか?
PD:うん、そうかもね。ただ「時代に早過ぎた」って自分で言うのは生意気だから「時代に合ってなかった」と言おう(笑)。ただ、今またMansunが受け入れられる時代になってきたのかもしれないとは感じているよ。『Attack of the Grey Lantern』を再発したらUKチャートに入ったし、ラジオでもいまだにかけてもらえる。『SIX』もリイシューされて評価を得ているしね。
ーーええ、実際、ゆうべのライブにも若い人、沢山来てましたよね。
PD:(嬉しそうに)そうなんだよ! 僕のソロからかつてのバンドを知った人もいるだろうし、バンド時代からファンでいてくれてる人もいるだろう。そんな風に新旧のファンがミックスされてるのはとてもいいことだよ。自分でも若いファンが多いのに驚いたけどね(笑)。
ーーこれは答えるのが難しいかもしれませんけど、バンドが長く続いていくには何が必要なんだと思いますか? Mansunが続けていけなくなった一方で、The Rolling Stonesみたいに長寿のバンドもいるでしょう?
PD:バンドを保てなかった僕がそれに答えていいのかな(笑)。
ーーだからこそ、あなたが実感したことを聞きたいんですよ(笑)。
PD:そうだな。まず基本、友達同士であるに越したことはない。Mansunは友達じゃなかった……と言うつもりはないけど、『バンドをやろう』という呼びかけのもとに集まった人間のグループだったんだ。まずバンドありきだったから、成功し始めるとパワーバランスがおかしくなってきてしまい、そこに金の問題も絡んできたりしてダメになっていった。問題が起こったところでメンバー同士が話し合いの時間をもって解決しようとすればよかったのかもしれない。でも、僕は嫌気がさしてしまって、それで4作目の途中で脱退してアメリカに渡ったんだ。幕引きをきれいにできなかったことに後悔はあるよ。
結局、バンドをうまく回すのは、いいマネージメントなのかもしれない。良き友達と良きマネージャー、もしくは友達じゃなくても人として相性がよければうまくいくんじゃないかな。
ーー以前「マンサンの再結成はThe Beatlesよりも難しい」と話していましたね。元メンバーとも会っていないそうですが、あなたの中にMansunというバンドに対する未練は全くないのでしょうか? 実際、4作目が未完成ですけど、他にやり残したなと思うことはありますか?
PD:そうだね。Mansunは過去のものだ。ただ、作品は別で、今でも直したいと思うところが結構あるので、その作業もしているよ。一連のリイシューが終わったら未完のままの4作目を完成させようと思っているし。『Kleptomania』に入ってるデモを、適切な形で仕上げるんだ。あと、気に入ってない『Little Kix』も、もう一度自分の手でプロデュースし直したい。あの時は外部のプロデューサーに頼む形になってしまって不本意な部分がたくさんあるから、自分のプロダクションで完成させたいんだ。それから、ライブの映像も撮ってあるから、フルコンサートの映像を映画館で特別上映みたいな形で上映しようとも思ってる。デモ音源もまだたくさんあるし、EPやアルバムのヴァイナル、本……出すものはたくさんあるから、向こう10年かけて少しずつ出していくよ。そうしたアーカイブを作ることで、Mansunを正しい形で知ってもらいたいと思うんだ。
ーーこれからまだまだリリースは続くんですね。その制作のモチベーションというのはどこからくるのですか?
PD:金じゃないことは間違いないね。なぜなら金になってないから(笑)。「自分の中でうごめいている何か」としか言いようがない。振り返ってみれば僕は、ポップスターだった時期があって、そこから裏方になって、ソロアルバムを作ってソロで活動するようになって……状況は変わるけれども、この『音楽』という大きな流れの中には常にいたいな、と思っているんだ。純粋に楽しんでいるという意味では、職業というより趣味と言ってもいいかもしれないね。
ーー最後に、4分の3はできているという2作目のソロについて聞かせてください。
PD:次のアルバムはもう少しヘヴィなロック寄りのアルバムだよ。今、イギリスではポストロック的なものが主流になっているんだけど、僕は90年代風のシンセサイザーを使ったロック、そういうテイストのものが20年経っても好きなんだよね。それが僕らしさってことなんだと思う。Facebookをやっている人は「Paul Draper Appreciation Society」っていうファングループを見てもらえば、新しいアルバムに収録される曲がいくつか聴けるよ。さらにダークでヘヴィなサウンドになってるのがわかると思う。
ーーそれを聴く日が待ちきれないです。それからフルバンドでの再来日も。
PD:ああ、僕自身も楽しみだよ。また会おう。
(取材・文=美馬亜貴子/通訳=染谷和美)