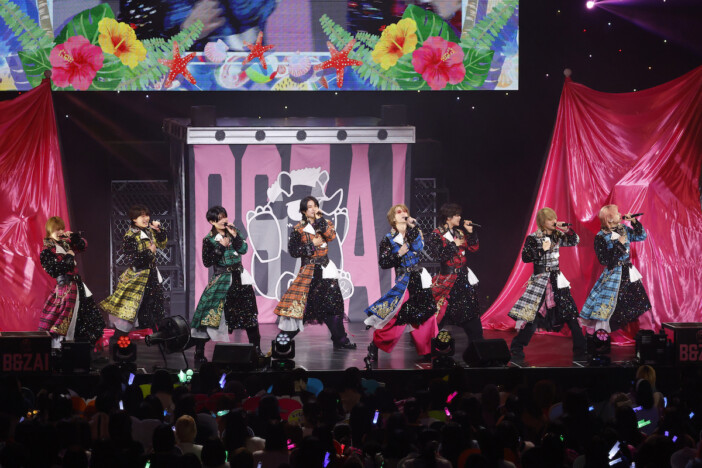星野源は、“普通の化物”だーー様々な経験がもたらした表現者としての武器
先に触れた通り、『YELLOW DANCER』は方向性がブラック・ミュージック寄りになったアルバムだった。ただ、ファルセットを使う場面もあるとはいえ、ボーカルはブラック・ミュージック的なかっこよさを追求したものではなかった。星野はブラック・ミュージック的な踊れるリズムを志向すると同時に、日本で生まれ育った自分が自然に吸収してきた歌謡曲〜J-POP的なメロディ主体の曲調を融合しようとした。その結果、エゴやナルシシズムを遠ざけた詞とキャッチーで歌いたくなるメロディ、体が反応しやすいアレンジからできた、星野がいうところのイエロー・ミュージックができあがった。同アルバムの後に発表された「恋」もその路線で作られている。
インストゥルメンタル・バンドのSAKEROCKをやっていた星野に、歌うことをすすめたのが細野晴臣だったのは知られている(その話題も『いのちの車窓から』に登場する)。細野が組んだイエロー・マジック・オーケストラには、外国人によって誤解された日本人像を意図的に演じ、遊んでいた部分があった。細野のイエローは、戦略的で批評的だったのだ。だが、細野とは違って星野のイエローは、ブラック・ミュージックも好きだが歌謡曲〜J-POPも好きな普通の日本人としての感覚をニュートラルに表現したもの。そういう姿勢によって間口の広いポップスになったのだ。
辛い体験を経て、様々な要素を折りたたんだ形で星野源の普通はできあがっている。その普通さが、ミュージシャン、俳優、文筆家に化けるための武器となっている。星野源は、普通の化物だ。
■円堂都司昭
文芸・音楽評論家。著書に『エンタメ小説進化論』(講談社)、『ディズニーの隣の風景』(原書房)、『ソーシャル化する音楽』(青土社)など。