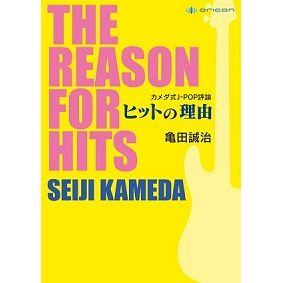『Music Factory Tokyo』スペシャルインタビュー
「PASSPO☆で書いている歌詞の原点は中ノ森BAND」 阿久津健太郎が語る“女性目線の作詞法”

「女性の歌詞を書くときは『視点をひっくり返す』ことを意識する」
――プレイヤーやコンポーザー、プロデュース業を並行するなかで、培ったものはなんですか。
阿久津:HAVは、最初のころにアレンジも全部自分でやろうとしていたのですが、それが原因でメンバーと衝突したりして。ZEROの時と同じになりそうだったので、自分を柔軟にするようにして、アイデアを出し合う感覚でバンドを続けることができました。中ノ森BANDでは、作家として女性アーティストへの歌詞の書き方が身に付きました。現在PASSPO☆で書いている歌詞の原点は中ノ森BANDにあって、ガールズロックの詩を真剣に書き始めたのがこの時期です。おそらく、この2グループを両方とも聴いている人はなかなかいないでしょうが、もし中ノ森BANDを知っている人がPASSPO☆を聴けば、両グループの歌詞が繋がっていることを感じて貰えると思います。
――女性目線の歌詞を書くにあたって、どのようなインプットをしましたか。
阿久津:恋愛経験や、女友達から相談に乗るなかで、女の子の意見をしっかり聞くようにしました。日常生活でも「こういうとき、女の子ならどう考える?」というのを意識するようになって、たとえば自分が経験した恋愛でも、その時の反省点を相手側の立場から書くなどしていました。「視点をひっくり返す」ということをすごく意識しましたね。そうすることで自分の書く歌詞も、抽象的なものからより具体的で身近なものへと変化していきました。
――ZERO解散からHAV結成まで、様々なジャンルを通り、中ノ森BANDでは女性目線の歌詞を学んだと。そしてHAVは2005年に解散し、以降は作家としての活動が続きます。
阿久津:自分は我が強かったのだと思います。自分はこうしたい、こうあるべき、というモチベーションも押し付けていたし、もっとこうしなきゃダメだろ、みたいなことも毎日、喧嘩のように繰り返していたし。いま振り返ると、ZEROの時の妹にしても、HAVの時のバンドにしても、自分の我が強かった。そうした経験を通じて、自分はバンド向きじゃないと気付きました。

――では、どんな適正があると思ったのでしょうか。
阿久津:「一人ですべてをつくるタイプのプロデューサー」ですね。プロデューサーにも、自分の曲をスタジオに持って行って、色んなミュージシャン・プレイヤーとセッションしてアレンジを組み上げていくタイプと、最初からアレンジの構想ができていてそのまま完成させるタイプがいて、自分は後者でした。
――なるほど。具体的なフローはどのような感じですか。
阿久津:最初の頃はひとつずつ、ギターのフレーズやドラムのトラックを重ねて作っていましたが、色んなDAWを使うなかでPro Toolsに出会ったことで、こだわりが強くなり、1曲のデモに時間がかかるようになった。そのうちに、はじめから完成形をイメージして、一気に打ち込んでいくというフローになりました。
――頭にイメージしたものを短時間でつくりあげていくということですね。
阿久津:ひとつひとつの音を考えながら打ち込んでいると、途中で変えるのも昔と違って面倒になってきたので、打ち込む音をイメージしてから作業するという形に変わったんです。もちろんそれは締め切りなどの時間的な問題もあり、そうしないと間に合わないという環境だからこそ身についたものでもあります。
――かなり難易度の高い方法に思えます。1日で50曲を作るなど、アイデアを出すのは早いタイプなのでは。
阿久津:そうですかね……(笑)。でも、それはやはり経験だと思います。事務所の社長には「駄作でもなんでも良いから、とにかくたくさん作れ」ということを言われていましたし、1曲では使えない作品も、1フレーズや1セクションなら後々使い回しができることもあります。そういう意味で、デモを大量に作ったことは、財産になっていると思います。
――HAV活動停止からプロデューサーとしてPASSPO☆に行き着くまでに得たものはありましたか。
阿久津:当時の事務所は自前のタレントに曲を提供することができたりして、フリーの作家がコンペに出すよりは良い環境で仕事をさせていただきました。でも、もっと多くのアーティストに対して自分の実力を試したかったのと、最後までアーティストとして活動することを僕に勧めてくださっていた社長の期待に100%応えられなかったのが申し訳なかった、ということもあります。そこから縁あって、+Plusの音楽プロデュースからマネジメントまですべて手がけることになりました。その話を受けて、初めてマネージャー業務もやりましたし、イベントのブッキングでは、知っているライブハウスに片っ端から電話をかけたり、プロモーションからホームページ更新からファンクラブ運営までやっていました。そこで、アーティストとして当たり前にあったホームページやライブが、こうやって組んでいかないと動かないのだと分かり、考え方も大きく変わりました。
――その考え方は制作物にも影響しましたか。
阿久津:いままでは、自分の作ったものがリリースされても、そこまで興味が沸かなかったし、ライブで演奏されることに対しても無自覚でしたが、バンドのマネジメントをするようになり、ライブでリリースより先に曲を披露したり、そこでファンの方のリアクションを受けたりすることで考え方が変わりました。ちょうどそのタイミングでPASSPO☆の楽曲プロデュース依頼も来て、彼女たちも毎週末のようにイベントへ出演するようなグループだったので、ライブ主体の曲作りになっていったように思います。昔はもっとマニアックで、メロやコードにとにかくこだわっていて、「このコードの展開は誰もやっていないだろう」とか「とりあえずテンションコード使っておこう」といった作り方でした。でも、ライブ主体の作り方になって、「逆にシンプルなものがいいんだ」という感覚に変わっていきましたし、初見の方が多い対バンイベントやアイドルイベントにおいて、どれだけ一体感を作れて、引き込めるかを考えるようになったんです。
――PASSPO☆のクレジットを見ていると、初期ではほかの作家さんとの分業もしていますね。
阿久津:それは前の事務所にいた頃で、制作チームで曲を作っているなかに、アレンジャーやマニピュレーターが常に一人いたので、アレンジを最終まで仕上げるということはありませんでした。自分で作るアレンジは「こういう感じで、ここだけは変えないで欲しくて、後は肉付けをお願いします」という要件を伝えるためのデモのようなもので。だからわりと曲だけ、詞だけという仕事が多かったんです。一人になってからは、全部自分で完成させなくてはいけないという状況が増えましたが、かといってクオリティに変化はないと思います。事務所に所属していた頃から、完成品レベルのデモは作っていたので。
後編【「平均点が上がってからのデモは財産」 阿久津健太郎が明かすPASSPO☆新作制作秘話と作家としての矜持】へ続く