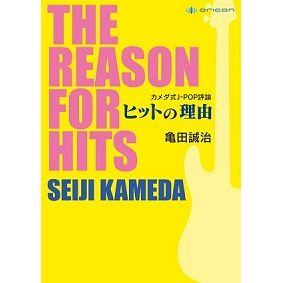『Music Factory Tokyo』スペシャルインタビュー
「PASSPO☆で書いている歌詞の原点は中ノ森BAND」 阿久津健太郎が語る“女性目線の作詞法”

音楽を創る全ての人を応援したいという思いから生まれた、音楽作家・クリエイターのための音楽総合プラットフォーム『Music Factory Tokyo』が、現在“ペンネとアラビアータ”名義でPASSPO☆のトータルサウンドプロデュースを手掛ける阿久津健太郎氏のインタビュー記事を公開した。
同サイトは、ニュースやインタビュー、コラムなどを配信し、知識や技術を広げる一助をするほか、クリエイター同士の交流の場を提供したり、セミナーやイベント、ライブの開催など様々なプロジェクトを提案して、未来のクリエイターたちをバックアップする目的で作られたもの。コンテンツの編集には、リアルサウンド編集部のある株式会社blueprintが携わっている。リアルサウンドでは、今回公開されたインタビューの前編を掲載。同記事では、作家としてこれまでも中ノ森BAND、w-inds.、Folder5、MAXなどの楽曲に携わり、過去に自身も歌手としてデビューし、ヒット曲を生み出した経験を持つ同氏の波乱万丈の半生や、豊富な経験のなかで得たプロデュース・作家論について、じっくり話を訊いた。
「プロデューサー志向が強すぎて、気付かぬうちに妹を追い込んでしまった」
――阿久津さんはご両親も音楽活動をしていたそうですが、ご自身はどのようにして音楽に目覚めたのでしょうか。
阿久津健太郎(以下、阿久津):両親ともに音楽家だったので、家には幼少期からアコースティックギターがありました。僕はそれを子供の頃から遊びで弾いていたのですが、中学生の頃には世間でバンドブームが起こり、同世代で楽器をやっているのは当たり前のような雰囲気になりましたね。当時のロック少年たちはガンズ・アンド・ローゼズやBOOWYなどを聴いていたのですが、僕はジャーニーやボン・ジョヴィが好きで、エレキギターを買って、彼らのイントロをフレーズ弾きしていました。だから周囲の友達とは全然話が合わなくて(笑)。彼らは当時、アイドル的な扱いをされていたので、ロック好きからすると仕方ないのかもしれませんが、僕は曲がすごく好きでハマっていたんです。そこがやはり、曲作りのベーシックになっているのだと思います。
――本格的に楽器を演奏するようになったのはいつからですか。
阿久津:高校生になって、芸能プロダクションに所属してからです。中学生のときに、うちの親が賞金目当てで、雑誌『JUNON BOY』に応募をしていて(笑)。審査に通ったところで「受かっているよ」と応募していたことを教えられて、そのまま運良く最終審査まで残り、芸能プロダクションに入ることになりました。どんな活動をしていくのか決める際、事務所のスタッフには「歌を歌いたい」と伝えましたが、社長に「お前は歌だけでは無理だろう。でも、シンガーソングライターならいいんじゃないか」と言われたんです。それまで作曲はしていなかったのですが、この出来事を機に「つくる」ことを始めようと思い、YAMAHAのQY10を買いました。
――自分で「つくる」と思い立って、ギター一本ではなく打ち込み機材を買うあたりが、現在の活動に繋がっていそうです。
阿久津:たしかに、バンドから始めるという人が多いですよね。でも僕は、シンガーソングライターとして、ひたすら曲を作る必要がありました。TASCAMの8トラックカセットレコーダーを使ってたくさん曲を録音して、社長に聴かせていましたね。今より作り込みが甘かったこともあり、一日に何曲も作っていました。それと、当時は役者もやっていたのですが、自分にはとても難しくて……(笑)。「台詞が入ってくるタイミングがおかしい」などと怒られたりして、「人のテンポに合わせるのは難しいな」と感じていました。

――その当時は何曲くらい作っていましたか?
阿久津:1年間で、200~300曲作りましたが、いま聴くと本当にヒドいです(笑)。ずっと同じ音符を繰り返したりして。でも、当時はすごく良く出来ていると思っていたんですよね。社長も「ヒドい」と言わずに「おう、がんばれよ」と聴き続けてくれて。それを1年間くらい続けていたある日、「お、これ良いんじゃないか?」と言ってもらい、その曲をきっかけにソロデビューしました。全然売れなかったのですが、当時は織田哲郎さんや小室哲哉さんといった「J-POPプロデューサー・コンポーザー」が時代を牽引していたこともあり、自分もそういう風になりたいという気持ちを募らせるようになりました。
――そこから自身がプロデューサー・コンポーザー的な役割をしていたZEROが生まれたのですね。
阿久津:ある日、社長から呼び出されたので「売れなかったからクビかな」と思ったんですけど、「お前の妹、いい声してるな」っていきなり言われて。どうやら妹が自分の知らないところで、勝手にデモテープを社長に送っていたらしいんです。その時、カーペンターズがドラマ主題歌に起用されて再評価されていたので、社長も「兄と妹で和製カーペンターズだ」とノリノリで。妹とはこの時、一緒に住んでいたのですが、おたがいに思春期でほとんど会話もなく、抵抗もあったので「嫌です」と断りました。ただ、社長が引き下がらなかったので「じゃあ、企画物ならいいですよ」と偉そうに言ってしまいました。そこで、「CMソングのタイアップ曲を作ってみないか」という話を頂いて、一日で50曲作って持っていきました。そこから選んでもらったのが「ゼロから歩き出そう」という曲で、CMを通じて大きな反響をいただいたこともあり、ZEROというユニットを組んでCDをリリースしました。
――同シングルは約30万枚という大ヒット作になりました。しかし、ユニットしての活動は3年ほどで終わっています。
阿久津:自分のプロデューサー志向が強すぎて、気付かぬうちに妹を追い込んでしまったのだと思います。そこからは事務所に「クリエイターとしてやっていきたい」と話して、所属アーティストのコンペに参加させてもらうようになりました。でも、まったく曲が通らなくて。100~200曲書いても採用されない期間が2年ほど続いたこともありました。その時はもともとRPGゲームが好きだったこともあり、『ファイナルファンタジーXI』にハマってしまいまして……。その世界の中でどんどん強くなっていって、スタッフの中で「健ちゃん最近見かけないね」「いや、元気でやってるよ。ヴァナ・ディール(ゲーム内の世界)に行くと、ナイトの格好でチョコボに乗ってケアル(回復魔法)をかけてくれるし」なんていうやりとりがあったくらい(笑)。
――ネットゲームはハマると大変そうですね(笑)。その後、バンド結成までにはどのような経緯がありましたか。
阿久津:もちろん音楽をまったくしていなかったわけではないので、楽曲が決まらない焦りから、色んなジャンルの楽曲を聴き、様々なデモを作るようになりました。このタイミングでヒップホップやミクスチャーバンドを聴くようになり、ミクスチャーロックバンド・HAVのメンバーになりました。この時はバンドと並行して作家活動も行っていて、MAX、Folder5、w-inds.、FLAMEといったダンスものを得意とするアーティストに楽曲を提供していましたが、「ロックをやりたい」という気持ちが強く、当時結成されたばかりの中ノ森BANDを手がけることになりました。