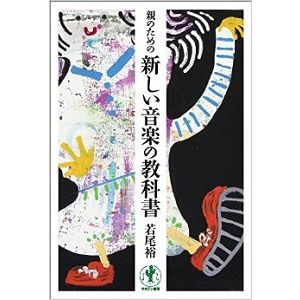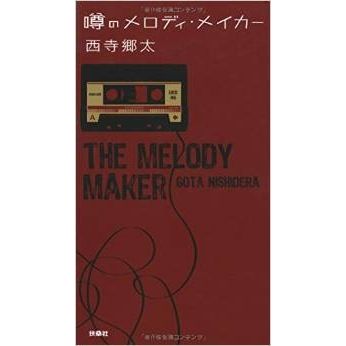栗原裕一郎の音楽本レビュー 第7回:『人を振り向かせるプロデュースの力 クリエイター集団アゲハスプリングスの社外秘マニュアル』
プロデューサー集団・アゲハスプリングスの新しさとは何か? その「社外秘マニュアル」を読む
プロデュースワークそのものを買っていただく
玉井のいうブランディングは、逆説的に聞こえるかもしれないが、大先生である作詞家や作曲家、有名プロデューサーといったブランドに頼れば済んでいた時代が去ってしまった現在において、音楽を届けるため採られるべき方策といった意味合いで用いられている。アゲハスプリングスが、90年代のプロデューサーのようにはわかりやすくない理由の一端はそこにもある。
一口に音楽プロデューサーといっても、時代ごとに役割や立場は変化してきた。ざっくり整理すると、80年代までは主にレコード会社やプロダクションの社員が裏方としてプロデューサーを務めることが多かったのが、90年代になると、作曲編曲ときには作詞もやるミュージシャンがプロデューサーとして台頭、表舞台に立つようになり、以後多様化して、現在では、ボカロソフトを使ってDTMをする人たちまでプロデューサーと呼ばれるようになった。
アゲハスプリングスの志向しているのは明らかに裏方であり、玉井は「いまプロデュースという責任を負った人間に必要なスキルが、まさに90年代以前のプロデューサーのそれに近づいているのではないか」という。
だが、テクノロジーが発達し、メディアが多様化して、音楽を作るという行為や意味が変容した現在で、90年代以前のプロデューススタイルを踏襲するなんて時代錯誤なのではないか。
いや、そうではないと玉井はいうのだ。
DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)以降、誰でも作編曲できるようになった結果、個々の曲の作者が誰かということはあまり注意されなくなったし、著名アイドルの作家に聞いたこともない人がいきなりクレジットされているといった事態も増えた。
作家性が楽曲の質や魅力を担保することが薄れ、良い曲であることなんて前提に過ぎなくなった状況が出てきた現在だからこそ、求められるプロデューサー像が90年代以前のものに近づいたのだというのが玉井の論理である。
「“目の前にいるアーティストが成功するか否か?”“そのアーティストと出会った人達が新しい価値を見つけられるかどうか”、そこだけに全力を注ぎ込む、すなわち必要なすべてのリソースを着実に揃え、それらを成功へと導くべくコンバインするという責任を負い、さらには、その役目だけに特化した立ち位置で、それだけを見据えている存在」「プロジェクト全体の成功率を高め得る知識やノウハウという、目に見えづらい能力を問われる存在」
ここで「リソース」と呼ばれているものは、詞、曲、アレンジからレコーディングまで、商品としての音楽を構成する要素すべてのことだ。それらを単なる和を超えるレベルで、それも受け手に確実に届くようなかたちでまとめ上げることのできる極度に専門的な職能、それが玉井のいう現在必要とされるプロデューサー像なのである。
そうしたプロデュース全体を丸ごと請け負うのがアゲハスプリングスという会社であり、玉井は「プロデュースワークそのものを買っていただく」と表現している。
言葉にすれば簡単そうだが、これは要するに、音楽制作を采配する権力そのものを外注業者として引き受けることに他ならない。クライアントの発注通りに仕上げることを旨とする制作会社とは本質的に異なるし、プロデュースそのものを売りものとする会社というのはアゲハスプリングス以前には存在していなかった。