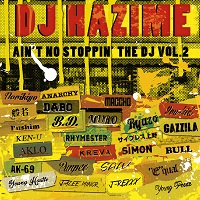瀧見憲司(クルーエル・オーナー/DJ)インタビュー(前編)
「DJに求められるものが違う」瀧見憲司が語る、海外のクラブ現場事情

日本を代表するベテランDJで あり、自ら音源制作を手がけるアーティストであり、インディ・レーベル「クルーエル」のオーナーでもある瀧見憲司。昨年秋に6年ぶりのミックスCD『XLAND RECORDS presents XMIX 03』をリリースした彼に、クラブ・カルチャーの変遷と現状、DJとしてのこだわり、そしてJ-POPカ ルチャーとの距離感などについて存分に語ってもらった。
筆者が瀧見と知り合ったのは彼がまだ20歳 そこそこで『フールズメイト』誌編集部で働いていたころに遡る。久々にじっくり話した彼は、それから25年以上がたっても、元ジャーナリストらしい冷静かつシャープで明晰な視点を失っていないのが嬉しかった。
――ー昨年「HigherFrequency」 のインタビューで、「海外のいろんなところでやる機会が増えて、日本人としてというか人間としての弱さも実感するけど。どうしても越えられない一線があるように感じるっていうか。例えば盛り上がっている現場で受けるトラックをそれなりのミックスでかけるのは簡単なんだけど、そうじゃない状態で一線を越えるのは難しい。自分固有のものを持ったまま、あくまでDJとして通用させるのは難しいよね。まだ自分はその一線を越えているとは思えないし」と発言されてましたよね。 瀧見くんのような海外でのプレイ経験も多い、キャリアのあるDJからそういう発言が出るのは重いし、意外でもありました。
瀧見: それは突き詰めると、日本人の、というか自分が持つ白人コンプレックスみたいなものに繋がるんですよ。日本人は世界的に見ればマイノリティだし。日々の生活の中で音楽はもちろん、洋服や身の回りのガジェット、生活様式もほとんど全てが西洋文化に元があるものに囲まれていて、そういう生活を普通にしている自分が、海外で日本人やアジア人が一人もいない場所でプレイして盛り上がってる時に、ふと、壁や一種のアイデンティティ・クライシスみたいなものを痛感することがありますね。もちろん現場では意識ではそう思っていても、体は動いてますけど。やっている事で国境は超えているんだけれど、世界の中での日本人の立ち位置とか存在意義みたいなものをどうしても意識してしまうんですね。30年ばかりずっと洋楽を聴いてきてレコードを買い続けて、音楽と状態を紹介する。言ってみれば自分はそういう人生を送ってきたと思うんです。紹介の仕方のパターンやフォーマットが変わっただけで。日本人なんだけど洋楽を聴いてる、というスタンスは変わってなくて、いざ海外でやってみると、自分はいったい何なんだろうって思いにとらわれるんですよ。結局自分はネイティヴではないし、かけているのは西洋の音楽だけど(歌詞などの)意味や成立過程が完全にわかっているわけではない。でもそれなりに受け入れられているという事実を考えると、 一体どういうことなんだろうなと。
――プレイしていてお客さんの反応を見てそう感じるわけですか。
瀧見:感じる。歌詞がわからないなりに流れを考えてセットを組んでるわけだけど、絶対に、完全には正しくはないだろうなと思う時はある。正しくなかったり誤読や誤解してるところが逆にうけてるのかもしれないけど。
――この曲の次にこの歌詞の曲はおかしい、とか、そういうことですか。
瀧見:極端に言えばそういうことです。その曲を成り立たせている文化や背景そのものを完全に理解できているとは言えないから。
――実際に言われたことはある?
瀧見:言われたことはないです。でも、これは外したかも、と思うことはある。まあ歌ものを続けてかけることは実際の現場では滅多にないですけど。
――それが日本人が海外でDJをやるときの限界ですか。
瀧見:日本人一般というより、自分自身の限界を感じるときはありますね。スポーツと違って明確な勝ち負けのある世界とも違うので。でも完全にわかってなくても呼ばれるってことは、それなりに意味を読み取ってくれてるんだなとは思いますけど。
――歌ものでないインストの場合は感じないわけですよね。
瀧見:いや、感じますよ。ある程度の技術があって、同じような曲をかけるのであれば、自分でなくてもいいのかな、誰がやっても一緒なのかな、と思う時がある。自分の持ち味を出しつつ受け入れられるのはすごく難しい。
――定番ネタとかヒット曲だと、誰がやっても同じになってしまう可能性がある。
瀧見:ヒット曲でなくても「こういうタイプの曲をかければキープできるな」というのはわかってるわけですよ、 経験上。そこで自分らしさを出して、なおかつ受け入れられるのは難しい。凄い盛り上がってる時に、客のパワーに寄せて合わせるのか、違う事をやりつつ場をキープできるのかという事ですね。
――なるほど。それはさきほどの、日本人のとしての自分というよりは、DJとしての自分の限界ということですね。
瀧見:そう。だから両方あるんですよ。後、アーティストDJというかパフォーマンスとしてDJをやるDJと、クラブDJの違いというのもあるので。
――なるほど。身近にいる日本人のDJで、 そこをうまくクリアしてる人というと?
瀧見:結局ガイジンになっちゃうのかならないのかっていう境目があって。サトシ・トミイエ君なんかは生活基盤も含めてガイジンになってるでしょ。でも僕はガイジンにはなれないわけですよ。今の自分の状況で自分が若かったら絶対向こうに移住してると思うけど、この年齡(47歳)ではすべてを捨てて海外で勝負するような、そういう無謀さはないし、状況的にも難しい。となると、そういうジレンマからもなかなか逃れられない。