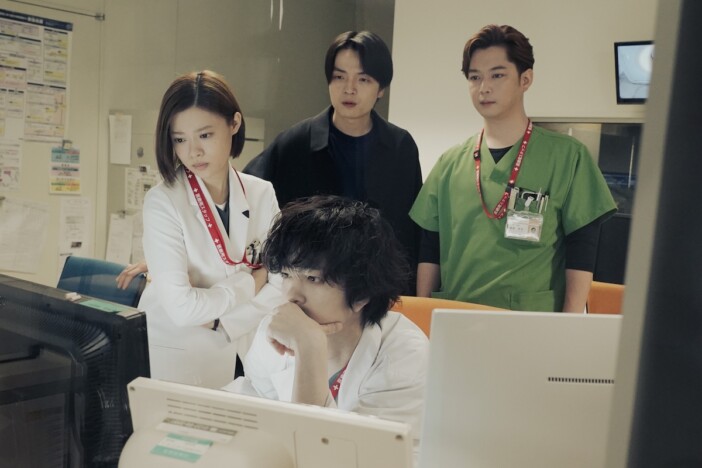井浦新が気付いた“当たり前”を変えていくことの大切さ 「幸せになることで誰かを幸せに」

井浦新がカウボーイになる。この一文だけでも映画ファンなら心踊るだろう。映画『東京カウボーイ』は、井浦演じる主人公・ヒデキが、アメリカ北西部・モンタナ州の牧場に出張する中で自分自身の人生を見つめなおしていく人間ドラマだ。初のアメリカ映画での主演、そして“人間讃歌”ともいえる本作を通して井浦は何を思ったのか。じっくりと話を聞いた。【インタビューの最後にはサイン入りチェキプレゼント企画あり】
「一歩踏み出すことの豊かさに気づくきっかけになれば」

――アメリカ映画での主演は初となりますが、オファーの経緯を教えてください。
井浦新(以下、井浦):マーク(・マリオット)監督はこれまでの僕の出演作をずっと観てくれていたそうなんです。作品を観た上で、「あなたに出演してほしい」と。とくに海外作品に出たいという意識はなかったのですが、俳優として取り組んできたことが海外の監督からのオファーにつながった……ということが、日本の俳優として素直にうれしかったです。

――この作品を経て、井浦さんの心にはどんな影響がありましたか?
井浦:お話をいただいたのが2021年のコロナ禍の時期で、日本では人とのコミュニケーションが簡単ではなくて、今まで当たり前だったことが当たり前じゃなくなったことを受け入れていかなくてはいけないころでした。どんどん締め付けられるし、僕自身も精神的にだいぶ疲れていた中、モンタナでの撮影が始まって。2022年の5月でしたが、その頃のアメリカにはもうマスクをしている人なんか一人もいなくて、今までと同じようにコミュニケーションを取って、感動したときにはハグし合って、尊敬し合って、語り合って……ということができた。それが僕にとって、だいぶ救いになったんです。物語の内容ももちろんですが、日本の撮影では本番だけマスクをはずすような時期だったので、久々に“現場で伸び伸びと過ごせている”ということに魂から救われる思いでした。

――恋人との関係も、仕事との向き合い方もある種“規律”に縛られていたヒデキが、カウボーイとなりどんどん開放されていく。映画を観ていて「何をしてもいいんだ」と救われたような気持ちになりました。
井浦:そう受け取ってくださると、本当にこの作品を作った甲斐があると思います。ヒデキは特別な人ではなくて、きっと誰でもヒデキの側面を持っている。男性でも女性でも何かを一生懸命やっている人は、ヒデキになりがちというか。でも、夢中になれることがあるのは素晴らしいことだけど、頑張った分の対価を自分の好きなことに費やすんじゃなくて、仕事に追われたり、没頭したりすること自体が幸せで、そうしなければいけないと錯覚してる人たちが実は多いと思うんです。ヒデキのように、仕事が生きがいだと思い込んで目の前のことを一生懸命やっているけれど、その目の前にある世界って実はまだまだ狭くて。その外側に広がった無限の世界に一歩踏み出すことの豊かさに気づくきっかけになったり、ご自身と重ね合わせたりしてもらえると、この作品を作った意義があると思います。

――ヒデキはモンタナに向かった当初、自身の考えを現地の人に押し付けるような行動が目立ちます。やはり日本人には、「自分たちのフィールドでやりたい」と思う人が多いですよね。「日本人は」と主語を大きくするのはよくないですが……。
井浦:僕もつい「日本人は」と言ってしまいますが、日本って世界から見てもなかなか個性的で。島国の気質がまずひとつあって、あとはやっぱり戦争が与えた影響が大きいんだろうなと思います。一回全部が壊れて、戦後に国自体を立て直していくときに、日本経済の歯車の一つとなって働いてきた人たちは相当な努力をされたのだろうと思いますし、それによって日本は数十年で経済大国になっていった。でも、発展や利益のために働くことがすべてではないんですよね。当時は必要であったことが、いまでも名残としてあると思うので、「それだけではないんだ」というのは、簡単には受け入れがたいところがあるのかもしれません。
今回の現場ですごく思ったことがあるんです。僕は俳優として26、7年やってきましたけど、職人や表現者、アーティストのようにこだわって仕事をする方たちが多い現場では、機が熟した時に伝える、“思ったことをすぐに言わないこと”が美徳の一つみたいなところがあって。打ち上げのときに「あのとき良かったよ」と褒め称えたりすることが多いんですが、『東京カウボーイ』の現場では、その瞬間瞬間に感じたら、すぐにみんなが敬意を伝え合う。僕にとってそれは学びであり、すごく刺激になりました。いいと思ったら素直に「よかった」、感動したら「素晴らしかった」と、俳優だけじゃなくて各部署がちゃんと言い合えているんです。そこにはポジティブな空気しか生まれてこないので、みんなが敬意を持って一つの作品に向かっていって、一体感を持ってプロフェッショナルに仕事するという、本当に素晴らしい現場でした。日本でもまったくないわけではないですが、それが当たり前になっていったら素敵だと思いました。

――“当たり前”を変えていくことの大切さに気づかれたわけですね。監督とは、どのようなやり取りを?
井浦:監督が求めていたのは、いわゆる演技らしい演技をせずに、怒ったり興奮したり、どう動いていくかを見せていくことでした。演技をし過ぎたときはもう1回やってみようとなり、僕も監督がこの映画の温度感をどうしたいのかはキャッチしていたので、いつの間にかヒデキの境遇と僕の状態が一つになっていました。言葉が通じない撮影の現場に入っていくという点では、本当にヒデキと同じような状況になって、いつの間にかフィクションではあるけれども、僕の内側のところでは完全なノンフィクションになっていると、一つ一つ体感してみて感じました。