美 少年 浮所飛貴が大活躍 『胸が鳴るのは君のせい』に見る“キラキラ映画”の男性像の変化
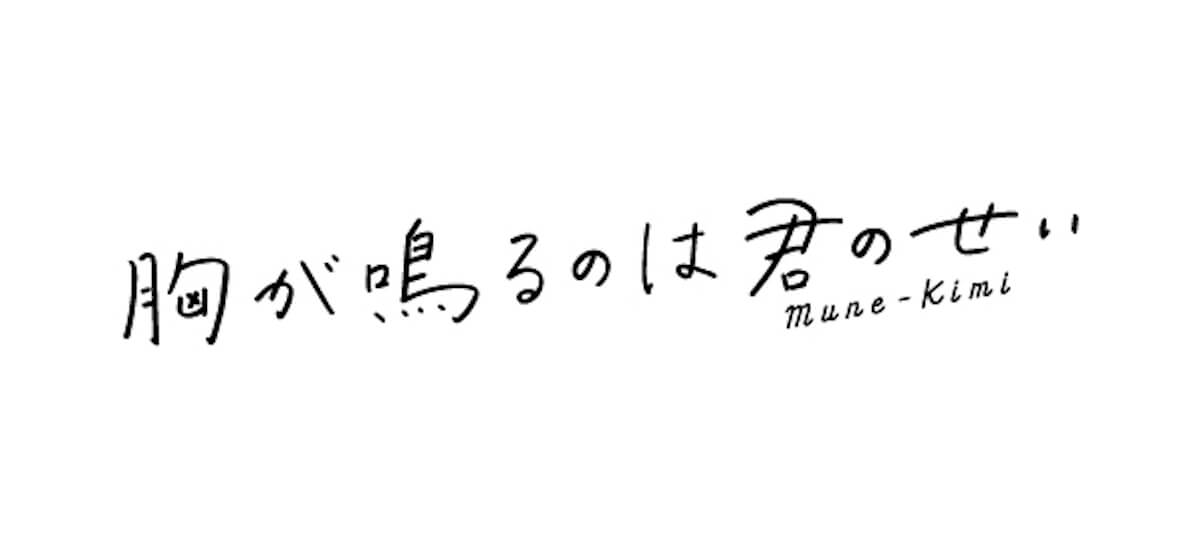
映画の序盤でヒロインが愛の告白に失敗し、それでも一途に相手を想いつづける。紺野りさ原作の『胸が鳴るのは君のせい』における恋愛要素の主軸となる部分は、昨年映画化された咲坂伊緒原作の『思い、思われ、ふり、ふられ』(以下『ふりふら』)における由奈と理央の関係性にも似ている。この両作品ともに2010年代の少女漫画を代表する傑作であり、2020年代に入り(すっかりブームは下火となった)“キラキラ映画”の流れを汲んで実写映画化されているとあれば、もはや「告白」は、かつてのように天地を揺るがすビッグイベントではなくなったのか。もしかすると、ここに“キラキラ映画”が陥ったマンネリ化を脱却するヒントが隠されているのかもしれない。
『ふりふら』では、原作でも実写映画でも、二組の男女の関係性の変化が台頭に描写されると同時に、その片方である由奈と理央の関係を通して、極めてオールドファッションな少女漫画の流れを汲むようにして「恋愛を通して人間的に成長していくヒロイン」の姿が描かれていた。しかし『胸が鳴るのは君のせい』(以下『胸きみ』)の場合は、劇中の様々な出来事を通してヒロインであるつかさにめざましい成長が訪れたようには見えない。しかし、それは決して悪いことではない。割と簡単に感情が揺れ動いてしまう従来の少女漫画ヒロインとは異なり、彼女は最初から最後まで徹底して「有馬隼人が好き」という一点から一ミリたりともブレない、驚異的な芯の強さを発揮するからである。
観客に“共感”してもらうことに注力された昨今の映画のなかでも、一際その傾向が強かった“キラキラ映画”界において、こんなにも変化がない主人公を扱うというのはかなり挑戦的と捉えることができよう。代わりに変化と成長を与えられるのは、相手役である男子キャラクターの方だ。有馬はかつての恋人に怪我を負わせてしまったことを悔やみ続け、自分のせいで大切な人が傷付くのを忌避しようと壁を作ってしまう。そんな苦悩を抱えた有馬を、つかさの一途さが解き解していく。「私はそんなに脆くないよ」というつかさの言葉はもちろん、思春期男子に特有の嫉妬心から解放されていく有馬の姿からは、(そもそも映画に対象となる性別は存在しえないとは思っているが)男子にも共感のチャンスが与えられた作品であるといえよう。
とはいえ、今回の映画化においては“キラキラ映画”特有の課題をまざまざと見せつけられてしまったことは否定できない部分だ。原作では物語は3つのパートに大きく分けることができた。1つ目は「つかさが有馬に告白して振られても想い続け、有馬は麻友との過去に向きあう」というパート。2つ目は「有馬がつかさに想いを伝えるが、つかさは長谷部にキスされたことが言えずに拒絶してしまう」パート。そして3つ目は「両者が無事に付き合うことになるが、言葉不足によって関係に綻びが出てしまう」といったところだ。
必然的にそれなりの期間連載された作品を映画用に脚色するとなれば、原作のどの部分を生かし、どの部分を削るかという取捨選択が求められる。前述した『ふりふら』のように頭から終わりまで淡々と一気に進めながら合間の細かいディテールを省いていくというやり方もあれば、原作とまったく異なる部分に結末を置きがらりと雰囲気を変えてしまうという選択肢もある。この『胸きみ』では後者の選択肢を取り、前述した3つのパートのうち前2つのみを映画にすることで、これまでの“キラキラ映画”の王道を貫く、「恋愛成就」に帰結点を求めるスタイルをとることとなった。





















