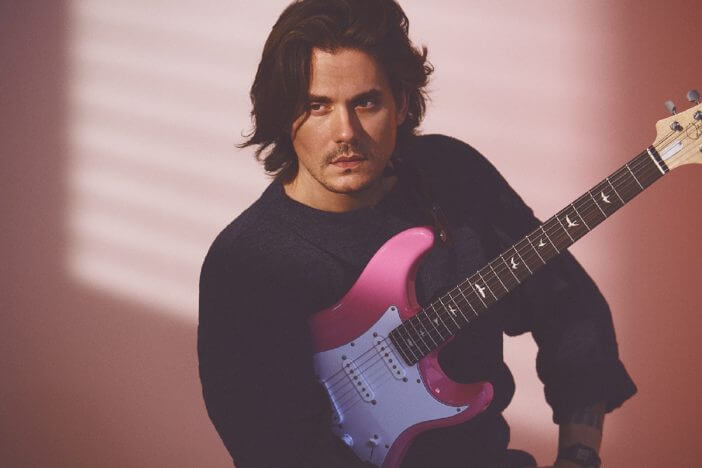葛谷葉子『MIDNIGHT DRIVIN’-KUZUYA YOKO MUSIC GREETING 1999〜2021-』特別対談
松尾潔×ジェーン・スー、再発見する葛谷葉子の魅力 「時代性と普遍性のバランスが自然に備わったアーティスト」

1999年8月にシングル『TRUE LIES』でデビュー。同時代のR&Bのテイストを反映したサウンドメイク、洗練と深みを共存させた楽曲、そして、透明感に溢れたボーカルによって、シュアな耳を持つリスナーの支持を得ていた葛谷葉子が、11年ぶりに活動を再開した。
最初のアクションは、リマスター・ベストアルバム『MIDNIGHT DRIVIN’-KUZUYA YOKO MUSIC GREETING 1999〜2021-』のリリース。「TRUE LIES」「サイドシート」などのシングル曲のほか、新曲「midnight drivin’」「Honey」を収めた本作は、葛谷葉子のタイムレスな音楽性を改めて示すと同時に、世界的なシティポップムーブメントの潮流とも合致したアイテムに仕上がっている。
リアルサウンドでは、デビュー当初から葛谷のプロデュースを担っていた松尾潔、レコード会社の社員として彼女のプロジェクトに参加していたジェーン・スーの対談をセッティング。シンガーソングライター・葛谷葉子の魅力について語り合ってもらった。(森朋之)

デモテープのメロディがとにかく素晴らしかった(松尾潔)
ーージェーン・スーさんは葛谷葉子さんのデビュー当時、レコード会社の社員として深く関わっていたそうですね。
ジェーン・スー(以下、スー):はい。それまでは担当メディアに自社の新譜をまんべんなく宣伝する仕事をしていたんですが、初めて新人アーティストのリリースと宣伝のプランを考えるプロジェクトにアシスタントとして関わることになって。入社して2、3年目の頃ですね。
ーー葛谷さんの最初の印象は?
スー:デモテープを聴いたとき、「手練れのコンポーザーが作った曲みたいだな」と思ったんですよ。それくらいクオリティが高かったし、成熟しているようにも感じて。ただ、デモ音源はキーボードの弾き語りで、かなり稚拙だったんです。その歪(いびつ)さにも惹かれたし、興味をそそられました。
ーー当時は宇多田ヒカル、MISIAのデビューによって、日本の音楽シーンにR&Bのムーブメントが巻き起こっていた時期。やはりR&Bの系譜にあるアーティストを探していたんでしょうか?
スー:どうですか、松尾さん。
松尾潔(以下、松尾):葛谷さんはもともと、JCMという音楽出版社のデモテープオーディションで選出されました。いくつかのレーベルと話をするなかで、エピックレコードに決まったと聞いています。その時点で宇多田さんやMISIAさんを意識していたかはわかりませんが、世界的な潮流として、90年代半ばにはR&Bが覇権を握っていましたし、いずれ日本にもその流れが来るだろうと言われていました。そういう見地じゃなければ、選ばれなかったタイプの音楽かもしれないですね。ただ、当時のエピックレコードには葛谷さんのようなアーティストを手がけた実績がなかったし、どうやって打ち出すかを考えあぐねていたようで。音楽的に近しいところでは(エピックレコードと同じソニーミュージックに所属していた)古内東子さんがいらっしゃいましたが、葛谷さんはもっとブラックミュージック寄りだったので。

ーーそれで松尾さんがプロデュースを担うことになった、と。葛谷さんはどんな音楽がルーツなんですか?
スー:メアリー・J.ブライジはよく聴いてましたね。
松尾:そうだね。あとはベイビーフェイスとか、当時のR&Bの王道が好きだったんじゃないかな。
ーー松尾さんはもちろん、スーさんもブラックミュージック好きですよね。
スー:そうですね。大学生のときは早稲田大学の「ソウルミュージック研究会」というサークルに入っていたし、それこそ松尾さんが書いた文章を読んで理解を深めていたので。葛谷のプロデュースを松尾さんが引き受けてくれたときも、「あの松尾潔さんと仕事ができる!」と、すごく嬉しかったんです。初めてお会いしたときはめちゃくちゃ緊張しましたけど。
松尾:まあ僕と2、3回も会えばスーさんのときめきは消えたようで、すぐに仕事仲間になりましたけど(笑)。葛谷さんはブラックミュージックに興味はあるけど、アーティストのデータやプロファイルにはそれほど興味がないというタイプでした。
スー:そうかも。音楽を体系的に聴くとか、ルーツを遡ることはほとんどなかったんじゃないかな。
ーーマニアックなリスナーではなかった、と。それでいて楽曲のクオリティが高いということは……。
松尾:天才的ですよね。ナチュラルボーンな才能なのかもしれません。
スー:音楽の芯の部分に最短距離で到達できる人ですよね。当時は嫉妬すら覚えましたから。
松尾:スーさん、「嫉妬するほどの才能なのに、本人はそのことに気づいてないんですよ」って言ってたよね(笑)。確かに才能はすごかったです。最初に20曲くらいデモを聴かせてもらったんだけど、どれも素晴らしくて。さきほどスーさんがおっしゃったように簡素なデモテープだったんだけど、とにかくメロディが素晴らしくて、ブラッシュアップすれば大丈夫だなと。
スー:その頃からアラフォー、アラフィフの耳の肥えたリスナーが涙するようなメロディを書いてましたからね。
松尾:うん。アレンジや歌詞、楽曲の構成に関しては意見を言わせてもらったけど、メロディを変えてもらったことは一度もないので。ボーカルの表現も最初からすごかったよね。
スー:そうですね。「もし私がこんな曲を書けて、こんなふうに歌えたら、死ぬ気でやるけどな」と思ってました(笑)。
松尾:ハハハハ(笑)。
スー:歌のテクニック、たとえばビブラートも本当に美しくて。R&Bテイストのビブラートが自然にできるシンガーは当時ほとんどいなかったと思うし、「日本人には無理」と言われてたのに、葛谷は最初から身に付けていました。
松尾:たとえば「恋」という楽曲のアウトロのフェイク。すさまじいよね。あのパートは歌い手としての非凡さを証明していますが、じつはスタジオに入った時点で、彼女のなかに譜面があったんですよ。
ーーどういうことですか?
松尾:その場の思い付きでフェイクしているのではなく、作曲家として考え抜いてからマイクの前に立っているんです。いつも。そのスタンスも好きなんですよね。僕自身もーー小説(『永遠の仮眠』)でも書いたんだけどーースタジオで起こるマジックを信用していないし、事前に準備してレコーディングに望みたいタイプなので。葛谷さんはレコード(記録)の意味をよくわかっていたし、誰に教わるでもなく、プロフェッショナルな意識が備わっていました。今回のベストアルバム(『MIDNIGHT DRIVIN’-KUZUYA YOKO MUSIC GREETING 1999〜2021-』)には1stアルバム(『MUSIC GREETINGS VOLUME ONE』/1999年)からもたくさん収録されてますが、10代から20歳くらいまでに書いた曲がほとんどなんですよ。今聴いても本当に素晴らしいし、20年以上経って、その作品力が証明されたのではないでしょうか。
ーー確かに楽曲の質の高さはすごいですよね。ただ、当時はセールス的に苦戦したそうですね。
スー:音楽的な才能は疑いようがないし、声の魅力や歌唱もずば抜けていたんです。ただ、いま振り返ってみると、こちらが大人の世界観を期待しすぎたのかもしれないですね。彼女の作曲センスを考えると、どうしても30代以上の人生経験を歌ったほうがいいのかなと。

松尾:そうかもね。
スー:もちろん反響もあったんですけどね。耳のいいリスナーが多い札幌の(FM局)NORTH WAVE、小倉のCROSS FMなどでヘビーローテーションになって、すごく応援してもらえて。それをきっかけにして、こういう音楽が好きな好事家のみなさんに「新しいアーティストが出てきた」と認知していただけたので。
松尾:各地のFMステーションごとにミックスCDを作って配ったりもしましたね。葛谷さん自身は岐阜の出身で、ZIP-FMを車でよく聴いてたらしいんですよ。新曲の「midnight drivin’」につなげようとしてるわけじゃないけど(笑)、そのときから「車のなかで聴いてカッコいい曲」が指針の一つになっていた感じはありますね。
スー:松尾さんのプロデュースのおかげで、力のある作品を作っていただきましたから。そう言えば、プロモーションの一環としてニューヨークにも行きましたね。
松尾:そうだった! R&B/ヒップホップ系のレコードショップに葛谷さんのカセットテープを置いてきたりしたな。僕はアトランタまで足を延ばして、ダラス・オースティンやベイビーフェイスのチームにも音源を聴いてもらいましたよ。デビューシングル「TRUE LIES」に収録したリミックスは、TLC「Creep」に関わったDJソウル・メサイアにお願いしました。
スー:当時はレコード会社にお金があって、市場調査のような目的でニューヨーク出張ができたんですよ。今では考えられないけど。
松尾:“海外で色付けする”みたいなことが有効な時代でもあったからね。あと、僕が関わっていた『ASAYAN』の男子ボーカリストオーディションで、葛谷さんの「最後の夜」を課題曲にしたこともありました。その後、葛谷さん本人がセルフカバーしたんだよね。
ーー「最後の夜〜KUZUYA’S R&B〜」ですね。
スー:そうです。1stアルバムと2ndアルバム(『MUSIC GREETING VOLUME TWO』/2001年)、両方に「最後の夜」が収録されてるっていう(笑)。振り返ってみると、いろいろ頑張ってましたね。私も一生懸命でしたけど、彼女の音楽の魅力を伝えるには、スキルもアイデアも足りなかったと申し訳ない気持ちになります。アーティストの魅力を引っ張り出して、それを最大限活用するのがプロモーターの仕事なんですが、私は足りない部分をサプリで埋めるようなことばっかりしてたので。たとえばラジオのゲストの枠が取れたときもそう。聴いている人が「この人、おもしろいな」とか「いい曲だな」と思ってもらえるような言葉を紡げないと、ゲストとして出させてもらう意味もないし、ラジオ側も「呼んでよかった」と思ってくれないじゃないですか。葛谷はそういうことがあまり得意ではなかったようで、私は大人げなく「もっとマジメにやって!」とヤキモキしちゃって。でも、彼女はマジメにやってたんですよね。
松尾:その話は葛谷さんに同情しちゃいますね。後に人気ラジオパーソナリティーになるジェーン・スーさんに「何でうまく喋れないの?」と言われても(笑)。
スー:私が得意なことを葛谷に押し付けようとしていたのかもしれないと反省しています。当時の葛谷の音楽に対する姿勢は、“曲を作って歌えれば満足”と言いますか、どうしても人に伝えたいという感じではなかったんですよ。本人を稼働させず、曲を動かすことを考えるべきだったんですが、時代的にもそれが難しくて。
松尾:ストリーミングもYouTubeもない時代だからね。いろんな意味で前例のないアーティストなんだと思います。