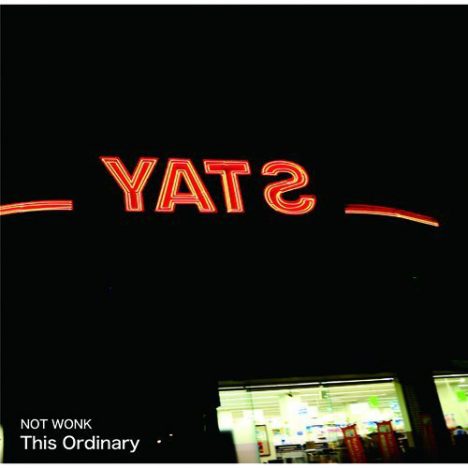NOT WONKは若い世代の新しいヒーローになる パンクバンドの現在形を石井恵梨子が観た

アンコール。再度ステージに出てきた加藤修平(Gt&Vo)は、前日名古屋で共演したニトロデイの名前を挙げ、「俺もけっこう若いけど、もっと若い人たちもベースとかギターが楽しいんだなって思う」と笑った。「ていうか俺も早くギター弾きたいんで!」と始まったのは1stアルバム収録の名曲「Laughing Nerds And A Wallflower」。疾走する青春を真空パックにしたようなメロディックパンクが弾け飛ぶ。同時に弾けだすフロアの観客。次々と上がる拳が眩しかった。これは何十年前から続くおなじみの光景? 否、はっきりと新しいパンクバンドの現在形である。

少し話が大きくなるが、今、本当に世界でギターサウンドは求められなくなっている。聴こえてくるのは豪華なシンセか圧倒的な低音ばかり、中域を担うギターの音が出た瞬間Spotifyではスキップされるとの話もあって、ロックバンドはなかなかに肩身が狭い。もちろん、そんなの知らねぇと開き直るのも一興。私を含めてロック愛好者は一定数いるのだし、ライブハウスで爆音を鳴らせば瞬間のカタルシスは得られるだろう。ただ、若いトラックメイカーや優れたラッパーが次々と出てくるメインストリームの流れには、どうやっても与せない。3人なり4人なりの集団がスタジオにアンプと機材を持ち込み、せーのでデカい音を出す、その光景自体がクールじゃない時代なのだ。ただギターを掻き鳴らせばOKという前提を疑わなければいけないのだろう。
『Down The Valley Tour』最終日、7月14日渋谷WWW X。ゲストに登場した踊ってばかりの国も同じような意識を持っているだろうか。ギターが3人いるバンドとは思えない音で、空間を活かした単音のフレーズがふわりふわりと宙を舞う。各パートに派手な衝突はない。主軸は下津光史(Gt&Vo)の美しい日本語と美しいメロディだ。昭和の路地から突然トリップしてきたようなレトロ感。それでも郷愁とは違うみずみずしさに溢れた声の力。無垢すぎてネジがぶっ飛んでいるようにも見える満面の笑顔。ただし歌い手+バックバンドというわけでは決してなく、5人のまどろむグルーヴは次第にサイケな熱を帯びていく。8分近い曲なのに長さを感じさせず、気づけば3人のギタリストが奔放なソロを弾きまくっていた「BOY」はことに素晴らしかった。豪快でも攻撃的じゃないところが彼ららしくていい。演奏することのピュアな楽しさを持ち寄り、じっくり手間暇をかけて“バンドじゃないとやれないこと”を見せる、そんなステージだ。
比べてNOT WONKはもっと即効性の高いパンクをやっている。少なくとも以前はそうだった。90年代のUKメロディックやエモを基調にした楽曲が一部愛好者の間で話題を呼び、苫小牧からの上京を待ちわびる週末のライブハウスには毎度熱心なファンが集まった。ただ、それらはキャパ200人規模の話。500人を収容するWWW Xが八割方埋まった今回の公演は、今までいなかった客層が一気に増えたことを示していた。新作『Down The Valley』がメジャーから発表されたことや、多くのバンドマンが本作を絶賛したことは大きい。ただ、結果はやはり音楽そのもの。過去の雛形から離れだした楽曲が、直接若いリスナーを撃ち抜いたのだと思う。これはなんだか新しい予感がする、と。

セッティングを終え、特別なSEもなくそのままライブがスタート。華はないし振りまく愛想もないが、Tシャツ姿の地方在住者たちがステージに立つことのほうが重要だ。誰も特別じゃない。僕もあなたも変わらない。1曲目は多くの先人が歌い継いできたレナード・コーエンの「Hallelujah」。それぞれの生き方を肯定するように繰り返されるサビが、耳にゆっくり染み渡っていく。しいて言うならジェフ・バックリィの弾き語りカバーバージョンに近い、祈りにも近いオープニングである。
もっと軽やかに始まると思っていたから、2曲目が「Landfall」だったことにさらに驚いた。近年はラストに配置されることの多かった7分超えの壮大なナンバーで、じっくり、ゆっくり、焦らすように歩を進めながら、中盤からようやくギターの轟音がうなりを上げていく。つまり、踊ってばかりの国の「BOY」とほぼ同じ展開なのだが、比べてもNOT WONKのギターはずいぶん生々しい。攻撃的と書くとニュアンスは違うが、苛立ち、怒り、悲しみ、悔しさ、どうしようもなさ、そういう感情を掻き集めて炎上させ、何もかも真っ白に昇華させるイメージだ。感情を増幅させ大爆発させる装置としてのギター、感情と音が直結している人間のギターが、気づけばごうごうと吹き荒れている。

感情爆発型だからこそ、NOT WONKがパンクから始まったのは当然だと思う。ただ、何度も書くように、ただギターを掻き鳴らして何かが変わる時代ではない。だからなのか、新作は爆発に至るまでの緻密さが違う。ライブは3曲目から新作の曲順どおりに「Down The Valley」〜「I Won’t Cry」の7曲が続くが、どれもしっとりしたメロディアスパートの焦らし方と、そこから爆音になだれ込むダイナミズムがたまらなかった。演奏力はもちろん、後半に向かって次第に熱を高めていく手法がお見事。静と動の対比を意識し、最初にこらえてサビで爆発、なんていう単純さでは絶対に作れない曲ばかりだ。
彼らの楽曲は、基本的にはいい歌、弾き語りでも成立するグッドメロディが芯である。そこに味をつけるのが新たに入ってきたソウルミュージックのフィーリングであり、細やかに震えるビブラートの艶っぽさ。いい歌+色気あるアレンジで耳を惹きつつ、アキム(Dr)のスネアが叩き込まれた一瞬、あるいは藤井航平(Ba)がぐっと体を動かした瞬間から、まず平熱が微熱にアップする。いわば“普通のいい曲”が“ロックバンドの激しい曲”になる。そしてそれは、後半に迫りくる轟音、限界まで膨れ上がるディストーションによって、いよいよ“問答無用に格好いいギターの曲”へと変化していく。ひときわヘヴィな「I Won’t Cry」が始まる頃には、もっと、もっとと心から爆音を渇望している自分がいた。普段から激しいライブには慣れている。むしろそれが当たり前くらいの感覚でいる。なのに私は10代のガキみたいな気持ちで衝撃を受けていた。一一ロックバンドってこんなに格好いいものなのか! これが、今のNOT WONKだ。