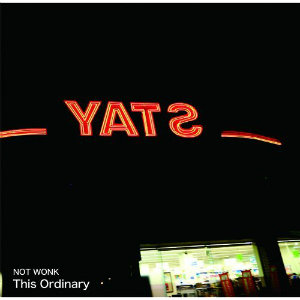“シティポップ”とは異なるもう一つのムーブメントーーNOT WONK、CAR10、ドミコの台頭を追う
2016年前半、東京を中心としたインディシーンを象徴するような作品が多くリリースされた。LUCKY TAPES、Awesome City Club、ミツメ、ayU tokiOらは新作で、広義の意味でのブラックミュージックを日本語のリズムで解釈し、都市、あるいは都市郊外の“街”のムードや空気感をサウンドに落とし込んだ新しいポップミュージックを生み出した。また、Suchmos、D.A.N.、雨のパレード、The fin.らは、世界とボーダレスにつながりながらも、あくまで日本的なメロディと歌の情感の中で、洋楽的なフォルムを再現した。彼らの音楽的ルーツ、編成などはそれぞれ異なるが、これまでの“ロックバンド”のあり方とは一線を画すその音楽性は、一つのうねりとなって音楽シーン全体を賑わせている。
ここで筆者が注目したいのは、上記のように東京を中心に洗練されたサウンドが流行する一方で、“地方都市”と呼ばれる場所で、90年代のパンク/インディ、あるいはオルタナ/ガレージを彷彿とさせる、等身大かつ自由な解釈で、新しいロックを構築しつつあるバンドたちが同時多発的に生まれている、ということだ。彼らの年齢は、1990年代生まれが中心の20代前半から半ば。ここでは、NOT WONK(北海道・苫小牧)、CAR10(栃木・足利)、ドミコ(埼玉・川越)を例にあげて、彼らの動向を追ってみたいと思う。
NOT WONK
北海道・苫小牧発、1994、95年生まれのスリーピース・バンド=NOT WONK。彼らの名が知られるようになったのは、2014年に京都の若者たちが主宰するインディ/パンクレーベル<生き埋めレコーズ>のコンピに収録された楽曲がきっかけだった。そこから火が付いて道外でもライブを行うようになり、YouTubeにライブ映像を投稿、カセットテープ限定で音源をリリースするなどして、ネットやライブハウスを中心に話題を呼んだ。そして、昨年には元銀杏BOYZのアビコシンヤがチーフ・プロデューサーを務めるレーベル<KiliKiliVilla>からファーストアルバムを、今年6月にはセカンドアルバム『This Ordinary』をリリースした。
はじめてカバーしたのはHi-STANDARDとELLEGARDEN。もっとも影響を受けたバンドはMega City Four。それらのバンドが日本の音楽シーンに新たな潮流を生み出した90年代から00年代にかけて思春期を過ごしながらも、同時にネットを使ってあらゆる情報に自由にアクセスできる時代に生まれた世代特有の感性を、NOT WONKの音楽からは感じられる。パンク、メロディック、エモ、USインディ、グランジ等のエッセンスを、自分たちの“今”の気分がハマる等身大な表現手段としてクロスオーバーさせることで、彼らのロックは成立している。
歪んだギターとドタバタと走るリズム。自由気ままに疾走するラフな演奏ではあるが、その真ん中を通っているのは清々しいほどのグッドメロディだ。曲によっては、驚くほどスイートなメロディを響かせているのも良い。彼らの若々しくまっさらなムードと相まって、そのサウンドは新鮮に聴こえるが、それをただ“若さ”という言葉だけで片づけることはできない。NOT WONKは、2010年的な「ポップ化」とは異なる立ち位置から、「ロック」にこだわった進化を掲示しているように感じる。
CAR10
CAR10も、NOT WONKと同じく<KiliKiliVilla>に所属。栃木・足利を活動の拠点としているスリーピース・バンドだ。同レーベル初のオリジナル・リリースとして2015年にアルバム『RUSH TO THE FUNSPOT』を発表。また、その前には東京や地方からバンドを呼び、足利で精力的に企画ライブを行っていたPSYKICK UNDERAGEとのスプリットCDをリリース。さらに、今年9月には東京でGEZANなどと交流のあるTHE GUAYSとスプリット・シングルを発売し、その後は共にツアーを回るなど、シーン全体を巻き込もうとする動きを見せているバンドだ。
CAR10の曲は短い。多くの曲は2分程度で、はじまってから終わるまで90秒もかからない曲もある。エフェクターが効いたローファイなサウンド。脱力感のあるボーカル。がなり声のようなコーラス。前置きも余韻も取っ払って、言いたいことを言って、言い終わったらサクッと曲が終わる。CAR10の楽曲には、そういう自由なスタンスが貫かれている。
サウンドは、ガレージからパンク、ハードコア、 ギター・ポップなどの影響を受けながらも、USベッドルーム・ポップにも通じる浮遊感、刹那感が漂うのがCAR10の面白いところだ。フロントマンの川田晋也は、The LibertinesやThe Clash、Venus Peterからandymoriまで聴くというが、英詞と日本語詞の混ざった歌詞は、ふてぶてしく投げやりでいながらも、その根底には拭えない憂鬱さと切なさがある。近しい仲間とやりたい放題やる自由な気分と、”ここ”には何もないという退屈な気分。そのアンビバレントな感覚が、2010年代に生きる彼らのリアルな感性なのだと思う。