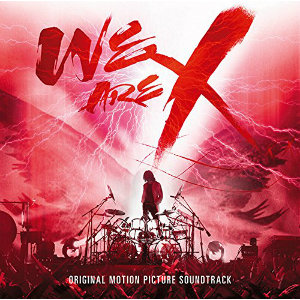『コーチェラ』に感じた時代の変化 ビリー・アイリッシュ、BLACKPINKら1週目ステージ振り返る
また、今年のコーチェラを通して感じた一つのテーマとして「ポジティブなムード」を挙げておきたい。最終日のヘッドライナー、アリアナ・グランデはラストの「no tearslLeft tocCry」、打ち上がる花火とレインボーフラッグをバックにした「thank u, next」で3日間のフェスティバルを讃えた。初日にガンビーノの直前に登場したジャネール・モネイも、ブラックウーマンの視点に、アルバム『Dirty Computer』のコンセプト=“多様性の祝福”を重ね、ビーチェラとリンクしながらも時代を前に進めた。さらにジャネールのステージにも登場し大柄な体でトゥワークしたリゾは若手の中でのその象徴だ(コーチェラで彼女を知った人は是非「Juice」のリリックを読んでみてほしい)。
そんな「ポジティブなムード」のほかに時代の変化を感じさせたことは、非英語圏のアーティストたちの活躍だった。例えば、J.バルヴィンとバッド・バニーがメインステージに持ち込んだレゲトンパーティ、スペインのロザリアであればフラメンコ、フランスのクリスティーン&ザ・クイーンズであればジャズダンスを織り交ぜた情熱的なステージはハイライトと呼ぶにふさわしい。他にもアフリカ・ナイジェリア出身のMrイージーやバーナ・ボーイ、チリのモン・ラフェルテ、The 1975と共演したフィリピンのノー・ロームなど挙げればきりがない。だが、中でも一番の衝撃はK-POPグループの歴史的デビューとなった、BLACKPINKのパフォーマンスだろう。
そもそもフェスの前の週に、マーチングを取り入れたサウンドや女性の隊列を使ったMVの演出でビーチェラを意識したシングル「Kill This Love」を発表したことからもコーチェラへの相当な気合が伝わって来ていた。直近のツアーでお披露目され始めたという生バンドの迫力はもちろんのこと、マイクを通してもいつもの何倍もの熱量がメンバーから伝わってきた。ビリー・アイリッシュに劣らぬ観衆の熱狂ぶりも後押しし、以前実際にライブを見たことのある私でさえ、画面を通してこれまで以上にグループの魅力に圧倒された。
普段はアメリカのメインストリーム音楽の中で「ユニークなもの」として受け入れられがちなこれらのアーティストの表現が、ヘッドライナー級のアーティストと変わらぬ熱狂を当然のように受けていた今回のコーチェラはとても感動的だった。近い将来、この中からヘッドライナーを飾るアーティストが出てくるのも時間の問題だろうし、そればかりか非英語圏アーティストによる表現こそがシーン全体の動きをリードするようになったって驚きはない。世界中にローカルシーンの魅力をアピールした今回のコーチェラでこれらのアーティストの功績はとても大きい。この原稿を書いている途中で2週目のストリームアーティストとして発表されたPerfumeのステージでは何が起きるだろうか。
■山本大地
1992年生まれ。ライター、編集者。海外の音楽を中心に執筆。2016年まで「Hard To Explain」編集部。現在は音楽メディア「TURN」編集スタッフも。