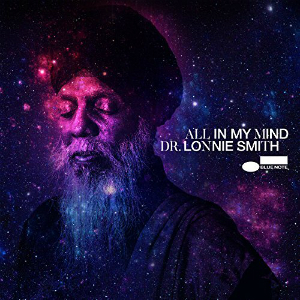柳樂光隆が選ぶ、ジャズミュージシャンが奏でる“まだ名前の付いていない音楽”5選
John Raymond & REAL FEELS『Joy Ride』

リリースは<Sunnyside>から。最近、生で観て最も印象的だったのはこのフリューゲルホーン奏者のジョン・レイモンドのグループ、リアル・フィール。ジョン・レイモンドは上記のJavier Santiago『Phoenix』にも参加している若手だ。
ジョン・レイモンドに加え、今やトップギタリストとなったギラッド・ヘクセルマン、カート・ローゼンウィンケルなどにも起用されるドラマーのコリン・ストラナハンの特殊編成トリオで、鍵盤やベースを排して、スペースをたっぷりと空けて音響感や空間性を生み出すことで、レディオヘッドの影響を受けたロック・インスパイアのジャズを演奏する、ということは知っていたが、この新作以降はそんな領域を超えた模様。
ボン・イヴェール、ピーター・ガブリエル、ボブ・ディラン、ポール・サイモンのカバーを収録していると言えば、少しはその雰囲気は伝わるかもしれない。アメリカーナ的な要素がありつつ、それでいて、ボン・イヴェールなど近年のインディーロックのサウンドも視野に入れている。ちなみにプロデューサーはマット・ピアソン。その時点で、何がやりたいかのメッセージが見えてくる。
特にジョン・レイモンドのエフェクトをかけたフリューゲルホーンがズバ抜けて素晴らしく、曲が求めている表現が確実に演奏されている。曲が持つフィーリングを的確に奏でるために、ソロのフレージングも音を増やしても上下させずに同じ体温と質感を保ったまま、狭い範囲で細かく動かして即興していた。つまり曲が持つ音色や手触りも合わせて、フレージングの熱量や運動をきちんと揃えていたということ。その抑制をしながらも、きちんと即興しながら音を変化させているそのセンスが抜群なのだ。
トランペットとエフェクトといえば、ニルス・ペッター・モルベルが思い出されるが、ジョン・レイモンドはそれをはるかに更新している上に、ニルス・ペッター・モルベル的な<ECM>的なサウンドとは違う感覚の表現を掴み取っていたのが素晴らしいのだ。つまりもっと柔らかくメランコリック。シガーロスが表現するようなエアリーで柔らかい感触の音像と音響を、北欧/ヨーロッパではなくアメリカの情景として奏でられるとでも言えばいいか。ジャズにおける管楽器の表現にはまだまだ可能性があると思わされたそのライブの一端は確実にこのアルバムにも封じ込められている。
Freelance『Yes Today』

黒田卓也『ジグザガー』に参加していたサックス奏者クレイグ・ヒルが参加しているバンドがデビューということで見てみたら、ドラマーはエスペランサ・スポルディングや今、話題のR+R=NOWにも起用されているドラマーのジャスティン・タイソンも参加していて、びっくり。
そして、音を聴いてまたびっくりなのが、今、聴きたい感じの70~80年代テイストのメロウなファンク~フュージョン的なサウンド。とはいえ、サンダーキャット的なコズミックなサウンドでもなく、ロバート・グラスパー・エクスペリメント『ArtScience』とも微妙に違って、ロバート・グラスパー以降のヒップホップ系譜の現代ジャズの感性を持ちながらも、もっとオーガニックでゆったりしていて、どこかサンプリング・ネタっぽいテイストがあるのが絶妙。
本人はアース・ウィンド&ファイアと言っていて、あー、確かに。EW&Fやモーリス・ホワイトのカリンバ・プロダクション、スティービー・ワンダーや、ロイ・エアーズ、ドナルド・バードあたりのジャズやソウルやファンクが入り混じっていたところ、曲によっては、ブラジル音楽に傾倒していたころのジョージ・デューク周辺やAzymuth、Seawind、ディスコ期のマルコス・ヴァ―リとかの雰囲気があったり。USのミュージシャンのフィジカルな魅力とセッション感はそのままに、レアグルーヴ~アシッドジャズ期のUKの感覚が入り混じったようなこの感じは、USではあまり聴けないサウンド。ジョン・コルトレーンの「A Love Supreme」をいじった「A Love So Cream」には笑った。
本作はREVIVE MUSICによるレーベルからのリリース。現代ジャズ最重要メディアのREVIVE Musicは近年ブルーノートとコラボしたり、音楽レーベルとしての活動も始めていて、オーティス・ブラウンⅢ『The Thought Of You』、ブランディー・ヤンガー『Wax & Wane』などにREVIVEのロゴが入っていた。これらの作品には、過去のジャズのサウンドを巧みに再解釈した雰囲気があった。特にフリーランスと、ブランディー・ヤンガーはヒップホップのサンプリングソースの雰囲気を新たなミュージシャンにより再提示しているようにも思えるし、それはそれぞれのアートワークにも示されている。これもジャズ史の見直しのひとつと考えると、見逃せない動きだと僕は思っている。
■柳樂光隆
79年、島根・出雲生まれ。ジャズとその周りにある音楽について書いている音楽評論家。「Jazz The New Chapter」監修者。CDジャーナル、JAZZJapan、intoxicate、ミュージック・マガジンなどに寄稿。カマシ・ワシントン『The Epic』、マイルス・デイビス&ロバート・グラスパー『Everything's Beautiful』、エスペランサ・スポルディング『Emily's D+Evolution』、テラス・マーティン『Velvet Portraits』ほか、ライナーノーツも多数執筆。