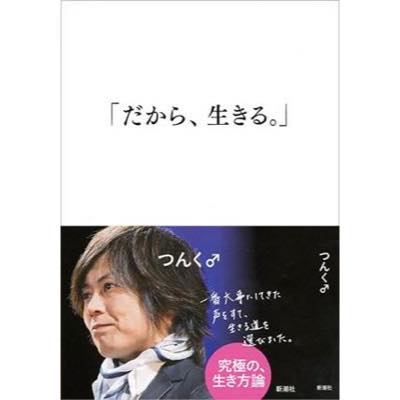『Music Factory Tokyo』スペシャルインタビュー
アイドル楽曲の“キャッチーさ”はどう生まれる? AKB48G、ハロプロ、でんぱ組.incなど手掛ける人気作家・板垣祐介が解説

音楽を創る全ての人を応援したいという思いから生まれた、音楽作家・クリエイターのための音楽総合プラットフォーム『Music Factory Tokyo』が、AKB48グループ楽曲の作編曲や、モーニング娘。、Berryz工房、℃-ute、アンジュルム、といったハロー!プロジェクトの編曲、でんぱ組.incではライブでのギター演奏や「ORANGE RIUM」の編曲を手掛ける板垣祐介のインタビュー記事を公開した。
同サイトは、ニュースやインタビュー、コラムなどを配信し、知識や技術を広げる一助をするほか、クリエイター同士の交流の場を提供したり、セミナーやイベント、ライブの開催など様々なプロジェクトを提案して、未来のクリエイターたちをバックアップする目的で作られたもの。コンテンツの編集には、リアルサウンド編集部のある株式会社blueprintが携わっている。リアルサウンドでは、今回公開されたインタビューの前編を掲載。インタビュー前編では、彼のキャリアを紐解いたほか、楽曲の気持ちよさ、キャッチ―さの陰に隠れた切なさなど、サウンドの核に迫った。
「結果として『Aメロがサビでもいいよね!』と言ってもらえるものを目指している」
――板垣さんが楽器を始めたきっかけは?
板垣:中学校3年生のときに音楽の授業でフォークギターを習ったことですね。そこでギターの面白さを知り、自宅に母がもともと使っていて、眠ったままになっているギターがあったので、それを触るようになりました。
――お母さまもギターが得意だったのでしょうか。
板垣:いえ、まったく。ギターはフォークソングのブームのときに少し触っていたらしいのですが、もう弾けなくなって物置にしまっていたそうです。そうこうするうちに友人内でもエレキギターを持つ人が出てきたので、それに影響されて自分もエレキを買いました。
――すぐエレキギターへ移行したのですね。当時はどんな音楽を聴き、また演奏していたのでしょうか?
板垣: X JAPANから入って、BON JOVI、Mr.Big、Aerosmithといった王道のアメリカンロックへと進みました。そこからさらに、速弾きのギタリストを追いかけるようになって、コピーをするようになって。
――バンドを組んだり、オリジナルの楽曲を作ったりはしなかったのですか。
板垣:バンドは組んでいたのですが、コピーばかりでオリジナル曲は作っていませんでしたね。高校生のときは洋楽のコピーバンドで文化祭に出るくらいで。ギター自体も独学だったのですが、「スタジオミュージシャンになりたい」という思いを抱えたまま大学に進学し、そこで町のギター教室に通い、初めて人から習うことにしたんです。ここではジャズやフュージョンなどの理論を学びました。
――なぜステージに立つバンドマンではなく、スタジオミュージシャンになりたいと?
板垣:音楽はやりたかったし、ギターは弾きたかったのですが、あまり表に立ちたくなくて(笑)。裏方で職人的な仕事をするギタリストに憧れていましたね。バンドでメジャーデビューをしようという気持ちはあまりなかくて、そのまま就職活動もせずに大学を卒業。しばらくは、バイトをしてギターを習って、サポートの仕事を受けて……という感じで生活していました。
――なるほど。そこからすぐに音楽作家の道へと進むことになると思うのですが、どのような転機があったのでしょう。
板垣:オファーをいただいてサポートの仕事をしていくなかで、23歳くらいのときに、あるユニットのサポートをし始めて。そのまま流れでアレンジャー兼ギタリストになって、ここでようやく打ち込みを勉強し始めました。機材もないし、DTMの知識もなくて、見よう見真似でやっていたので、今でもそのやり方が正しかったのか自信はありません(笑)。そのときはまだ曲はかいていなくて、ボーカルの子が作詞作曲をしていました。僕は楽曲のアレンジをして、自主制作CDのようなものを作って、路上ライブで手売りをする…ということをしばらく続けましたね。
――ちなみにこのユニットではどのような音楽を?
板垣:女性シンガーソングライターで、アコギを弾きながら歌うような曲が多かったです。ただ、当時はSheryl CrowやMichelle Branchなどの洋楽シンガーが流行っていたので、 “Jポップど真ん中”というよりは、ちょっと洋楽テイストな音楽をやっていました。
――その経歴から、どうやって音楽作家への道が拓けたのでしょうか。
板垣:ユニットで事務所に所属してメジャーを目指したのですが、デビューには至らなくて。当時は25歳で、ギターの仕事もあまりなかったし、バイトも相変わらずやり続けていたところに、作家事務所で働いていた友人から「作家として曲を作らないの? もし作ったら聴かせてよ」と声が掛けてくれて。当時は作家の事務所があることも知らなかったのですが、それで数曲を提出したら、すぐにコンペを通過してしまって。それならうちの事務所に来なさいよ、という話になって、本気で曲を作り始めました。
――事務所へ所属し、Jポップの仕事が増えてからは楽曲の作り方が変わりましたか。
板垣:そこまで変わっていないですね。基本的には鼻歌から始めて、伴奏を付けて、という流れです。散歩をしたり、シャワーを浴びたりしながら口ずさんで出たメロディーのうち、自分でいいなと思ったものをiPhoneなどに録音しておいて、そのなかから使えそうなものを膨らませて曲にします。もちろん、ギターを弾きながら鼻歌でメロディーを作るようなときもありますし、ピアノを爪弾きながらメロディーを考えるときもあるんですけど、なんとなくではなく、わりと「曲を考えよう」と思って作るときが多いです。
――作家として活動されてきた中で、明確にステップアップしたターニングポイントを挙げるならどこでしょうか?
板垣:打ち込みのスキルや音色のジャッジなどは時間をかけて学びましたが、感覚的なところでいうと、今リリースされて流行っているような曲を一通り聴いて、「どんな音色が受けるのか」を研究したことですね。女性アイドルや男性アイドルの、キャッチーかつ王道でカラオケでも歌いやすそうな曲を分析したり、かなりの曲数を聴いて自分の中にエッセンスとして取り込んだり、コード進行のコピーもしました。僕自身、1990年代半ばに<Being>がリリースしていたような楽曲はよく聴いていましたし、メロディーラインに関しては、それが今でも根底にあるのかもしれません。
――板垣さんの音色からは、確かに織田哲郎さんを思わせるテイストも感じます。
板垣:まさに織田さんが大好きでしたし、ZARDさんやB’zさんも聴いていました。これらの楽曲から、自分の中でのメロディーの持っていきかたや、「これを言えば気持ちいいだろう」というフレーズの感覚を学んだ、ということは言えますね。
――その「気持ちよさ」はどういう基準なのでしょう。
板垣:あえて言語化すると、「自分が歌いやすい」ということですね。僕自身はあまり歌が上手ではないので、「そんな自分が歌っていていいメロディーだと思えるなら、一般の人にとっても親しみやすいだろう」という風に一つの基準を設けています。
――ほかにベンチマークとした作家さんはいますか?
板垣:織田哲郎さんなどのJポップを聴いていた時期を経て、しばらくは洋楽を好んで聴くようになっていました。作家活動を始めるようになってから、その空白の時間を取り戻すために、1990年代~2000年代のJポップを聴くようになりました。琴線に触れたのはMr.Childrenさんやスピッツさん。とてもいいメロディーで、心にグッとくるものがあったので、当時は自分もそういう楽曲を志向していましたね。あとは、キャッチーなジャニーズ系の音楽、SMAPさんやKinKi Kidsさんもよく聴いていました。