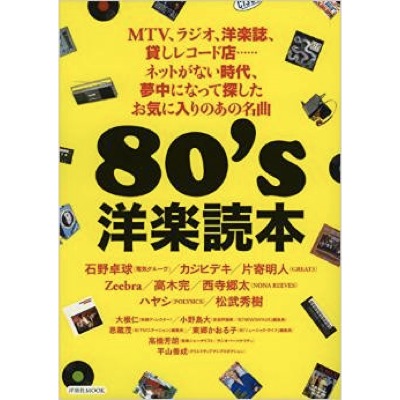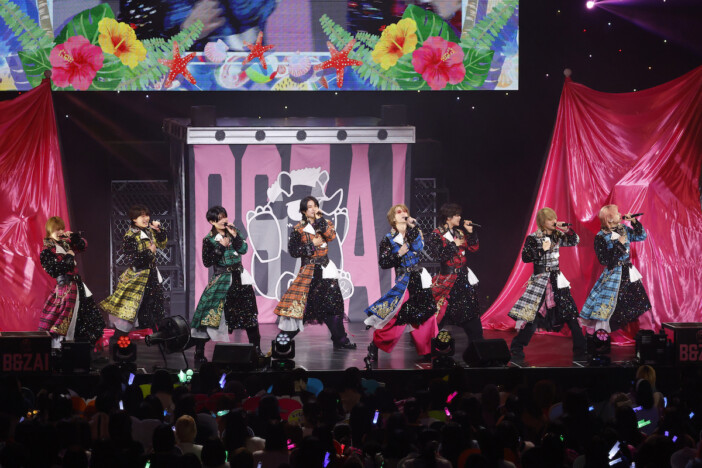市川哲史の「すべての音楽はリスナーのもの」第29回
オックスフォードの轟音牧童・ライドが再結成 市川哲史が彼らのキャリアを振り返る
呆気なく解散してしまう1996年初頭まで、ライドとの付き合いは続いた。1993年春に私もROから独立したけれど、その後も最後までアルバムのライナーノーツは執筆した。
日英問わず何度もインタヴューしたが、彼らは最後まで「普通」のことしか言えなかった。以下は、マーク・ガードナー(g,vo)の発言だ。
「本当に普通の村の子だったから(苦笑)。とにかく内向的で、僕のレコード・コレクションは大切な友だちに他ならなかった。レコードの唄に、僕が当時感じてたことがすべて包括されてたんだよね。スミスとかエコバニとか、育ち盛りだっただけに受けた衝撃も大きかったよ? とにかくリアルだった、キュアーもニュー・オーダーも」
「僕たちにとっての音楽は極端な話、外界をシャットアウトできるバリアーみたいなものなんだ。個人的な負い目や劣等感による報復手段では決してないよ」
このヘタレならではの美学は、たしかに素敵だ。しかしこの発言の陰に、どれだけの普通の言葉が積み重ねられていることか。
「僕たちは自分たちがやりたい音をやって、結果こういうレベルに達しただけで――自分自身を愉しませてるに過ぎないんだけど、それが単に『他人にも聴かせて愉しませたい』と変わっただけの話でさ(微笑)」
私がそれまでインタヴューしてきた外タレたちは皆、イカれていた。
日本人を未だジャップ扱いする尊大過ぎる英国人。自分がいかに赤貧かとうとうと語るポップ親父。午前11時なのに金髪の姉ちゃん連れてベロンベロンで現われ、寝転がって話してたものの開始5分で「気持ち悪ぃから帰る」と、バンドに加入したばかりの若造1人残していなくなった米国南部男。電話の向こうで「今夜はパーティーにお呼ばれしてるの。ばあや! ばあや!」とシャワーを浴びてた自由な米国人お嬢。こんなの序の口だ。
しかも国産ロックバンドも躍進するにつれて、さまざまなキャラが咲き誇り、言葉による自己主張が個性的な連中も増えてくる。イジればイジるほど面白いし、叩けば埃の出る奴も珍しくない。だって日本語が共通言語だもの。
そうなのだ。私はライドと出逢ってようやく、洋楽コンプレックスが解消されたのだ。
彼らのフェティッシュな轟音ギター・サイケは、問答無用で恰好よかった。しかし見栄えはぱっとしない普通の少年で、話す内容も概ね普通。
商売に走らない。他人を誹謗しない。ロックスターに執着しない。大言壮語しない。眼中にあるのは音楽だけ。万年思春期であるがゆえの純粋培養の音と言ってしまえばそれまでだが、それ以外の<カリスマ性ゼロ>感が衝撃的だったのである。
「なんだ、日本のミュージシャンの方が話面白いじゃん」
「なんだ、ごくごく普通の少年でイカレてなくても恰好いいロックできるんじゃん」
目からウロコというか洋楽の呪縛からの解放というかライド以降、私はキース・リチャーズだろうが鬼龍院翔だろうが相手を問わず、失礼極まりないインタヴューに邁進できるようになった気がする。本音の交換に国籍も年齢も関係なく、遠慮は無用なのだと。
それにしても揃って45歳になったライドの四人の、なんと老け込んだことか。
なまじ20歳の姿を知ってるだけに容姿の老化がより目につくのだろうが、今回20年ぶりに再会したらきっと「あんたに言われたくはない」と失笑されるに違いない。
ふ。
■市川哲史(音楽評論家)
1961年岡山生まれ。大学在学中より現在まで「ロッキング・オン」「ロッキング・オンJAPAN」「音楽と人」「オリコンスタイル」「日経エンタテインメント」などの雑誌を主戦場に文筆活動を展開。最新刊は『誰も教えてくれなかった本当のポップ・ミュージック論』(シンコーミュージック刊)