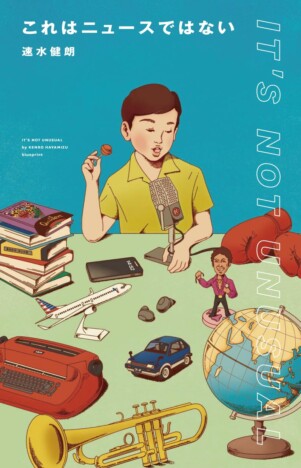「スコラ 坂本龍一 音楽の学校 シーズン4」第12回
坂本龍一ら『スコラ』で第二次大戦後の音楽を考察「音楽を科学に近づけたいという衝動があった」
いっぽう、第二次世界大戦後のアメリカ音楽においては、ジョン・ケージが全く別の方法で、音楽から情緒的要素を取り除く音楽を発明した。坂本はこのことについて「ジョン・ケージは西海岸の生まれで、当時西海岸に亡命していたシェーンベルクの門を叩いた」と、彼の原点はヨーロッパ音楽にあることを紹介すると、続けて浅田が「ドイツ・オーストリア音楽の中核を20世紀化したものを受け取ると同時に、日本の鈴木大拙を通じて禅を学び、『あるがままの自然をそのままに置いておけ』という思想を受け取った」と、彼の音楽が日本の禅と結びついていることを指摘。坂本は「シェーンベルクのレッスンを受けていて、『この先には音楽の可能性はあまりないな』と感じ取り、彼独自の『チャンスオペレーション』を作った。これはヨーロッパの音楽家にとって脅威だった」と、ケージがヨーロッパ音楽とアメリカ音楽の垣根を越えた存在であったことを語った。
同番組では、ケージの音楽的功績として「易の音楽」と「4分33秒」の2曲を紹介。「易の音楽」は、古代中国の占いの方法に習い、音の高さ、長さ、強弱を3枚のコインを投げることで決め、作曲されている。こうした手法は「偶然性の音楽(チャンスオペレーション)」と呼ばれ、その後の作曲家に大きな影響を与えた。さらに翌年、ケージは全く「4分33秒」という曲で、新しい音楽の概念を提示する。楽譜は3楽章に分かれていながら、それぞれに「楽章にわたり休止」の指示がされており、聴衆を前にした演奏家はストップウォッチで4分33秒を計測するものの、その間楽器の演奏を行わないという斬新な曲だ。
「4分33秒」について浅田は「4分33秒ということは273秒。これは絶対零度の数字(-273℃)であるわけで、音のない絶対零度の空間に、観衆はざわざわしたり、外から鳥の声が聞こえたりする『借景の音楽』があった」と、ケージがこの曲に込めた思いを代弁すると、岡田は「もう一つ、忘れてはいけないのが、ヨーロッパの音楽というのはきわめて人工的だということ。彼らにとっては蝉の音やスズムシの音は一種のノイズであるのに対して、ケージの音楽はノイズかどうかも無効にしようという発想があったかもしれない」と、ヨーロッパ音楽とケージが作る音楽の違いについて語った。続けて坂本が「ケージは、音楽というのは『音』と『沈黙』の2つだと言っている」と語ると、浅田が「『ケージは何でもありなんですか?』となるが、実は厳格な枠がある。あまり、なんでもありの前衛音楽家と思わない方がいい」と、一見なんでもアリに見えるケージの音楽にも、一定の法則性があることを指摘した。
音楽を体験しながら学ぶ「スコラ・ワークショップ」では、図形を楽譜として捉えて作曲するというテーマを、坂本が小沼と共に解説した。この手法は、1950年代にケージらが用いたもので、参加した3人の作曲を学ぶ大学生にも、今回同じ方法で作曲をしてもらった。折り鶴の展開図を用いた作曲や、ペツォルトの「メヌエット」という既存の楽譜の縦横を入れ替えて再構築したもの、ヒマラヤ山脈の衛星写真から作曲したものなど、数多くのアイデアが学生から飛び出し、坂本も「これは思いつかなかった。みんな将来が楽しみだ」と、学生たちを称えた。
後半では「伝統的西洋音楽からの脱却」として、同番組では建築家でもあった音楽家であるヤニス・クセナキスを、量子力学以降、原子や電子などの世界では、運動量と位置などを同時かつ正確に測定することは不可能であるという「不確定性原理」を音楽に持ち込んだ存在として紹介。楽譜を方眼紙に書くという、建築家ならではの技法を使ったクセナキスは、音の響き全体が音楽であるという技法を確立した。
トークの最後では、坂本が「70年ごろにあったミニマリズムの音楽が、一つの袋小路かなと思っている。ちょうどその時僕も20歳くらいで、音楽を習っていて、『ここがいよいよ西洋音楽のなれの果てかな』と深く感じていたのを思い出す。でも音楽は人間がいる限りあるわけだから、形が変わっても続いていく」と、番組を総括した。
番組の最後には、ブーレーズのノタシオンを演奏。12の短い曲で構成されている同曲は、特定の12音からなる音列に基づいて作曲されており、十二音技法を確立したシェーンベルクやヴェーベルンの影響を受けているものだ。
今回は第二次世界大戦後の音楽について、深く解説した同番組。シーズン4は今回で最終回となり、次週からは全く異なるジャンルの同世代の2人が「人生」と「音楽」について語り合う『ミュージックポートレイト』のシーズン4が放送される予定だ。
(文=中村拓海)