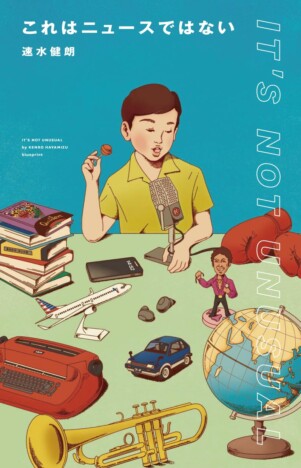「スコラ 坂本龍一 音楽の学校 シーズン4」第12回
坂本龍一ら『スコラ』で第二次大戦後の音楽を考察「音楽を科学に近づけたいという衝動があった」
世界的音楽家・坂本龍一を講師に迎え、音楽の真実を時に学究的に、時に体感的に伝えようという『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』(NHK Eテレ)のシーズン4・第12回が、2014年3月28日に放送された。
3月期のテーマは「20世紀の音楽」。ゲスト講師には前回同様、小沼純一、岡田暁生、浅田彰を迎えて放送された。テクノロジーの発達や2度の世界大戦で、世界が大きく様変わりし、音楽という概念が大きく揺れ動いた20世紀。その中でも今回は「第二次世界大戦後に生まれた新たな音楽」について講義した。
1939年~45年に渡って、世界中に多大なる影響を与えた第二次世界大戦。戦後、ヨーロッパとアメリカでは新世代の作曲家により、音楽の新たな可能性を模索する動きがみられた。今回の放送では、音楽そのものの概念が大きく変化したこの時代における、ヨーロッパとアメリカの音楽事情について、ピエール・ブーレーズ、ジョン・ケージ、ヤニス・クセナキスという3人の作曲家を通じてその歴史が語られた。
まずは坂本が、第二次世界大戦後のヨーロッパ音楽について「音楽技法的に言うと、戦前までの大きな流れだった十二音技法がシステム化され、トータル・セリエル(総音列)技法というものが生まれた」と、その特徴を挙げた。続いて、浅田が「ブーレーズという人がとても象徴的で。1925年生まれで三島由紀夫らと同じ世代。終戦時に20歳を迎えるというのは、全て壊滅していると同時に全く新しいタブラ・ラーサ(白紙の状態)が目の前に広がっている。『全面的音列音楽』である総音列技法はそこから生まれたものだ」と、大戦後の若手音楽家が「総音列技法」を用いて、音楽の歴史を変えたとした。
総音列技法(トータル・セリエリズム)というのは、音の高さ、長さ、強さなど、音に関する要素それぞれに対して、ある規則をあてはめ、作曲するというもの。この技法について浅田は「シェーンベルク、ヴェーベルンを引き継いで、音の高さだけではなくて、音色の繋がり方や強弱、リズム、長い音符や小さい音符の全部をシリーズとして考える。数学の塊みたいなものを作っちゃう」と紹介。坂本がそれに補足するように「しかも、演奏をするのが非常に困難ということで、シュトックハウゼンなどの電子音楽家が登場してくるという流れを作った」と、後世への影響も語った。
岡田はこの時代におけるヨーロッパの音楽家がもつ特徴として、「音楽を限りなく科学に近づけたいという衝動があったと思うし、ほとんど憑りつかれているような感じがする。操作性、科学性、分析性。こういうものを一言でいえば『音楽は娯楽じゃない』と考えていたということ。それには第二次世界大戦における科学の限りない暴走が影響しており、ブーリーズの中にも『音楽も何らかの形で科学と対決しないかぎり、芸術として存続が危うい』という意識があったのではないか」と語り、「科学の戦争」と呼ばれた大戦以降、音楽と科学を密接に考えることは必然だったという考えを話した。小沼もこれに続いて、「相当、ナチスドイツというかファシズムが持っている情念的なものに対するアンチテーゼ。情念とかロマンチシズム主義から離れて、知的に、頭でものを考える音楽の作り方があった」と語った。