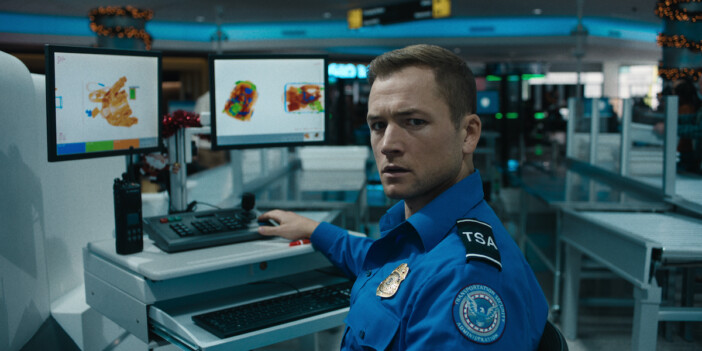イ・ビョンホンの“最高”がここに 『スンブ:二人の棋士』は囲碁が分からなくても面白い!

これはどうしようもないことなのだが、やはり時々、Netflixの配信限定の作品を観て「これは映画館で観たかったな」と思わされることがある。
VFXで「地球に巨大ロケットをつけて太陽系脱出」という壮大な絵面を実現させた中国の熱血SFディザスター『流転の地球』(2019年)や原作ゲームを完全再現して派手というには途方も無さすぎるアクションを魅せる『真・三國無双』(2021年)など。最近では『ザ・レイド』(2012年)のギャレス・エヴァンスが苛烈なアクションでネクストレベルを目指した『ハボック』(2025々)が「映画館で観たかったなあ」と思わされた。しかし、派手でアクションのすごい映画だけが映画館の価値じゃない。
Netflixで5月8日に配信された『スンブ:二人の棋士』は本当に映画館で観たいと思わされた。アクションがすごいからではない。VFXが派手だからでもない。理由はシンプルにひとつ。面白いからだ。

囲碁の世界選手権大会「応昌棋杯」に優勝して世界トップ棋士に輝いたチョ・フニョン(イ・ビョンホン)は多面打ちの指導対局で囲碁を始めて半年ながら「神童」と呼ばれる少年イ・チャンホと出会う。チャンホの才能を見込んだフニョンは棋士として脂ののった時期でありながら、チャンホを内弟子(住み込みの弟子)として迎え入れる。全盛期の棋士が内弟子をとるのは異例のことであった。共に暮らし、共に囲碁を打つ日々を過ごす二人の師弟。やがて少年は青年となり、フニョンを脅かす最大のライバルへと成長する……。
Netflixで連日「今日の映画TOP10」にランクインを果たす『スンブ:二人の棋士』は韓国の囲碁界を舞台に、二人の師弟を描く実話に基づく映画だ。囲碁を題材にした映画というのはそれほど多くない。それこそ韓国バイオレンスと囲碁を融合させた唯一無二の傑作映画『神の一手』(2014年)、『鬼手』(2019年)や、草彅剛と國村隼のブロマンスをやりつつ囲碁を打つし人も斬る『碁盤斬り』(2024年)など、ないわけではないが見ての通り囲碁・ミーツ・バイオレンスな映画ばかりだ。だが、『スンブ:二人の棋士』は実話映画であり、暴力は存在しない。ただシンプルに囲碁、そして二人の棋士の対決を描いた作品である。
囲碁、実話、要素だけ並べ立てると地味に思える。では、『スンブ:二人の棋士』は何故おもしろいのだろうか? 簡単な話である。優れた題材に優れた脚本。優れた演出に優れた演技。そして優れた劇半。当たり前のようで難しい話だが、映画を構成するすべての要素が優れていれば、表面的な要素はなにであれ映画は陶酔するような面白さになる。
「師弟であり、棋士として最大のライバル」というマンガみたいな筋書き(これで本当に実話なのだからすごい)は観客の興味を引きつけ、効果的な劇伴が感情と心拍数に寄り添う。演出は無駄がなく、的確。確かに『スンブ:二人の棋士』は一見地味に思える。だが派手さがないからといって、決して地味であることを意味しない。むしろ『スンブ:二人の棋士』においては「研ぎ澄まされた」と表現したほうが正しい。本作は人間ドラマではあるが過剰なドラマチックさは排し、二人の棋士と囲碁を物語ることに焦点を絞っている。だからこそ映画というメディアの根本にあるような、技術力の太さを感じることができる。
ここまで読者が記事を読んでいてくれていたとして、そろそろこのような疑問が頭に浮かんでいるはずだ。「囲碁のことはよく知らないんだけど、この映画は楽しめるの?」と。ご安心を。まず筆者に囲碁の知識はない。小学生時代に『ヒカルの碁』を読んでいたくらいだ。それでも『スンブ:二人の棋士』は面白い。それどころか、対局シーンであっても手に汗を握るほどの緊張感を与えてくれる。
なぜ囲碁のルールがわからなくても対局シーンが面白いのか。これに関しては先ほど述べたことの繰り返しとなる。効果的な演出、効果的な劇半。時々映画は本当に科学的なものなんじゃないかと思わされる。ルールのわからない対局を観ているのに脳が機械的に快楽物質をまろび出す。どのようにカメラを配置し、どのようなリズムで編集すれば人の脳を喜ばすことができているのか把握しているような技巧に優れた演出が本作にはある。筆者はこれを「ケミカルな面白さ」と呼んでいるが、人によってはあまり褒め言葉にならなそうなので個人の感想であると主張しておく。