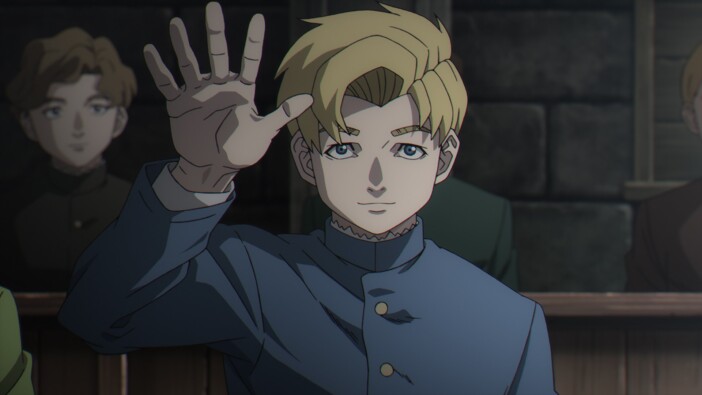『天久鷹央の推理カルテ』“医療ミステリ”の映像化はなぜ成功した? ジャンル的問題の解決

知念実希人の人気シリーズを原作とするアニメ『天久鷹央の推理カルテ』(以下『あめく』)が現在各種放送局やストリーミングサービスで放送・配信されている。原作は新潮文庫nex(現在は引き継がれて実業之日本社文庫)から刊行され、漫画化やジュニア文庫化も果たしながら幅広い層の読者を獲得しているシリーズである。
本作を含め「医療ミステリ」というジャンルは小説や実写映像作品においては以前から人気だが(それこそ医者である知念実希人による別作品『祈りのカルテ』はドラマ化、帚木蓬生『閉鎖病棟』は映画化されているし、『MIU404』(TBS系)とともに社会現象となった『アンナチュラル』(TBS系)は解剖医を主人公としている)、ことアニメに関してはあまり同ジャンルの作品が生まれてはこなかった。そんな中で『あめく』は、医局内の権力闘争を描いたり単独の連続殺人犯や事件に焦点を当てる多くの「医療もの」とは異なり、数話ごとに独立して発生する不可解な病気や事件を主人公の幅広い能力や知識を通して解決していく構成になっており、さまざまな面で挑戦的といえるアニメ作品である。
ところで、先日Blueskyを見ていたところ、品田遊(ダ・ヴィンチ・恐山)氏の呟きに目が留まった。
医療ミステリって、急に読者が知らない知識が出てきてそれで解決するのに許されててすごい。(※1)
確かに医療ミステリは専門外の読者にはおよそ考えられもしない用語や知識が頻繁に出てくるし、それを用いて知らない間に謎が解決してしまうことも少なくない。それを考えると、『あめく』もミステリの定義やルールから大きく外れてしまっているように思える。この医療ミステリというジャンルの特殊性からくる「ミステリらしくなさ」の問題に対し、『あめく』がどのようにして自分をミステリたらしめることに成功しているのかを、「論理」と「形式」というふたつの側面から考える。
『あめく』のジャンル的問題

まずは『あめく』の問題点、つまり「ミステリらしくなさ」の正体が何なのかを具体的に考えたい。
これまでミステリというジャンルでは何がミステリであるか、いわばその線引きやルールについて作家や批評家たちの間で多くの論が交わされてきた。その中でも広く同意され共有されている有名なものに「ノックスの十戒」や「ヴァン・ダインの二十則」といったものがある(※2)。余白の都合からここでは大半を省略するが、本記事と関係の深いもののみいくつか引用すると、
未発見の毒薬、難解な科学的説明を要する機械を犯行に用いてはならない。(十戒)
探偵は、読者に提示していない手がかりによって解決してはならない。(十戒)
事件の謎を解く手がかりは、全て明白に記述されていなくてはならない。(二十則)
といったものがある。これらのルールを見ると、『あめく』において真相解明にあたり専門的な医学的知識を必要とし、視聴者の預かり知らないところで話が解決してしまう天久鷹央の推理は一見して反則であるように見える。
こういったルールを守らずに「ミステリ」をすることは可能だろうか? 実際のところ、この種の「戒律」は厳密に運用されている訳ではなく、縛りとしてよりはあくまでもフェアであるための目安として存在する。こういった要素に露骨に反すると読者・視聴者などに対して卑怯、という作り手の意識の問題ともいえる。とはいえ、文字通り受け取られるのではないにせよ、作り手の前提として公平さが求められるあたりこの「フェアネスの原理」とでも形容すべき考え方はやはりミステリに必須の要素だといえる。

逆に、こういった考えやルールを意図的に無視する、破る、または逆手に取る作品も多い。それらは奇抜さやサスペンスの手段として「謎」を利用しているだけでそもそもミステリを志していない(初期の『ガリレオ』シリーズなど)か、ミステリに対する逆張りや批評、つまりアンチ・ミステリやメタ・ミステリとして書かれているかのどちらかであることが多い(『見晴らしの良い密室』『ディスコ探偵水曜日』など)。いわゆる特殊設定ミステリでも基本的にこれらのルールは遵守されており、例えば2020年にミステリ作家の舞城王太郎が脚本を務めたことで話題になったアニメ『ID:INVADED イド:インヴェイデッド』でも犯人の殺意から構築される世界に潜入するという大胆で特殊な設定が登場するが、作中での推理はおおむね上記の法則に反さない形で描かれている。
したがって『あめく』のような医療ミステリも正しくミステリたるには「フェアネスの原理」に則ったかたちで推理が展開される必要がある。言い換えるならば、上に述べた「ミステリらしくなさ」の原因は主にこの「形式」上の問題である、ということが分かる。
医療ミステリにおける真相解明の論理

ここで一旦「ミステリらしくなさ」=「形式」の問題に迫る前に、「ミステリらしさ」=「論理」のほうに着目してみよう。
『あめく』の主題である「医療」とは実際のところどのようなメソッドで行われるものか。診察という行為は医者が患者の様子を観察し、症状や普段の習慣などについてやり取りする中で病気に関する知識や患者についての前提的な理解を得てゆき、それらから消去法的に患者の病気を推察し、適した療法・処方を提示する一連の作業だといえる。
この臨床診断のプロセスに着目してみると、その構造がミステリにおける推理とよく似ていることが分かる。医者は「謎(=患者、病気、怪我など)」に対する知識がゼロの時点からスタートして、カルテや病歴を参照し、患者との(触診や検査などの非言語的なものを含めた)コミュニケーションを通して「謎」を解明していく。患者は必ずしも正直に答えてくれるとは限らないし、人体には類似した機能や症状が多く、ミスリーディングな結論=誤診に誘導されてしまうことも少なくない。前提条件が非常に多い中で繰り返し観測と選択肢の排除を重ねることで、医者はさまざまな分野のアプローチを検討し、次第にひとつの結論とそれをもとにした治療メソッドの提案へと至っていく。
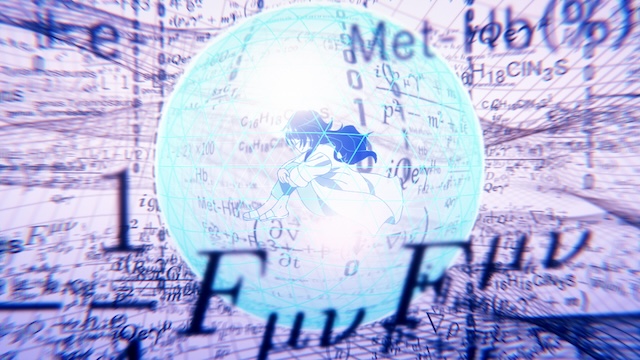
とりわけ『あめく』において、天久鷹央が所属する統括診断部は特定の医学的分野に囚われずにあらゆる可能性を考慮して診断を下すための部署とされている──密室殺人において現場や登場人物のどんな細かい要素をも無視してはならない探偵のように。また、その名の通り統括診断部はあくまで「診断」を下すことを主目的とする部署であり、病名が判明したあとの処理、つまり治療にはあまり関わらない。この点でも実に探偵向きというか、真相解明以降の逮捕や裁判には直接関わらない探偵と通じるものの多い仕事だ。
要するに、『あめく』は真相解明に関して、ミステリ作品における探偵と全く同一の論理とメソッドを用いて取り組んでいる、といえる。「フェアネスの原理」のためのルール的な「形式」を守らずにミステリとして成立している(と考えられている)作品は、主にこのような謎解きの「論理」によって推理ものとしての性質──「ミステリらしさ」を表現している。
アニメだからこそ成立する医療ミステリ

インターネットの普及以降、「形式」という言葉は頻繁にメディア(媒体)の種類を指す枕詞として使われているが、「媒体」の類義語として捉えられるこの文脈での「形式」の解釈は『あめく』を理解するヒントにもなっている。小説を原作としていて、かつ漫画としても展開されているにも拘わらず、本稿でわざわざアニメ版の『あめく』に注目しているのには理由がある。結論から言えば、手がかりの置き方が他のメディアとは必然的に異なるものになってしまうからこそ、本作は独自の方法で謎解きのシステムを再構成し、微妙な立場にある医療ミステリをミステリたらしめているのである。
アニメという媒体は非常に受動的だ。画面の前に座ってテレビやパソコンを点けっぱなしにしておくだけでいいし、疲れているときにはそのまま眠ってしまうことだってありえるくらい、視聴者の側からの積極的な働きかけを必要としない。それでいて映画などと並んで総合芸術と形容されるほど作品を構成する要素が多く立体的で複雑に絡み合っている。だからミステリや謎とも別のやり方で関係しなければならない。

小説の場合、手がかりは全て文章として明瞭に紙面の上に載せられているため、一読してその要素が存在することが認識できるし、一度でも紙面に載った要素は手がかりと認められる。叙述トリックのような工夫はあっても、書かれた内容に嘘はあってはならないし、読者が読み飛ばすように書いてしまっていてはフェアでないような印象を読者に与えてしまう。
しかしアニメの場合、視聴者は例えば背景に映る看板の文字や登場人物の服装の細部といった全ての要素を把握する訳ではないし、作劇に際してもその事実を前提としなくてはならない。つまり、形式からしてそもそもアニメはフェアではないのだ。とりわけ医療というテーマを扱う『あめく』の場合、初見で意識の向かないところにヒントを置いてしまっては推理のしようもない。
しかし同時に、映像上のフェアネスという要素だけを見ると、映画やドラマなどの実写映像作品にも同じことが言えてしまうのではないか、という疑問が生まれる。この二点の問題に応えるためには、アニメの記号化作用という性質に着目しなければならない。
アニメという媒体は漫画などと同様の作画上の制約から、必然的に多くのものが簡略化される。多くのものが同じ作画上の法則から簡略化された独自の自然さ、大塚英志の言葉を借りるなら「まんが・アニメ的(な)リアリズム」があり、程度の差こそあれ全てのアニメはこれに則って描かれる。
このリアリズムの制約下においては実写作品ほど露骨で我々にとって自然な感情等の表現ができないため、代わりにイメージを喚起させるさまざまな「記号」が用いられる。怒りを表現する血管のマークや焦りを表現する汗のマークなどの漫符が代表例的だが、より大胆な表現も多く存在する。
例えば山田尚子監督の『映画 聲の形』では、他人とのコミュニケーションを諦めた主人公・石田将也が周囲の人間と関係することを拒絶している様子が他者の顔の上に描かれたバツ印によって表現されている。これは大今良時による原作漫画でも用いられる演出だが、よりアニメに限定された技術を用いて記号表現を実現している作品も多い。同監督の『きみの色』では主人公の日暮トツ子が(共感覚的に)他人に「色」を見出す様子が、撮影処理における色彩加工や被せられたモノローグなどによって複層的に描かれている。