『ショーシャンクの空に』はいかにして“名作”となったのか 今こそ沁みるラストシーン
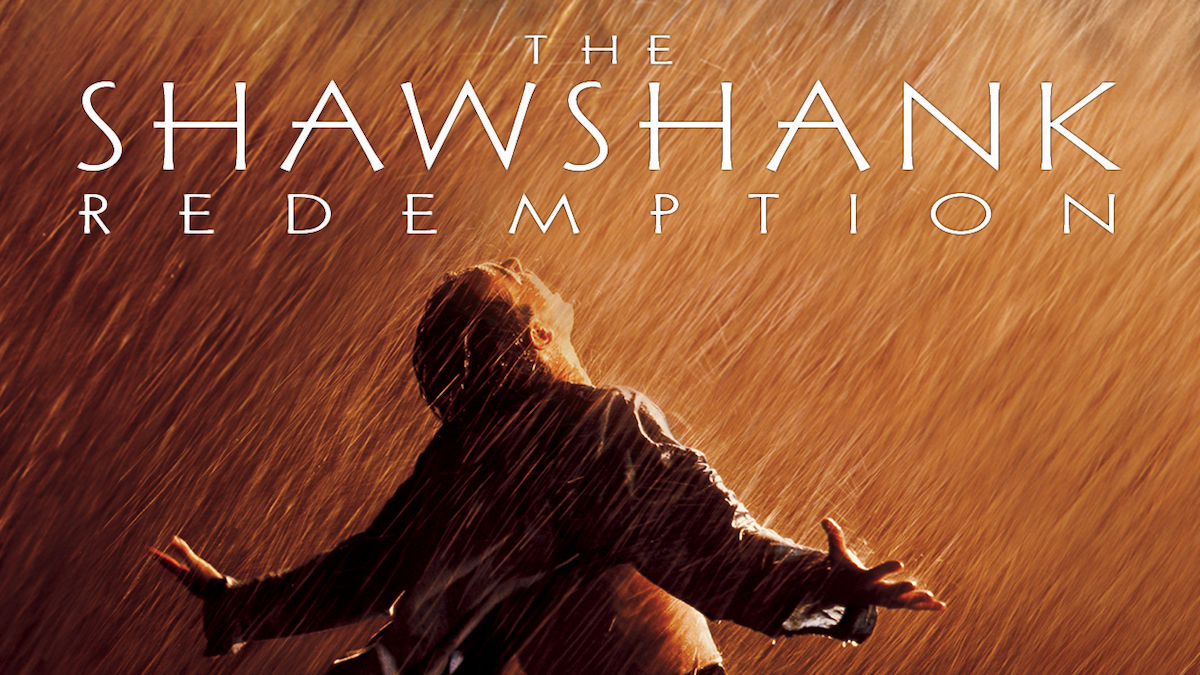
スティーヴン・キングはホラーだけの作家にあらず。そのイメージを初めて映画ファンにもたらしたのは、青春映画の金字塔となった『スタンド・バイ・ミー』(1986年)だろう。監督のロブ・ライナーは同作の成功を機に、キング作品の舞台となる架空の町の名前をとって、製作会社キャッスルロック・エンタテイメントを設立した。
しかし、映画界ではその後も相変わらず、キングはジャンル映画ファン御用達作家として重宝され続けた(著者本人が1986年の『地獄のデビル・トラック』なんていうジャンル愛まるだしの珍品で映画監督デビューしていたせいもあると思うが……)。キャッスルロックも『ミザリー』(1990年)、『ニードフル・シングス』(1993年)とホラー寄りの作品を相次いで映画化し、ようやく非ホラーに取り掛かったのが、1994年公開の『ショーシャンクの空に』だった。

監督・脚本を務めたのは、これが初の劇場用長編となったフランク・ダラボン。当時は監督としては未知数で、こんなにストレートな人間ドラマとしてキング原作を映画化できるなんて、ジャンルムービーにさほど興味がないのかとさえ思った。しかし、それ以前には脚本家として『エルム街の悪夢3 /惨劇の館』(1987年)、『ブロブ/宇宙からの不明物体』(1988年)に参加するなど、むしろ熱烈なジャンル信奉者であり、さらに筋金入りの「キング愛」の持ち主であることも後から知った。何しろ、まだ学生だったころにキングから短編小説『312号室の女』の映像化権を格安で取得し、30分のショートムービー『老母の部屋』(1983年/オムニバス『スティーブン・キングの ナイトシフト・コレクション』に収録)で早くも監督デビューを果たしているほどだ。
ダラボンはほかにもキング作品の映像化権をいくつか取得しており、そのなかに連作中編集『恐怖の四季』の一編「刑務所のリタ・ヘイワース」があった。舞台は太平洋戦争が終わって間もないころのアメリカ、メイン州にあるショーシャンク刑務所。妻と愛人を殺した罪で収監された元銀行員アンディと、刑務所内の調達屋をつとめる終身犯レッドが長年にわたって紡ぐ交流、そして大胆不敵な脱獄を描いた物語だ。言うまでもなく、ホラーではない。
これをダラボンは映画脚本として巧みに整理した。1947年から1976年まで続く原作の時代設定も60年代中ごろまでに圧縮。何度か入れ替わる刑務所長や看守のキャラクターも絞り込み、映画オリジナルのエピソードやセリフも随所に散りばめた。『暴力脱獄』(1967年)や『パピヨン』(1973年)といった「刑務所もの」の名作群からエッセンスを援用し、最終的にはジャンルに限定されない全方位型のヒューマンドラマとして作品を完成させた。そこには、キングという作家の才能をホラーファンだけでなく、もっと幅広く世に知らしめたい! という熱烈な「推しの心」もはたらいていたに違いない。
製作のロブ・ライナーとキャッスルロックは、ある時期まで本作の企画を大スターの共演作として進めようとしていた。一時はトム・クルーズとハリソン・フォードが主演候補に挙がったこともあったという。ダラボンはそれも悪くないと考えていたが、最終的にはアンディ役にティム・ロビンス、レッド役にモーガン・フリーマンという実力派キャストの起用を決めた。この時点で、作品全体の作りも大きく方向性を変えたのだろう。主演スター頼みの話題作として作れば、刹那的なヒットは見込めるが一瞬で消費される可能性も高い。しかし、ダラボンは地味だが長く記憶に残る、一切無駄のない142分の良質の映画にするという道を選んだ。新人監督にとっては大きな賭けでもあったはずだ。

実際、『ショーシャンクの空に』は批評家ウケこそ良かったものの、初公開時の興行はあまり振るわなかった。同年には『パルプ・フィクション』や『フォレスト・ガンプ/一期一会』などのトリッキーな作劇が話題を集めていたことを思えば、確かに地味で直球で落ち着きすぎていたかもしれない。それでいて刑務所映画ならではの口汚いセリフと暴力描写のおかげで北米ではR指定となったのも、興行面で不利な条件となった。
しかし、その後のソフトリリースやTV放映、アカデミー賞ノミネート後の再公開などを経て、本作は徐々に観客の支持を得ていった。いまや『スタンド・バイ・ミー』と肩を並べる名作として定着し、キング作品やホラー映画のファンでなくとも「繰り返し観る、お気に入りの1本」として挙げる人は多いのではないだろうか。ダラボンの賭けは、見事に実を結んだといえる。
日本では1995年6月、松竹東急系で全国公開された。リアルタイムで観た印象としては、なんといっても主演俳優2人の「旬」に立ち会っている感が強かった。モーガン・フリーマンは『許されざる者』(1992年)、『アウトブレイク』(1995年)、『セブン』(1995年)と代表作の公開が相次いでいる時期で、本作のレッド役も前述の作品群に引けを取らないハマり役だった。
原作のレッドはアイルランド系の白人という設定で、保険金を目当てに妻を計画的に殺した罪をのっけから読者に告白する、なかなかにヤバい男である(しかも過失とはいえ、知人の母子まで巻き添えに)。だが、映画では中年の黒人男性という設定になり、フリーマンが持ち前の落ち着きと頼もしさ、知性とユーモアをもって、ベテラン囚人を味わい深く演じている。その罪の詳細は劇中明らかにされないが、「若造のころに1人の男を殺した」ということだけが端的に語られる。人種差別がはびこる時代のアメリカで、彼が殺人を犯し、有無を言わさず終身刑を言い渡された状況、人生の大部分を塀の内側で過ごしてきた男の悔恨と諦念を、ダラボンはフリーマンの姿を通して観客にただ想像させる。原作そのままの設定では出せなかったであろう深みが、このキャスティングで見事に醸し出されている。

アンディ役のティム・ロビンスも『ザ・プレイヤー』(1992年)以降、役者として絶頂期を迎えていたころだ。『未来は今』(1994年)でも存分に発揮されたベビーフェイスがもたらす純真無垢なイメージ、さらに『ザ・プレイヤー』で見せた危険な知性と悪意、これらを両立させてしまう演技力は、本作で演じたアンディのミステリアスな人物像にも大いに役立っている。ちなみに原作のアンディは「小男」という設定だが、身長195〜6cmのロビンスが脱獄に挑むことで、さらにサスペンスは倍増。いろいろな意味で秀逸なキャスティングだ。





















