「荘子itは電気蝶の夢から覚めるが」vol.1
荘子itによる批評連載スタート 第1回:『Mank/マンク』から“名が持つ力“を考える

3.彼はなぜ“Herman”ではなく“Mank”と呼ばれるか
批評家/思想家の柄谷行人が『探求2』において行った整理に従えば、「固有名」が持つ注目すべき性質とは、「一般性」の中で「他ではない」と区別する「特殊性」ではなく、そのような体系の中での記述の差異に還元され得ない、「他ならぬこのもの」を直接に示す「単独性」である。
それ自体が柄谷「固有」の用法である「単独性」と「特殊性」の区別を短い紙幅で詳細に定義し尽くすことは本来難しい。あえて即席で感覚的に理解してもらうならば、例えば次のような説明があり得る。「豚」という「一般性」の中で、「一級ブランドの食肉用の豚」は、他の凡百の豚と比べて貴重なものであり、その意味で「他ではない」「特殊性」がある。それをあなたは美味しく頂くだろう。しかし、「ペットとして可愛がって育てた豚」は、多くの場合名前をつけるだろうし(そして実際に名前をつけたかどうかに関わらず)、「固有名」的な存在であり、それがどんなにありふれた豚であろうとも、「他ならぬこの豚」である以上、「単独性」を持ち、あなたはそれを食べることを躊躇うだろう。(余談だが、『豚がいた教室』という映画はこの点を議論し尽くす前に教育という名目で「他ならぬこの豚」を食べるという恐るべき結末が用意されていて、荘子itにとっての「トラウマ映画」である。)
さてこの概念を実際の作品に対してどう使えるか。『市民ケーン』というタイトルは、映画史(=「歴史」)において「単独的」な「固有名」であるが、その名をあえて記号として分解してみる。「(新聞王)ケーン」という特権的な「名」は、誰よりも成功を手にした男を表すので、人類一般の中で秀でる「特殊性」を帯びたメディアを賑わす記号であるとも言えると同時に、それに「市民」という「一般性」を表す普通名詞が冠されていることで、落差が生まれる。「並外れた成功者」(特殊性)のイメージを帯びたケーンもまた、多くの人々と同じく、一人の「市民」(一般性)である(『市民ケーン』の劇中でも、ケーン自らそのようなイメージのアピールとしてこれを自称するシーンがある)(註:3)。また、ケーンが死の直前に口にした“Rose Bud”という言葉も、少年時代のソリに刻印された文字のことで、あらゆる成功を手にした彼が最期に望んだのは、母親と過ごした少年時代の幸福な思い出で、結局それは他のどんな財によっても埋め合わせ難いものだった、というのが『市民ケーン』の基本的な感動惹起構造である(むろん、有名な「実は“Rose Bud”というのはハーストが愛人のマリオンの女性器につけたあだ名」というエピソードも描かれているので、この部分のフィクションとしての解釈は「映画的」に多様に開かれている)。そうして、記号やイメージが引き剥がされたところでようやく、ケーンという人物の「単独的」な有り様が映し出されるというわけだ。
柄谷の「固有名」の議論で重要なのは、「固有名」が、「話すー聞く」という対等な関係からではなく、「教えるー学ぶ」のような非対称な関係によって伝達されるということだ。それも、『市民ケーン』という「固有名」の伝達が、 デヴィッド・フィンチャーの場合は「父と子」の間であり、荘子itの場合は授業での「教師と教え子」の間であったりしたという具体的なことに限らず、原理的に、「固有名」の「単独性」は、同じルールを共有する間柄ではない関係によってしか伝えられない(柄谷はこのような形でのコミュニケーションのあり方を「命がけの飛躍」と表現している)。仮に、「固有名」を伝達された子や教え子が、それを元とは全く別の意味で理解したり使用したりしたとしても、元を辿れば、それが使われてきた固有の歴史性は残り続けるので、「単独性」は消えないとした。
「固有名」が記述に還元できないと言った通り、たとえ、「『市民ケーン』を書いたのはハーマン・マンキーウィッツ一人だった」(=『スキャンダルの祝祭』の主張)という命題や、反対に、「やっぱり『市民ケーン』はウェルズとハーマンの共同執筆だった」」(=『スキャンダルの祝祭』への反論)という命題が真であり、それ以前の『市民ケーン』に関する記述が訂正されたとしても、やはり『市民ケーン』の「単独性」は消えないということになる。
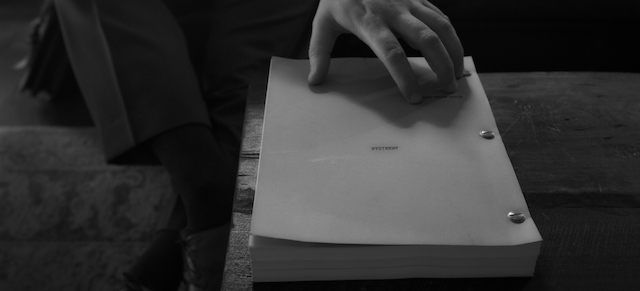
この議論については、柄谷の影響下にある批評家/哲学者の東浩紀が初期の著作『存在論的、郵便的』で批判的検討をしている。東によれば、このような、「固有名」がいくら訂正されようとも「単独性」を持つという議論には注意しなければならないと指摘した。東は本書を通して、一つの空虚な中心を前提とした否定神学的思考には批判的であり、「固有名」が「単独的」であると言う柄谷の議論を転倒させ、むしろ、「単独性」より、「固有名」が事後的に訂正可能であること(=「訂正可能性」)の方が、現実の(誤配にまみれた「郵便的」)コミュニケーション空間に開かれた議論としてより重要であるとした。その後の2000年代の批評が、比較的、「アーキテクチャ」や「二次創作的」なものを積極的に語る方向に向かったのはそのためである。また、より文学的な見地からは、ループものや可能世界の議論を経て、再帰的に一回限りのこの生を肯定するに至る過程を描き出す試みがなされた。『市民ケーン』もまた、他の様々な形でもあり得る可能性を帯びているからこそ、これだけ強い「固有名」として残り続けているのだ。
その意味で、『スキャンダルの祝祭』を下敷きにした『Mank』は、『市民ケーン』や「オーソン・ウェルズ」、「ハーマン・マンキーウィッツ」といった「固有名」の「訂正可能性」についての作品である。

しかし、果たして『Mank』の可能性はそれに尽きるだろうか。『市民ケーン』という作品の虚実交えた二次創作として、あるいは、単独的な映画史への批評的アプローチとしてのみ機能するのだろうか(実際、本作を手法的側面、例えば30-40年代オマージュに見える様々なギミック、タイトルロゴや音声や照明が、現代のデジタル技術でしかありえない仕方でアップデートされていることに注目し、「見かけ上はヴィンテージだが、実は極めてモダンな作りによる、古典的ハリウッド映画様式への批評」とみることができるだろうが、本稿の論旨からはずれるので割愛する)。
※註3:あるいは、“Citizen Kane”の企画当初のタイトルが“American”(アメリカ人)だったことから、「市民」という言葉を、単なる一般市民としてではなく、「アメリカ」という国の固有な歴史における「単独性」と理解することも可能である。(そもそも、「citizen=市民」という言葉自体が、国家に対して積極的に関わる「近代的主体」という意味で、単なる「民」や「大衆」とは定義的に異なるものであることには注意すべきだ)




















