デヴィッド・フィンチャー監督にとっての『市民ケーン』 Netflix映画『Mank/マンク』を解説

物語は、ゲイリー・オールドマン演じるハーマン・J・マンキーウィッツが『市民ケーン』の脚本を執筆する“現在”の時間と、彼が脚本にかかる前、カリフォルニア州知事選の期間にハリウッドで過ごした日々が“過去”の時間として、二つの時間が並行して語られていく。この構成は、まさに『市民ケーン』で、ケーンの死後の時間と、ケーンの半生が並行して語られていく試みに近い。そして、ベッドで酒ビンを落とすシーンなど、やはり『市民ケーン』にオマージュを捧げるような映像が、同じモノクロームで再現されている。
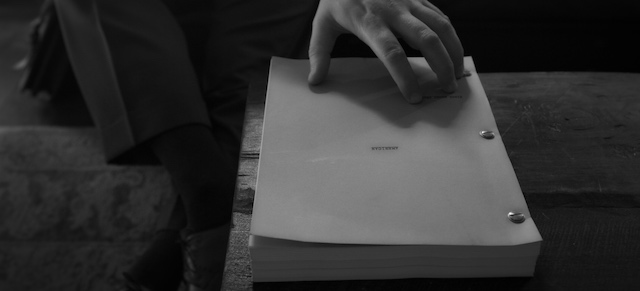
『市民ケーン』が、ケーンの発した最後の言葉“薔薇の蕾”の謎を追っていく一種のミステリーだとするならば、本作はハーマン・J・マンキーウィッツが、あのようなきわめて挑発的で攻撃的といえる脚本をなぜ書いたのかが解き明かされていく趣向となっている。もちろん、それは本作独自の解釈である。
背景に色濃く存在するのは、政治と映画の関係だ。1930年代の世界的な恐慌のなか、知事選では民主党の候補が労働者の権利をうったえていた。それを苦々しく思っていたのが、保守派の「新聞王」ハーストや、ハリウッドの映画会社の上層部だった。なかでも、映画会社メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)の創始者の一人であるルイス・B・メイヤーは、スタジオで映画を作りあげるスタッフの賃金をカットすることで上層部の利益を確保するような人物として描かれており、彼のような人物にとって、大企業に不利な政策方針をとる政治家は邪魔なのだ。
そして、当時のMGMには“天才少年”と呼ばれる敏腕の若手プロデューサー、アーヴィング・タルバーグがいた。本作では、ハーストやメイヤー、タルバーグが、映画などメディアの力を利用して知事選をコントロールする様子が描かれる。なかでもショッキングなのは、ニュース映画において“やらせ”が行われるという描写だ。そこでは、大企業を優遇する政策をとっているはずの当時の共和党候補が、むしろ民衆の味方であり、貧困層から熱烈に支持されているかのように、事実を歪曲した演出が施されていた。この製作に関わり、ニュースを製作した人物は、深い後悔を感じて精神を病んでしまう。

かつてハリウッドの大女優ローレン・バコールは自叙伝にて、自分をスターダムに押し上げた恩人でもある名匠ハワード・ホークス監督が、スタジオの経営陣について、「ユダヤ人は金だけ出していればいいんだ」と仲間内で差別的にののしっていた事実を暴露している。ハリウッドの名だたるスタジオの創始者たちはユダヤ系であり、映画をつくる資金や大権は彼らが握っていた。
ホークス監督は、ハリウッドの歴史を代表する映画監督でありながら、このように口汚いものいいをしてた粗野な人物としても、当時の記録に記されている。荒野や草原でロケをした大スペクタクルの西部劇『赤い河』(1948年)の撮影時、知性派俳優のモンゴメリー・クリフトは、主演のジョン・ウェインとホークス監督が、あまりに粗野な会話を続けるために彼らを避け、孤独に現場で過ごしていたという。
しかし、なぜホークス監督は、経営陣を悪し様にののしっていたのだろうか。それは、資金を提供する者ではなく、自分のように実際に映画製作を指揮する“アーティスト”こそが、真に映画を生み出しているということを主張したかったからではないか。このようにハリウッドにおいて、資金を用意する者たちと製作する者たちの間は、歴史的にも分断されているところがある。
ハーマン・J・マンキーウィッツは、持ち前のユーモアで一時はウィリアム・ハーストに気に入られ、彼のそばでジョークを言うなどして、「面白い奴」と喜ばれていた。だが『市民ケーン』の内容がハーストや、その愛人で映画スターであるマリオン・デイヴィスを中傷するようなものであることが知れると、ハーストの息のかかった映画人たちから「身の程を知れ」「モンキーウィッツ」などとののしられる。ハーストが「オルガンを弾く猿」の話をすることも象徴的なように、ハーマンは実業家ハーストから猿回しの猿としてしか扱われていなかったのだ。

ハーストが別世界に生きていることは、彼の持つ邸宅の一つである“ハースト・キャッスル”を見れば一目瞭然だ。カリフォルニアの広大な土地に、動物園や飛行機の発着場ほか様々な施設が並ぶ。巨大な城は、『市民ケーン』では「ザナドゥ(桃源郷)」と称され、ケーンの富の豊かさを誇るシンボルとして紹介されるが、2番目の妻スーザンに「こんな場所、面白くも何ともない!」と文句を言われるという描写を、ハーマンは脚本に入れている。本作はその理由を、アマンダ・セイフライド演じるマリオンとハーマンのひそかな恋愛に結びつける。
演技力の拙さをたびたび世間から批判されていたマリオンだが、ハーマンは彼女に合った配役がされていないことを劇中で指摘する。これは、『市民ケーン』で、ケーンがスーザンをオペラ歌手に無理に仕立て上げようとした箇所に相当する。本作のハーマンは、彼女のことを真に分かっているのはハーストではなく自分だと言いたいのである。






















