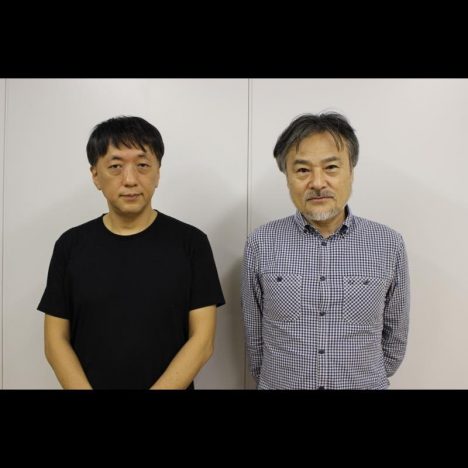宮台真司の月刊映画時評 第9回(後編)
宮台真司の『ザ・スクエア 思いやりの聖域』評:この世に存在しながら存在しない、子供の指し示す幽霊性

キーワードは“子供”と“幽霊”
現代アートの滑稽さは、この社会における生き方の滑稽さです。僕らは「万人は平等」などと言うけど「仲間内での平等」しか意味していない。「差別はダメ」という作品のメッセージが理解できない人を「レベルが低い」と差別します。右も左もおためごかし。誰もが同じで、言うこととやることが違う。言葉を実践が裏切っている。それが見過ごされているのは、界隈に住むから。界隈に住めば「見たいものを見て、見たくないものを見ない」営みをスルーして貰えます。
主人公クリスティアンもそう。思いやりの大切さを説く上流階級のスノッブがアートを理解しない移民を差別する。差別を前提として成り立つ社交界で資金集めパーティをやる。その場を異化するべく有名な“ドッグマン”ことオレグ・キューリクをモデルにした猿人間が出てきます。パフォーマンス(見世物)かと思いきや、レイプに及ぼうとします。本当のカオスが生じてパーティ会場でボコられて終わります。犯罪を通してようやく「見たいものしか見ない枠=スクエア」の存在が暴露された。アートよりも犯罪のほうがアートである――――。
僕がスラスラ喋れることからも「問題」がとうに決着しているのが分かるでしょう。だから映画を観ていて途中まで不安でした。20世紀半ばに決着がついた問題を描いて一体どうやってケリをつけるんだと? ところがケリは子供でした。とばっちりに抗議してクリスティアンに付きまとう貧困マンションの男児が幽霊性が示されます。アートならぬ子供の幽霊性を通じてクリスティアンは覚醒、オルタレーション(翻身=戻れない変身)をします。父親をクズだと思いつつ事態に怯える彼の娘たち。その眼差しをクリスティアンは途中から絶えず感じるようになる。「子供に見られる存在」となることを通じて彼は覚醒していく。
でも幽霊性を帯びた子供のまなざしで一体「何に」覚醒したのか? それがこの映画で謎として残されます。でも子供まみれで暮らしていらっしゃる方は何となく「世界は確かにそうなっている」と感じたはず。どうなっているのかと問われると言語化が難しいが、何となく「そうだな」と。それをアレゴリー(寓意)と言います。子育てほど名状しがたい体験に満ちたものはない。子育てには愛に満ちた平穏と地獄のカオスがある。その両義性にこそヒントがあるのかなと。
平穏とカオスの奇蹟的両立を支えるのは抽象的な概念やゲームならぬ、生のエネルギーです。映画では定番だから「そこに落とすのかい」と思いましたが、やがて「そこに落とすのならいいか」と変わりました。言葉とりわけ文字誕生以降 の、詩的言語ならぬ散文言語を頼る文明(大規模定住社会)に、普遍的な問題を扱っていて、新しい処方箋がないからです。処方箋は生き方に関わりますが、「こう生きればいい」と言い切れば、先の反権力や反制度と同じ袋小路に入ります。僕ならば“なりすませ”と言います。キュレーターになりすます。アーティストになりすます。教員や会社員になりすます。子供に促されて子供のような幽霊性を身に纏う。言葉の世界を生きながら生きないことを「選ぶ」のです。この世に存在しながら存在しないこと。それが子供の指し示す幽霊性です。
■宮台真司
社会学者。首都大学東京教授。近著に『14歳からの社会学』(世界文化社)、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』(幻冬舎)など。Twitter
■公開情報
『ザ・スクエア 思いやりの聖域』
監督・脚本:リューベン・オストルンド
出演:クレス・バング、エリザベス・モス、ドミニク・ウェスト、テリー・ノタリーほか
配給:トランスフォーマー
後援:スウェーデン大使館、デンマーク大使館、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本
2017年/スウェーデン、ドイツ、フランス、デンマーク合作/英語、スウェーデン語/151分/DCP/カラー/ビスタ/5.1ch/原題:The Square/日本語字幕:石田泰子
(c)2017 Plattform Produktion AB / Societe Parisienne de Production / Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office ApS
公式サイト:www.transformer.co.jp/m/thesquare/