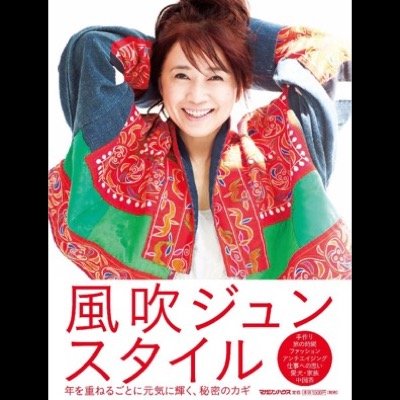成馬零一の直球ドラマ評論『あさが来た』
『あさが来た』はなぜ成功したのか? “鬱展開”を排除した作りと、キャラクターの魅力
連続テレビ小説『あさが来た』(NHK)が完結した。
本作は明治時代に活躍した実業家・広岡浅子をモデルとした白岡あさ(波瑠)を主人公とした朝ドラだ。京都の豪商・今井家の娘として生まれたあさは大阪の両替店・加野屋に嫁ぐ。やがて義父に実業家としての才能を見込まれたあさは、幕末の激動の時代を得て、炭鉱開発、銀行設立、日本ではじめての女子大学設立、生命保険業への進出といった新事業に次々と挑んでいく。
舞台こそ、朝ドラ初となる幕末からスタートする時代モノだが、史実を元にした女の一代記をWヒロインで描くといった、近年の朝ドラが確立した成功フォーマットに忠実で、ここ数年の朝ドラの集大成とでも言うような作りとなっていた。
何より思い切りがよかったのは、視聴者が不快に思う要素を極限まで排除したことだろう。悪役を作らない、画面に極力映さない、対立場面は引っ張らない、という戦略を近年の朝ドラでもっとも感じたのは『あまちゃん』(NHK)だったが、『あさが来た』では、それがより徹底されていた。
視聴者が不快に思う要素とは簡単に言うと、主人公の行動がうまくいかなくて空回りする場面や、主人公の価値観を否定する悪役が登場して、主人公を精神的に追い詰める場面だ。そういった場面が長く続くと鬱展開と呼ばれ、視聴者は離れていく。そんな過去作の失敗が、本作では活かされていた。
とはいえ、基本的にドラマとは異なる価値観を持つ者同士の対立を描くものである。その前提があるからこそ、「悪人と思ったら本当はいい人だった」といったカタルシスが生まれる。しかし、あさの姉・はつ(宮崎あおい)に対する姑の菊(萬田久子)の嫁いびりの淡泊さを筆頭に『あさが来た』は、主人公と対立する悪役めいた存在は極力登場させず、仮に登場したとしても、対立を引っ張らずに、すぐに解消してしまう。それをもっとも強く感じたのは、炭鉱で落盤事故が起きた回だった。犯人のサトシが、実は新次郎の幼なじみで、加野屋を逆恨みしている松造(長塚圭史)だと分かる場面は、あさと新次郎を中心とした世界を全否定する人間がはじめて出てきたことに興奮したが、そんな松造も、あっさりと退場してしまった。
松造の存在は、新次郎がお金を扱う家業を憎むきっかけとなった新次郎の人格形成にもっとも大きな影響を与えた人物だ。そんな松造が、あさと新次郎が事業を起こす度に、「弱者の復讐」と言う形で嫌がらせを仕掛けてくる作りにすれば、本作の根底にある、商売は本当に人を幸せにするのか? というテーマがもっと深まったのではないかと思う。
ひいき目に見ても、物語として本作が面白かったのは、ディーン・フジオカが演じた五代友厚の退場までだろう。銀行設立、日の出女子大学設立といったあさの挑戦は続くのだが、時代背景の描き方が希薄になっていく。あさの身内だけで話が進んでいき、外部がどんどん描かれなくなっていくことに対して、居心地の悪さを感じた。
本作の制作総指揮を担当する佐野元彦が手掛けた大河ドラマ『篤姫』(NHK)は、このバランスが絶妙だった。篤姫(宮崎あおい)が大奥で過ごす豪華絢爛な日常と、幕末の維新志士が命を落としていく血なまぐさい物語を対比させることで、幕末のダイナミズムを描きだすことに成功したが、『あさが来た』においては、血なまぐさい現実や貧困が生み出す弱者の問題は、あくまで見えない場所で展開されていた。