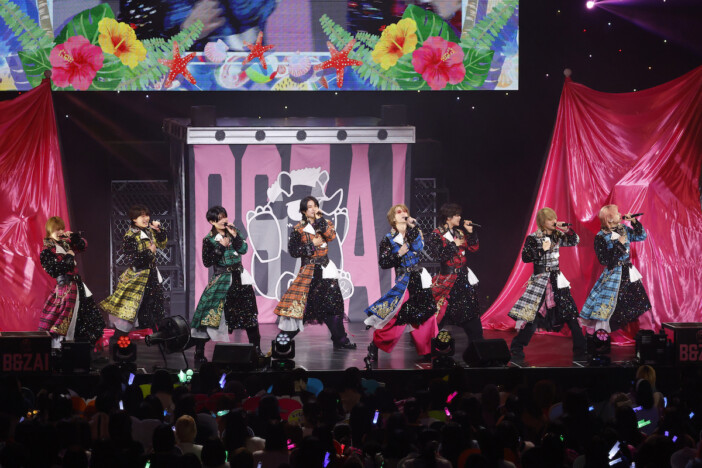LAMP IN TERREN、葛藤から抜け出す“希望”を感じさせた2度目の日比谷ワンマンを観て


アンコールで現れた4人は少しだけ安心したような顔をしていた。そして秋のツアーと年明けの東京公演の告知をしたあと、松本は「サクッとやったほうが次につながる気がするからさ。だから、やるわ」と言って、「緑閃光」を演奏した。4人がステージを去っても、月は会場を照らし続けた。現在のこのバンドが映し出された2時間だった。
そんなライブだっただけに、僕はつい、かつてのこのバンドと、今の彼らの姿とを脳内で行き来させながら見ていた。僕は4年前、アルバム『LIFE PROBE』のリリース時に、テレンの歌の世界に関しての考察をこのリアルサウンドに寄稿している。(LAMP IN TERREN、松本 大の歌が放つ存在感 各楽曲の世界観を読み解く)当時に比べてライブの場での彼らはかなり積極的になっていて、オーディエンスへの声かけもあるし、演奏面での充実は著しい。この間にギタリストの大屋が加入したのも重要な出来事だ。
そしてテレンの最大のポイントである松本の歌だが……「僕」、あるいは「俺」を中心にしながら、そこで自身の内面への問いかけや、その歌が結果として「いかにして生きるか」というテーマ性につながっていることは変わっていない。また、天体をモチーフにした描写も、そこで「光」「灯り」を求める意志も、同じくだ。
ただ、この4年の間に松本にとって大きかったのは、彼自身が大きな挫折を味わったことだった。自分の理想を強く求め、そのために「化身を演じていた」(筆者が別メディアで取材した際の発言)というが、活動を続ける中で、その理想の手前で現実の巨大な壁にブチ当たり、思うように曲が書けなくなった。どんな歌を唄えばいいのかが見えなくなったのだ。バンドの動きが鈍くなった2、3年ほど前は、とくにそんな時期だったのである。追い込まれた松本は、そこでまとっていた化身のベールを脱ぎ去って、自身をさらけ出す歌を書くようになった。自分のダメなところも、情けない部分までも。それを「本音を唄うようになった」と言えば聞こえがいいが、つまり、そのぐらい振り切れないと身動きが取れなくなっていたということだ。テレンにとってのこの数年は、こうした苦悩と葛藤の連続だった。
しかし今、彼らは、その苦い季節から抜け出しつつある。「ホワイトライクミー」には〈何もないなんて寂しい事は言うな 僕が望んだ場所にいないだけだ〉という詞がある。自分が望んだ場所にはいれなくとも、また別の場所で、違う輝きは得られるはず。そうした希望はある、ということなのだろう。
「もっと素晴らしい景色を見せるつもりだから。これからもよろしくお願いします」
アンコールの「緑閃光」の後半で、松本はそう言った。僕もそれを願う。だからこれからの彼らは、もっとアグレッシブであってほしいと思う。

この先彼らが新しく作る曲は、今までとは違うファンの心をつかむものにまでなってほしい。チャンスがあれば、ヒットチャートに入ることだって可能なはず。対バンやイベントに出た時に、自分たちらしい演奏をするのは当然として、そこでほかのバンドを食ってしまって、そのお客さんを持っていくとか、まったく違う、新しいリスナーを引き込むとか。そのぐらいの貪欲なライブができると思うのだ。こう考えるのは、初期から見てきた筆者にとって、テレンはあまりにも自分たちのストーリーを走ることに懸命で、内側に向きがちで、そこで足を取られそうになっていたように見えたからだ。だから思う。ここから外に目を向け、もっと遠くに向かって戦っていってほしいと。
デビューからもう少しで5年、メンバーも20代後半。機は熟した。今の彼らに、もうそれだけの下地はできている。優しい月の光を見ながらそんなことを考えた、夏の夜だった。
(文=青木優/メイン写真=浜野カズシ)
■リリース情報
「ホワイトライクミー」
発売:7月17日(水)
ダウンロード/サブスプリクションサービスで配信中
配信はこちらから