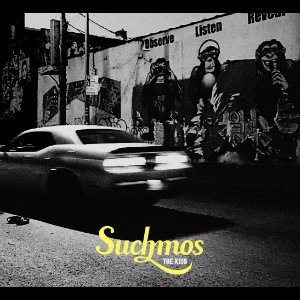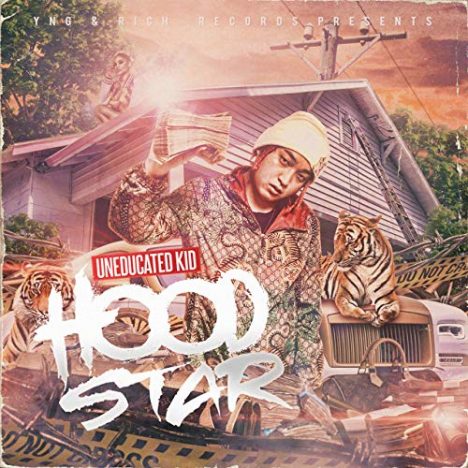『Ghost Notes』インタビュー
Kan Sanoが追求するサウンドのオリジナリティ 全てを一人で作り上げた『Ghost Notes』を語る

鍵盤奏者Kan Sanoによる、通算4枚目のアルバム『Ghost Notes』がリリースされる。
前作『K is s』からおよそ2年ぶりとなる本作は、作詞作曲はもちろん、演奏やミックス、そしてボーカルまで全てを一人で行い作り上げた意欲作。彼の原点である90年代ネオソウルや70年代ブラックミュージックに根ざしながらも、低音の作り込みやレンジの広がりなど「ジェイムス・ブレイク以降」のサウンドプロダクションが施されており、さらにSanoが持つメランコリックなメロディセンスやコード感が絶妙にブレンドするなど、唯一無二のオリジナリティを誇っている。
なお、初回盤にはディアンジェロやエイドリアナ・エヴァンス、サム・クックなど「今作を作る上でインスピレーションを受けた」というアーティストの楽曲を、ソロピアノでカバーしたボーナスディスクを付属。彼のルーツを知る上でも貴重な内容だ。
CharaやKIRINJI、藤原さくらなどジャンルも世代も様々なミュージシャンからラブコールを受け、プロデュースやリミックス、客演といったコラボレーションを展開。トム・ミッシュら海外アーティストも注目し、最近では自身がリーダーを務めるバンド、Last Electroとしての活動も精力的に行なっているSano。様々な「顔」を持つ彼は一体何者なのか。リアルサウンドでは初登場となる彼に、新作はもちろんライフストーリーについてもじっくり聞いた。(黒田隆憲)
音楽以外、他の選択肢は何もなかった
ーーもともとSanoさんは、どのようなきっかけで音楽に目覚めたのですか?
Sano:小学校5年生くらいの頃、ちょうどMr.Childrenが流行っていて。「かっこいいな」と思って家にあったクラシックギターを引っ張り出してきて、見よう見まねで弾き語りをしてみたのが最初ですかね。家にはピアノもあったので、習っていた時期もあったんですけど続かなくて。音大に行くまではほぼ独学で弾いていましたね、The Beatlesの譜面を見てコードを覚えたり。入口がポップスやロックだったので、クラシックの楽曲を譜面通りに弾くのはあまり好きじゃなかったんですよ。それよりはコードを押さえつつアドリブを入れながら弾く方が楽しかったのだと思います。
ーーミスチルがきっかけだったのですね。Sanoさんのポップセンスはそこから始まっている。
Sano:初めて買ったCDが『innocent world』(1994年)のシングルで、その年にThe Beatlesも聴き始めて。『Abbey Road』(1969年)が最初だったのかな。そこからはThe Beatlesのアルバムをひたすら聴いていました。中学校の3年間はそんな感じでしたね。未だにThe Beatlesは好きで聴いています。
ーー曲作りを始めたのもその頃?
Sano:そうですね。「自分で作った楽曲を、自分で演奏して歌いたい」という気持ちが強かったので、割と早くから曲作りはしていました。録音機材なども何も持っていなかったし、使い方もそもそも分からなかったんですけど、ラジカセを2台使ってピンポン録音などをしていました。
ーー思えばThe Beatles周辺にも、素晴らしい鍵盤奏者がいましたよね、ビリー・プレストンとか。
Sano:好きでしたね、ニッキー・ホプキンスとか。The Beatlesから好きになったミュージシャンは、例えばエリック・クラプトンとか鍵盤奏者以外でもたくさんいました。
ーーそこからブラックミュージックへたどり着いたと。
Sano:The Beatlesを聴いていた頃から、ファンキーなものが結構好きで。彼らの楽曲の中でもブラックミュージックの要素があるもの、例えば「Taxman」や「I’ve Got a Feeling」のような、16ビートの楽曲に惹かれる傾向があるって自分でも気づいたんです。それで、スティーヴィー・ワンダーとか有名な人から入っていって、さらにビル・エヴァンスやハービー・ハンコックのようなジャズ界隈にも興味がいって。

そうすると、いろんなテンションノートとか知るようになり、もっと複雑なボイシングがあることも分かってくるのですが、自分ではどう弾いたら良いのか分からなくて。やっぱりジャズとかアカデミックなことをやろうと思うと、独学では限界があったので、ちゃんと勉強したいと思って留学しました。バークリー(音楽大学)はピアノ専攻ジャズ作曲科で、ビッグバンドのスコアなどを研究しつつDTMも本格的にやるようになりました。
ーー以前、お話を聞いたときに「ディアンジェロやエリカ・バドゥのヨレた演奏の凄さは、向こうへ留学してわかった」とおっしゃっていましたよね?
Sano:そうなんです。留学前はジョン・スコフィールドやMedeski Martin & Woodのようなジャムバンドが好きで、地元の大学のジャズ研の人たちとそういうバンドを組んでいました。で、留学した頃というのはヒップホップがルーツにあるような音楽を、プレーヤーたちが生で演奏していたのが印象的だったんですよね。みんなThe ROOTSのクエストラヴが大好き、みたいな(笑)。その流れでディアンジェロの『Voodoo』(2000年)を聴き直してみた時に、これはすげえアルバムだなということに気づいたんです。
ーー帰国してからは、すぐに音楽の仕事を精力的にされていたのですか?
Sano:いや、今のように仕事は全然なくて。ホテルのラウンジでピアノを弾いたり、箱バンやピアノのレッスンをやったりしていましたね。その合間を縫って、デモテープを制作して。当時はアメリカよりもイギリスやドイツの音楽、例えばクラブジャズやクロスオーバー系の音楽が好きだったので、ジャイルス・ピーターソンのレーベルにはよくデモを送っていましたね。

ーーそういう活動を、当時は1人でやっていたのですか?
Sano:2006年に東京に出て来て、2011年に初めてアルバムを出すのですが、その間は完全に1人で動いていました。自分でMySpaceやSoundCloudに音源をアップしていましたが最初は反応も全然なくて。めちゃくちゃ辛かったですね(笑)。
ーーそんな中、当時はどんなモチベーションで続けていたのでしょうか。
Sano:音楽以外の道は考えられないというか、他の選択肢は何もなかったんですよね。小学校の卒業アルバムに「将来の夢はミュージシャンになること」と書いて以来、それしか見ていなかったのかも(笑)。
ジャイルスに初めてラジオでかけてもらったのが2010年だったと思うんですけど、その時はメチャメチャ嬉しかったですね。その時のことは忘れられない。あと、初めてコンピレーションCDに入れてもらった時とか。続けていてヘコむことや落ち込むことも多かったですけど、そういう成果が少しでもあると、それが糧にはなっていたと思います。
ーーなるほど。
Sano:SNSを使い始めてからは、国内外の様々なリスナーからダイレクトな声が届くようになり、それもモチベーションとしては、かなり大きかったと思います。曲を作ってその日の晩にアップすると、1分後には「やべえ!」みたいなコメントがバーっと来るっていう(笑)。その反応の速さには結構力づけられました。
ーー1stアルバム『Fantastic Farewell』をCIRCULATIONSから出したのは2011年ですね。
Sano:レーベル元のCIRCULATIONSがビートミュージックの強いところで、僕的にもすごく好きなジャンルだったので、サウンド的にはそっちへ振り切ったアルバムになりました。
ーーorigamiへの移籍は、mabanuaさんのサポートがきっかけ?
Sano:そうです。移籍して、最初に作ったアルバムが『2.0.1.1.』(2014年)。その時に目指していたのは、自分が好きなビートミュージックの要素と、自分の強みであるピアノストとしてのキャラクターを融合させたサウンドでした。当時は「Bennetrhodes」という別名義でアルバムを出すなど他にも色々やっていたんですけど、自分で何をやりたいのかわからなくなっていて(笑)。それでスタッフから出たアイデアに乗っかってみる形で始めたんです。