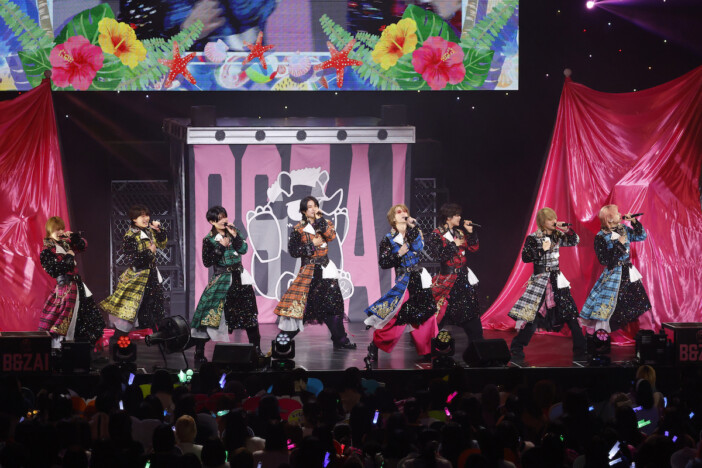細野晴臣『HOSONO HOUSE』なぜ海外で再評価? “観光音楽”がいま注目集める理由を考察
ここ数年、70年代〜80年代の日本のポップミュージックが海外から注目されている。昨年3月にはアメリカ・シアトルのレーベル<Light In The Attic>が日本の名曲をリイシューする“Japan Archival Series”を始動。第1弾の『Even a Tree Can Shed Tears: Japanese Folk & Rock 1969-1973』(2017年10月発売/CD4枚組)には、金延幸子「あなたから遠くへ」、加藤和彦「アーサー博士の人力飛行機」、はっぴいえんど「夏なんです」、そして、細野晴臣の「僕は一寸」などが収録されている。本作はニューヨークタイムズで特集が組まれるなど(The Hidden History of Japan’s Folk-Rock Boom)、現地でもかなり大きな話題となった(この記事のなかで触れられている2014年の『Red Bull Music Academy』における、海外ジャーナリストの細野さんへのインタビューも非常に興味深いのでぜひ)。同シリーズからはシティポップ、AORを中心にした『Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR & Boogie 1975-1985』もリリース予定ということで、こちらも楽しみだ。
なかでも特筆すべきは、細野晴臣に対する注目度の高さだ。今年8月には、カナダ出身のシンガーソングライター、マック・デマルコが細野晴臣の「Honey Moon」(アルバム『トロピカル・ダンディー』収録/1975年)のカバーをシングル配信。以前から細野をはじめ、山下達郎、矢野顕子、吉田美奈子などの日本のアーティストからの影響を公言しているマック・デマルコだが、「Honey Moon」のカバー(すべて原曲通り、日本語で歌っています)における東洋的なエキゾティシズム、眩いばかりのサイケデリアを感じさせるサウンドからは、1970年代の細野の音楽に対する強いリスペクトが伝わってくる。

さらに10月3日にはアメリカの音楽メディア『Pitchfork』に細野晴臣に関する記事(Haruomi Hosono:Hosono House)が掲載された。『HOSONO HOUSE』『はらいそ』『CHOCHIN MOON』『フィルハーモニー』『オムニ・サイト・シーイング』の5作のアメリカでの再発盤を受けての記事で、70年代〜90年代における細野のキャリアを俯瞰した内容となっている。80年代初めに細野が提唱した“観光音楽”というコンセプトを縦糸、時代によって変化しながら、古今東西の音楽を再発見・再構築するセンスを横糸としながら、細野晴臣という音楽家の全体像を捉えようとしているのだ。
記事の冒頭では、はっぴいえんどの成り立ちと解散後のキャリアについて説明している。ざっくり要約すると「1960年代のはじめ、東京・渋谷を中心にした音楽シーンを拠点にしていた“はっぴいえんど”は、西洋の音楽のリズムに乗せて母国語で歌うはじめてのグループだった。これだけでも彼のキャリアを決定づける生花だが、解散後も細野の創造性は旺盛で、フィル・スペクターのThe Wrecking Crewに対する日本からの回答と言うべき、彼自身の音楽仲間とティン・パン・アレーを結成した」というわけだ。
この記事のなかで、個人的に最も印象的だったのは『HOSONO HOUSE』についての記述だった。まず作品の全体像を「an album of what Hosono called “virtual American country”」と位置付け、「冬越え」「薔薇と野獣」を例に出しながら、“ホンキートンク・スウィングのカッコいい(Chunky)リズムからは、この地方(アメリカ)の音楽に対し、彼がどれだけで慎重で、思いやりに溢れていたかが聴き取れるはずだ”と評価。「HOSONO HOUSE」からは、その出発の土地となるアメリカ音楽に対する真摯な姿勢が感じられるというわけだ。