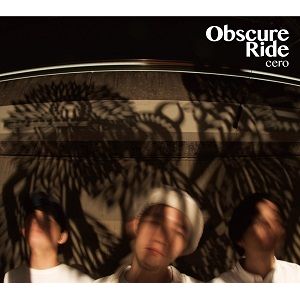『TOKYO MUSIC ODYSSEY 2017』特集第6弾
ceroが考える“都市と音楽の未来” 「今は『オルタナティヴ』な音楽って成立しにくい」

「ceroを始めた頃は、オルタナ感やアンチテーゼは意識してた」(高城)
ーー『TOKYO MUSIC ODYSSEY』は、テーマが「都市と音楽の未来」です。僕らが今住んでいる東京について、何か思うところあります?
高城:僕ら3人はJR中央線沿いにある吉祥寺という場所でよく遊んでいたのですが、高校の頃にみんなで行ってた喫茶店とか、軒並みなくなっているんですよね。当時と比べたら、ほぼ完全に細胞が入れ替わった感があって。残り少なかったいくつかの店も、壊滅状態。『カルディ』もなくなったし、『ダルジャン』っていうスパゲティ屋もなくなってしまって。でもそれは、「都市の宿命」っていうところもあるんでしょうね。みんな年老いていくし。
橋本:そういう伝統あるお店が潰れていくのは、新興勢力というか、新しい企業の力がどんどん入ってきているからだと思うんですけど、見てるとエグイなと思いますね。古いものに対して、あまり重きを置いてないような気がするし、「ちょっと野蛮だなあ」と思う時もあります。
高城:割と「スクラップ&ビルド」的な開発の仕方が多いですよね。「履歴」を残したがらないというか。去年、ニューヨークへ行った時に印象的だったのは、街がすごく古いんですよ。それって、天災や空襲の被害がなかったというのも大きいと思うんですけど。
ーーインフラが昔のまま残っていて、それを補修しながら発展している感じですよね。すごい早さで新開発が進んでいく一方、「リノベーション」という形で古いものを残していこうという動きも最近はありますよね。
高城:そういうパターンもありますよね。例えば吉祥寺の「ハーモニカ横丁」がそう。作ったおじいちゃんたちは代替りして、若い人がうまいこと受け継いで、昔ながらのお店をオシャレに蘇らせたりしている。

ーー東京も場所によって表情が違いますよね。空襲の被害が少なくて、昔ながらの街並みが割と残った西東京の方とか、再開発がガンガン進んで古い景観がほとんどないベイエリアとか、あるいは下町のごちゃっとした区域と、高層ビルが立ち並ぶ区域が混在している新宿とか。それを音楽で置き換えてみると、ceroは東京のどの辺になるんでしょうね(笑)。
高城:なるほど(笑)。うーん、でも音楽は古いものからの影響を受けずに作るのは、ほぼ不可能だと思います。全く新しい、どの文脈にも根ざしていないような音楽があったとしたら、それはもの凄いことですよね。新しく感じる音楽でも、大抵は何かのルーツだったり、何かと何かを掛け合わせたものだったりして、完全に新しいものはなかなか生まれない。「再開発したベイエリア」のような音楽が、もし生まれたらそれは凄いことだと思うけど......。
ーーじゃあ、「ベイエリアが好きな街なのか?」と言われたらそんなことないし、そこはやはり音楽に置き換えるのは無理がありますね(笑)。今回、ceroは『ALTERNATIVE ACADEMY』という枠に登場するわけですが、「オルタナティヴ」という定義についてはどう思いますか?
荒内:「オルタナティヴ」の本来の定義は、「別の選択」ということですよね。でも、音楽ジャンルとして「オルタナティヴ」という言葉が誕生した90年代と比較すると、今は様々なジャンルが乱立する中、いろんなポジションの人がいるわけじゃないですか。そうなると、「メインストリームに対する別の選択」という意味で使われていた頃のようには、「オルタナティヴ」という言葉そのものが使えない気がするんですよね。
ーー確かにそうですね。ある意味、全てが「オルタナティヴ」というか。
荒内:そうなんですよ。だから、今は「オルタナティヴ」な音楽って成立しにくい。
ーーそれだけ多様化したのは、いいことですよね。まさに、「みんなちがって、みんないい」(笑)。
高城:面白い時代だと思います。それこそceroを始めたばかりの頃は、もうちょっと気張りがあったんですよ。今となっては、当時の感覚をリアルに思い出せないんですけど、何かに対してのオルタナ感やアンチテーゼは、割と意識してやっていた。こうやって話してみて思ったけど、今はそんなことほとんど意識せずに音楽を作っていますね。気がつけば、周りはオルタナティヴばかりだし(笑)。

ーーそういえば、新木場コーストのワンマンでやっていた新曲は、さらに変態度が増していました(笑)。今の話でいうと、どこにも属さないような、それこそ「オルタナティヴな曲」だと思ったんですよね。
荒内:あの曲は、アフリカンなリズムを、それこそ「都市的」な感覚で鳴らそうというテーマで作ったんです。アフリカンなものを「アフリカっぽいでしょ?」って演奏するんじゃなくて、僕らがこうやって普通に生活している感じにフィットするよう定義し直したというか、普段着で演奏する感覚。
ーー20年くらい前だと、「アフリカンリズムを日本人がやったってそれはフェイクだ」とか、「そもそも黒人のグルーヴを日本人が体得するのは不可能だ」とか、そういう批評って普通に存在していたと思うんですよ。日本人がブラックミュージックをやるといったら、可能な限り自分のライフスタイルも含めて黒人に寄せていくことが求められていたというか。
高城:ああ、そうですね。ロックやフォークミュージックにしたって、昔は「日本語でやるものじゃない」って言われていましたし。
ーーええ。そういう感覚は、今やもうすっかりフラットになりましたよね。別に黒人に寄せなくても、日本人のフィルターを通したブラックミュージックを演奏すれば、それはオルタナティヴなものになるっていう。そういう土壌作りに貢献してきたバンドの一つは、間違いなくceroじゃないかと。
高城:例えばヒップホップにしても、かつてのロックやフォークのように「日本語でやるもんじゃない」と言われた時代もあったと思うけど、今や街のいたるところで、若い人たちが「サイファー」(ストリートで行うフリースタイルバトル)をやってる。昨年ツアーで全国を回った時も、地方の高架下でやってる人たちを見かけたし。僕ら今年で32歳になるんですけど、こういう変遷を目の当たりにするような歳になってきたんだな、と感慨深くなりました。これから先も、もっともっと変わっていくでしょうしね。