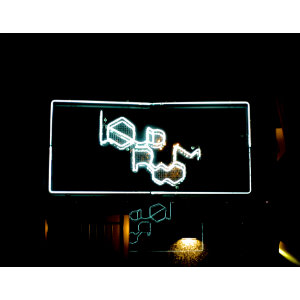2ndアルバム『FASHION』リリースインタビュー
I Don’t Like Mondays.が考える、“世界基準”と“日本らしさ”の両立「ビルボードチャートでも勝負できるものを」

まるでデビュー当時のフランツ・フェルディナンドにも通じる雰囲気で“お洒落な女の子を踊らせる”ことを最大のテーマに掲げ、ソウル/R&Bやファンク、ポップス、インディ・ロックまで多岐にわたる海外シーンの流行を溶かし込んだサウンドを鳴らす4人組バンド、I Don’t Like Mondays.。彼らの2ndアルバム『FASHION』が完成した。
最初から最後までキラー・チューンを詰め込んだ雰囲気だった1stアルバム『TOKYO』に対して、今回の『FASHION』ではアルバム全体の構成を意識。『CDTV』(TBS系)の7月エンディング曲「Tonight」を筆頭にポップな曲はよりポップに振り切れつつも、アルバム曲ならではの実験性を加えることで、『TOKYO』と『FASHION』の2枚でようやくバンドの全体像が把握できるかのような、華やかで巧みなポップ・ワールドを手に入れることに成功している。10月より始まるリリース・ツアーのファイナルとして、11月19日にはキャリア最大規模となるZeep DiverCity(Tokyo)での単独公演も控える彼らに、新作『FASHION』の制作背景を訊いた。(杉山仁)
「『FASHION』という言葉には「流儀」という意味もある」
――今回の『FASHION』というタイトルには、I Don’t Like Mondays.の魅力がよく表われているように思えます。そこでまずは、このタイトルにした理由を教えてもらえますか?
悠(Vo.):ひとつは僕らが音を表現するだけではなくて、ヴィジュアル面でも表現をしていきたいという気持ちがあるバンドだからですね。バンドをやっていて「ファッション」という単語を出すと、「チャラいんじゃないの?」「うわべで音楽をやってるんじゃないの?」と思われがちですけど、僕らは全然そうは思っていないんですよ。むしろ、バンドという形の中で、自分たちができることはすべて表現していきたいと思っているんです。
――そもそも、バンドが掲げている「お洒落な女の子を踊らせる」というテーマも、「お洒落な女の子のジャッジが世の中で一番シビアだ」という考えに基づいたものですよね。
悠:そうですね。やっぱり僕らは、音楽に詳しくない人でも楽しむことができて、かつ玄人の人にも理解されるものが最強だと思っているというか。玄人にだけ向けたものを作るんだったらそこに焦点を当てればいいわけですけど、それよりお洒落な女の子や中高生の子に「すごい」「かっこいい」って思ってもらうことの方が実は難しいことだと思うんです。つまり、「お洒落な女の子を踊らせたい」というのは「ハードルを一番高く設定しよう」ということですね。実際に今の僕らがどれだけ上手く出来ているかは別にしても、この目標ならそう簡単には達成できないし、そこを目指してずっとやっていきたいと思っているんですよ。

――言い換えれば、「シリアスになりすぎない」ことを「シリアスにやっていく」と。前作リリース以降活動が広がっていく中で、その気持ちが強くなってきたりもしていますか?
悠:前は漠然と「お洒落な女の子を踊らせたい」と思っていたものが、もっと明確にどうすればいいか分かってきたり、考えるようになってきた部分はあるかもしれません。実際僕らは、お洒落な女の子のファンが多いバンドだとは感じるんですよ。それに、自分たちが出会う可愛い子たち、皆の心を掴みたいぐらいに考えていて。そういうことがかなり明確に、研ぎ澄まされてきている部分はあると思いますね。
秋気(Dr.):昔から僕らのことを観てくれて、ライブに来てくれている人たちも、ファッションが変わってきたりしているんですよ。メイクが変わった子もいたりして。
悠:そうそう、それは僕らにとって純粋に嬉しいことなんです。そういうところまで楽しめるバンドを目指しているし、ファンの子たちにもそれを感じてもらえたら嬉しい。あと、『FASHION』という言葉には「流儀」という意味もありますよね。デビューから2年経って、最初はがむしゃらだったところから、今はどんなことがやりたいか、どんなバンドを目指したいかということが僕ら自身明確になってきているんです。だからこのタイミングで、自分たちの流儀をヴィジュアルも合わせて表現しようと考えたんですよ。
――その結果、今回の『FASHION』は「Introduction」から始まって、途中にもインストの「Right before sunset」があったりと、全体の構成が練られた作品になっていますね。前作『TOKYO』にあったキラー・チューンをとにかく詰め込むような雰囲気とはまるで対照的です。
兆志(Gt.):前作は当時の集大成としてああいう形の作品になったんですけど、セカンドで一緒のことをしてもしょうがないというのがあって。今回は若い世代の人たちにも、CDを最初から最後まで聴いてもらえるようなものを作ろうと考えたんです。
悠:今の時代ってAppleMusicやLINE MUSICでプレイリストを作ったり、シャッフルして聴くことの方が主流で、アルバム全体を通して聴かない人が多いと思うんです。だからこそ、「そのままでもいいプレイリストになっている」アルバムを作ろうと思ったんです。
――流れを作るにも様々なパターンが考えられたと思うんですが、今回の構成は、具体的にはどんな風に考えていったんですか?
悠:せっかく2作目なんで、作る前から「『Introduction』は入れたい」と思っていたんです。あとはキーとなる曲を並べて聴いていったんですけど、その時に「ここにもっとこういう曲がほしい」というものを作曲していきました。テンポ感もそうだし、僕の場合は歌詞でも、「ここで甘いラブソングがほしいな」と感じたら変えていったりして。前作は全曲シングルとして聴けるものを目指した作品でしたけど、今回はその結果、いわゆる“アルバム曲”のようなものを初めて作ることになったんです。
兆志:これにはライブで感じたことも関係しているんですよ。『TOKYO』を作ってから初めてワンマンを2回やったんですけど、1曲1曲が強すぎて、セットの中で山を作ることが難しく感じた部分があって。だから、今回アルバム曲のようなものを作ることで、リリース以降のライブで「谷」の部分も作ることができると思ったんです。
悠:音数が少ない「Marry me」や「Stranger」はまさにそうやって出来た曲ですね。「Stranger」は2回目のAメロが変わったりしていて、こういうソウルっぽいものもずっとやりたいと思っていた曲です。一方の「Marry me」は、僕個人としては好きなんですけど、このバンドでやるとは思っていなかったようなタイプの曲ですね。

――何しろドラムが入っていないですよね。リズムは秋気さんのシェイカーだけで。
秋気:たぶん『TOKYO』の時の僕らだったら、もっとシングルとして出すことを考えて、こういうアレンジにはしてなかったと思います。でも、今回はアルバムの流れで考えた時に、ここで一回落とした方が全体の中で区切りがついていいと思ったんです。